マイコプラズマ肺炎の基本情報
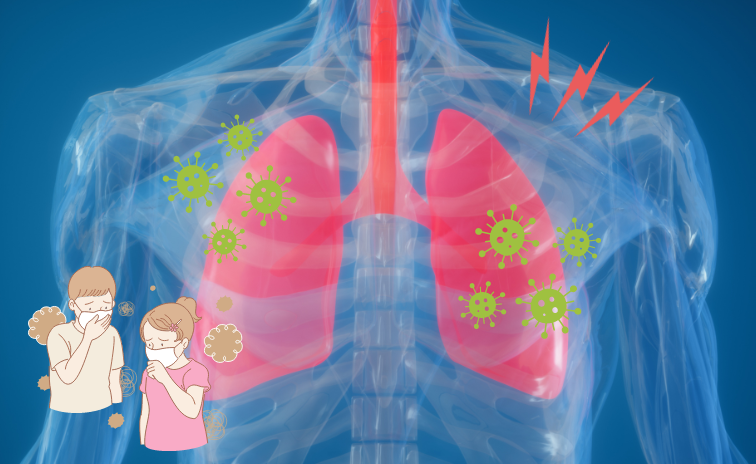
マイコプラズマ肺炎と聞くと、「普通の肺炎と違うの?」と疑問を持つ人もいるでしょう。
マイコプラズマ肺炎は、マイコプラズマ・ニューモニアと呼ばれる細菌に感染することで起こる感染症です。
幼児や学童期の小児の発症頻度が高く、集団生活を通して感染が広がりやすい病気です。
今回の記事では、マイコプラズマ肺炎の症状や特徴、検査、治療などの基本情報を分かりやすく解説します。
「マイコプラズマ肺炎は聞いたことはあるけどよくわからない」という方は、ぜひ最後までお読みください。
1.マイコプラズマ肺炎の症状・特徴
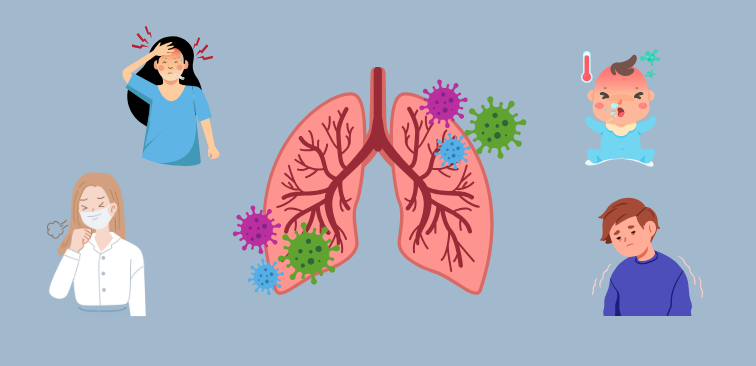
マイコプラズマに感染すると、一般の肺炎とは異なる症状があらわれます。
マイコプラズマでは、初期に以下のような症状がみられます。
・発熱
・全身の倦怠感
・頭痛
初期症状があらわれたあと、3日~5日後に痰のない乾いた咳が出始めます。
咳は経過とともに増強し、解熱後もしつこく続くのが特徴です。
多くの人は、肺炎を起こす前に回復しますが、肺炎を起こし重症化するケースもあります。
重症化すると、以下のような合併症を発症することがあります。
・重度の肺炎
・無菌性髄膜炎(脳や脊髄を包む膜が炎症を起こす病気)
・脳炎
・中耳炎
・中枢性神経症状
重症化しなくても、マイコプラズマ肺炎を起こした人は、肺の機能が低下します。
そのため、早期に治療を受けることが大切です。
マイコプラズマは、幼児や学童期の小児に発症しやすいのが特徴です。
学校保健安全法で「第三種学校伝染病」に指定されています。
特に出席停止期間について明記されていませんが、急性期は出席停止とされており、全身状態が良くなれば登校が可能です。
【参考情報】『マイコプラズマ肺炎』東京都感染症情報センター
https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/diseases/mycoplasma/
2.マイコプラズマ肺炎の検査

マイコプラズマ肺炎が疑われる場合や他の疾患との鑑別のため、いくつか検査をおこなう必要があります。
ここでは、検査の種類や特徴を解説します。
2-1.画像検査
マイコプラズマ肺炎を疑う場合、胸部レントゲン検査とCT検査をおこないます。
<胸部レントゲン検査>
肺の部分に、網状の結節影と呼ばれるものが写ります。
白っぽく丸いのが特徴です。
肺門リンパ節腫大(左右の肺の付け根にあるリンパ節が腫れた状態)が見られる場合もありますが、子どもに多い所見です。
<胸部CT検査>
CT検査では、中枢気管支〜細気管支壁の肥厚と小葉中心性(肺の構造である「小葉」の中心部に異常が現れる状態)の結節影がみられます。
ときには、広範な浸潤影(ぼやけた影)や無気肺(肺の一部または全体が空気を失い、しぼんでしまった状態)のような所見も確認できます。
成人よりも、子どもの方が浸潤影が強い傾向です。
これは、子どもの方が体も小さく、免疫反応の違いが原因だと考えられています。
2-2.血液検査
血液検査では、以下のような項目に特徴的な変化がみられます。
・一般検査で白血球(体内に侵入した細菌やウイルスなどの異物から守る免疫細胞)は上昇
・白血球は正常〜やや上昇
・AST/ALT(肝臓の細胞がダメージを受けると血液中に漏れ出る酵素)の上昇
マイコプラズマの感染の確定診断には、ペア血清と呼ばれるものを確認します。
ペア血清とは、マイコプラズマ抗体の血清免疫反応(血液中の抗体が病原体と戦って排除する免疫反応)を調べるもので、 急性期と回復期の血清を比較して4倍以上の上昇が診断基準となります。
2-3.迅速検査
マイコプラズマ検査では、迅速検査もあります。
特別な綿棒でのどをぬぐい、検体を採取します。
検査をしてから10分~15分程度で検査結果が出るため、早めの診断に有用です。
ただし、ペア血清に比べると参考程度の結果といえます。
LAMP法と呼ばれる検査がありますが、これは精度が高く、マイコプラズマに特徴的なDNAを検出する遺伝子検査です。
発症初期でも有効な検査ですが、結果が出るのに2日程度必要なため、すぐの診断はできません。
【参考情報】『マイコプラズマ肺炎の実験室診断』国立感染症研究所
https://www.niid.go.jp/niid/ja/iasr-sp/2123-related-articles/related-articles-392/2714-dj3927.html
3.マイコプラズマ肺炎の治療

マイコプラズマに感染し、軽症の場合には経過観察で特に治療を必要としないケースもあります。
症状が強くあらわれている場合には、基本的に抗生物質を使用し治療します。
主に以下の3種類の抗生物質が使用されます。
・マクロライド系抗生物質:クラリス、クラリシッド、ジスロマックなど
・テトラサイクリン系抗生物質:ミノマイシン
・ニューキノロン系抗生物質:クラビット、オゼックス
状況に合わせて、使用する抗生物質が異なります。
妊婦や子どもは、マクロライド系の抗生物質が第一選択薬です。
しかし、マクロライド耐性マイコプラズマが存在しているため、2~3日使用しても効果が得られない場合には、別の薬剤への変更を考慮します。
テトラサイクリン系は、歯を変色させたり骨の発達に影響を与えたりすることがわかっているため、8歳以下の子どもには使用しません。
ペニシリン系やセフェム系の抗生物質は、マイコプラズマには効果がありません。
抗生物質の副作用として、腸内細菌のバランスが崩れ、便が緩くなる傾向があります。
そのような人は、一緒に整腸剤も処方してもらうと安心です。
また、抗生物質に対する「耐性菌」の発生を防ぐため、処方された抗生物質はすべて飲み切るようにしましょう。
重症の肺炎を起こしている場合には、入院治療が必要です。
病態によっては、ステロイドの投与がおこなわれます。
【参考情報】『東京都感染症マニュアル マイコプラズマ肺炎』東京都感染症情報センター
https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/assets/survey/kobetsu/j2023.pdf
4. マイコプラズマ肺炎の予防

現時点でマイコプラズマには、有効なワクチンがありません。
一度感染して免疫を得ても、長くは続かないので、再度感染する場合もあります。
マイコプラズマは、「飛沫感染」と「接触感染」で感染が広がります。
そのため、流行時期にはマスクの着用やうがい、手洗い、消毒などをしっかりおこないましょう。
基本的な感染対策が、一番の予防方法です。
【参考文献】”Mycoplasma pneumoniae Infections” by Centers for Disease Control and Prevention
https://www.cdc.gov/pneumonia/atypical/mycoplasma/about/prevention.html
5.おわりに
マイコプラズマ肺炎は、しつこく長引く咳が特徴です。
軽症で済む場合もありますが、重症化するとさまざまな合併症を起こす可能性がある感染症です。
抗生物質を使用して治療しますが、重症化すると入院治療が必要でしょう。
予防に有効なワクチンはないため、手洗いやうがい、マスクの着用などの基本的な感染対策が重要です。
しつこい咳が長引いている場合、一度呼吸器内科を受診してみましょう。



