胸膜炎とは

胸膜炎(肋膜炎:ろくまくえん)は感染症、がん、膠原病、肺塞栓症などが原因で肺を包んでいる胸膜に炎症が起こる病気です。
胸膜の炎症により胸水(きょうすい:肺と肺を囲む壁の間に溜まる液体)が過剰に貯留すると肺を圧迫し、呼吸困難や胸痛などの症状を引き起こします。
重症の場合は大量の胸水に心臓が圧迫されて血圧低下や頻脈などの症状が現れることもあります。
1.原因
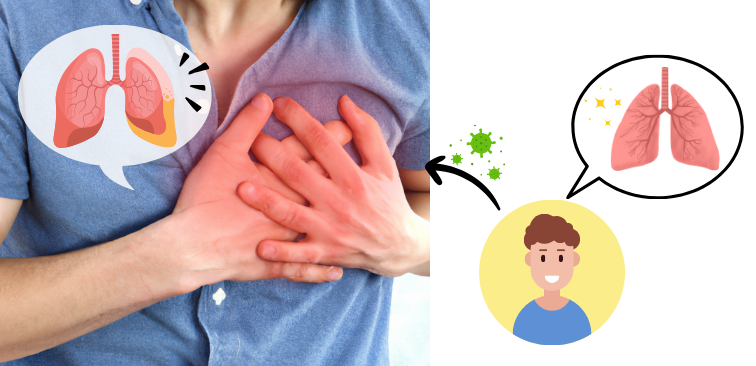
肺表面を覆う「臓側胸膜(ぞうそくきょうまく)」と、胸壁を覆う「壁側胸膜(へきそくきょうまく)」の間の空間を胸膜腔(胸腔)といいます。
胸腔内には正常でもごく少量の胸水が存在し、肺がスムーズに膨らんだり縮んだりするための潤滑油の働きを担っています。
胸水は壁側胸膜の毛細血管で産生され、通常は臓側胸膜から吸収されています。
しかし、ここに何らかの異常が起こると胸水が漏れ出て貯留してしまいます。
胸水が漏れ出る原因には次のようなものがあります。
1-1.滲出性胸水(しんしゅつせいきょうすい)
.jpg)
炎症により毛細血管の透過性が亢進し、隙間ができることで胸水が滲出します。
具体的な原因には次のようなものがあります。
・細菌、肺炎、結核などの感染症
◆「肺炎」について詳しく>>
・肺がん、転移性腫瘍(乳がんなど)、悪性リンパ腫、悪性胸膜中皮腫などの悪性腫瘍
◆「肺がん」について詳しく>>
・関節リウマチ、全身性エリテマトーデス(SLE)、好酸球性多発性血管炎性肉芽腫症、家族性地中海熱などの膠原病・血管炎
・肺塞栓症(エコノミークラス症候群)
・アスベスト(石綿)ばく露
・薬剤によるもの
日本人では特に結核性胸膜炎とがん性胸膜炎が多く、全体の60%~70%を占めています。
男女比は同じ程度ですが、関節リウマチや乳がんが原因の悪性胸水は女性、アスベストを扱う職歴に影響する悪性胸膜中皮腫による胸水は男性に多いです。
結核性胸膜炎は、肺結核に伴うものと、単独で発症するものがあります。
単独で発症する結核性胸膜炎の場合、肺結核の症状がなくても、体の中に潜んでいた結核(潜在結核)が再燃することが原因となります。
薬剤性の胸膜炎では、抗不整脈薬のアミオダロン、抗がん剤のブレオマイシン、抗てんかん薬のパルプロ酸ナトリウムなどが原因として挙げられます。
1-2.漏出性胸水(ろうしゅつせいきょうすい)
.jpg)
漏出性胸水の原因としては次の2つのようなものがあります。
①毛細血管の静水圧亢進:心不全などが原因で胸水を押し出す力が強くなり、胸水が漏出します。
②毛細血管の膠質浸透圧低下:毛細血管の中にはアルブミンという水を保持する物質があります。
肝硬変やネフローゼ症候群などでアルブミンが減少すると胸水を引き込む力が弱くなり、胸水が漏出します。
【参考情報】日本心臓財団『心不全 Question4』
https://www.jhf.or.jp/pro/hint/c4/hint004.html
2.症状
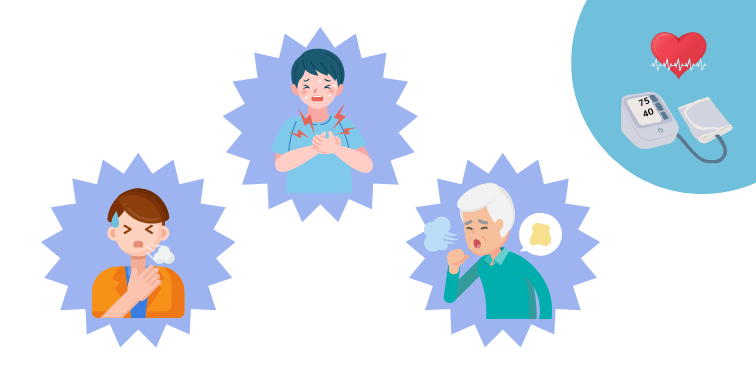
胸膜炎では、胸水で肺が圧迫されることによる息切れや呼吸困難、胸膜への刺激による空咳や痰、ピリピリとした鋭い胸痛、胸部の違和感や圧迫感などの症状が現れます。
胸痛は、特に深呼吸や咳をした時に強くなり、人によっては背中に痛みを感じることもあります。
強い痛みが生じるのは、壁側胸膜に「知覚神経」という痛みを伝える神経が豊富に通っているためです。
また、感染症による胸膜炎では、胸腔内に化膿性胸水が貯留し膿胸(のうきょう)と呼ばれる状態になる場合もあります。
呼吸器症状の他にも、発熱など胸膜炎の原因疾患による症状も見られます。
がん性胸膜炎ではがん症状の悪化も伴います。
重症化して胸水が大量に貯まると心臓が圧迫されて頻脈、血圧低下など命に関わる重篤な状態になることもあります。
【参考情報】日本呼吸器学会『胸膜炎』
https://www.jrs.or.jp/citizen/disease/g/g-01.html
【参考文献】”Pleurisy” by Mayo Clinic
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/pleurisy/symptoms-causes/syc-20351863
3.検査

問診、聴診などから胸膜炎が疑われる時は次のような検査を行います。
3-1.血液検査

血液検査では、炎症により白血球(体内に侵入した細菌やウイルスなどの異物から守る免疫細胞)の増加などが認められます。
3-2.画像検査

胸部エックス線検査(レントゲン)やCT検査で胸水の貯留、胸膜炎やその原因疾患による石灰化、胸膜肥厚、肺炎や癌の所見があるかについて確認することができます。
胸部画像で胸水が両側に認められる場合は、心不全・腎不全などの漏出性胸水を示唆します。
一方、胸膜炎では片側性に胸水が偏ることが多く、X線所見は診断の手がかりとなります。
3-3.胸水検査

胸水検査とは、胸腔穿刺(きょうくうせんし)を行い胸水を採取する検査です。
座った状態で、局所麻酔をかけて行います。
採取した胸水の色や性状、成分(pH、蛋白、LDH、腫瘍マーカーなど)から胸膜炎の原因疾患を特定することができます。
治療方針を決定するためにも重要な検査です。
がんや細菌感染が原因の滲出性胸水では黄褐色や血性、心不全やネフローゼ症候群が原因の漏出性胸水では透明や淡黄色の胸水がみられます
3-4.胸膜生検
胸水検査で原因が特定できない場合は胸膜生検を行います。
胸膜生検とは皮膚を部分的に切開して胸腔鏡を挿入し、病変部の組織を取って顕微鏡で詳しく調べる検査です。
4.治療

胸膜炎の治療には次のようなものがあります。
4-1.薬剤投与
細菌感染症が原因の場合は抗菌薬(抗生物質)、結核が原因の場合は抗結核薬、がん性胸膜炎の場合は抗がん剤など、基本的には胸膜炎の原因疾患に有効な薬を投与します。
細菌性胸膜炎では、症状改善後も解熱後5~7日程度は抗菌薬を継続し、耐性リスクや再発を防ぐのが一般的です。
4-2.胸腔ドレナージ
胸腔ドレナージとは胸膜の間に管を挿入し胸水を排出する処置です。
貯留している胸水の量が多い時は、息苦しさを緩和するために胸腔ドレナージを行います。
また、感染性胸水で膿胸の状態になっている時も、膿性胸水を排出するために胸腔ドレナージを行います。
4-3.胸膜癒着術
胸膜癒着術とは胸水が貯まる空間を閉じて胸水が溜まらないようにする治療です。
がん性胸膜炎によって胸水貯留を繰り返している場合などに行われます。
【参考情報】臨床外科看護各論/医学書院
https://www.igaku-shoin.co.jp/book/detail/81406
5.おわりに
胸膜炎は肺炎や結核などの感染症やがんなど、様々な原因で起こる病気です。
感染性の胸膜炎では、免疫を低下させる原因である喫煙、大量飲酒、糖尿病などが危険因子となります。
生活習慣を見直し、感染症に注意して生活することが予防に繋がります。
また、がんやCOPD(慢性閉塞性肺疾患)などの持病がある場合、適切な治療を受けることが大切です。
胸痛や息切れなど、気になる症状がある場合は早めに呼吸器内科を受診してください。
なお、突然、胸に強い・激しい痛みを感じ、息苦しくなって冷や汗が出たり、痰に血が混じったりといった症状が出た場合、それは肺血栓塞栓症、心筋梗塞、胸部大動脈解離などの命に関わる重大な病気の可能性があります。
このような症状を感じたら、決して自己判断せず、すぐに救急車を呼んで医療機関を受診しましょう。



