運動後に咳が止まらない…喘息の可能性と予防のポイント

「体育や部活の後、子どもが長く咳き込んでいる」と不安に思ったことはありませんか?
実はその咳、風邪や疲労と片付けずに注意が必要です。
運動誘発喘息や咳喘息といった疾患が隠れている可能性があります。
本記事では、咳の見分け方から家庭での対応、予防策、受診タイミングまで、詳しく解説します。
1. 運動後の咳、見過ごさないで!

運動後に子どもが咳き込む様子を見て、「よくあること」「疲れているだけ」と思い込んでいませんか?
実はその咳、体力の問題ではなく、気道の異常が関係している可能性があります。
特に、毎回同じようなタイミングで咳が出る、悪化してきている、といった場合は注意が必要です。
ここでは、子どもの咳にどんな意味があるのか、まずは基本的な見方を解説します。
【参考文献】”Asthma in Children” by MedlinePlus
https://medlineplus.gov/asthmainchildren.html
1-1. 「ただ疲れている」だけとは限らない
体育や部活のあとに「ゴホゴホ」「コンコン」と咳き込む様子を見ても、「きっと運動して疲れただけ」と思っていませんか?
確かに、激しい運動後は一時的に呼吸が荒くなることもありますが、咳が毎回出る、長引く、悪化していく――こうした傾向がある場合は、体力や持久力の問題ではなく、気道の過敏性や炎症が関係している可能性があります。
特に、寒い日の屋外運動や乾燥した体育館など、空気が冷たく乾燥している環境では、気道が刺激を受けやすくなります。
その結果、運動のたびに咳や息切れが出るようになり、症状が悪化することもあります。
運動後の咳を「疲れ」や「一時的なもの」と軽視してしまうと、症状を放置してしまい、運動誘発喘息や咳喘息の発見が遅れる可能性があります。
実際、気道が炎症を起こしているにもかかわらず、本人も周囲も「気合いで乗り切れる」と思い込み、医療機関を受診するタイミングを逃すケースも少なくありません。
まずは「いつも運動後に咳き込むのはなぜか?」という視点で、子どもの体に起こっていることを見つめ直すことが大切です。
子どもが「運動後だけ咳が出る」と話してきたら、単なる疲れではなく、何らかの気道トラブルのサインとして受け止めるようにしましょう。
1-2. 咳の出るタイミングが示すもの
咳が出るタイミングは、風邪なのか、運動によるものなのか、あるいは喘息のような慢性疾患の可能性があるのかを見極める重要なヒントになります。
たとえば、運動中または運動直後に毎回咳が出るようであれば、「運動誘発喘息(EIB/EIA)」が疑われます。
一方、明け方や就寝中に咳が目立つ場合は、「咳喘息」や「気道過敏」が背景にある可能性もあります。
このように、咳が「いつ・どんな場面で出るか」を意識して観察することが、疾患に早く気づく第一歩になります。
※具体的な記録方法については「3-1」で詳しく紹介します。
【参考情報】『小児ぜん息基礎知識「運動時のポイント」』独立行政法人環境再生保全機構
https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/basic/kodomonozensoku/undo.html
【参考情報】『運動誘発性喘息』メイヨークリニック
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/exercise-induced-asthma/symptoms-causes/syc-20372300
2. 主な疾患:運動誘発喘息&咳喘息

運動後の咳を引き起こす主な原因として、「運動誘発喘息」と「咳喘息」という2つの呼吸器疾患が知られています。
どちらも子どもに多く見られる病気ですが、特徴や対応が異なるため、正しく理解しておくことが大切です。
2-1.「運動誘発喘息」
「運動誘発喘息(EIB/EIA)」は、運動をきっかけに一時的に気道が狭くなることで、咳や息切れ、ゼーゼーという喘鳴(ぜんめい)などの症状が出る状態です。
運動後5〜15分で咳が出始め、30〜60分ほどで自然に治まることが多く、特に冬の冷たい空気や乾燥、強度の高い運動時に起こりやすい傾向があります。
喘息において運動時咳嗽発作が起こる場合の多くは、通常喘息のコントロールが悪い場合に起こることが多いです。
純粋な運動誘発喘息は、そこまで頻度が高い病型ではないので、運動をあきらめるのではなくまず適切に診断し治療することが重要です。
また、喘息の診断を受けていない子どもでも、こうした症状が現れることがあり、見逃されやすいため注意が必要です。
◆ 喘息の方でもスポーツはできる?おすすめのスポーツと注意点について解説>>
2-2.「咳喘息」
「咳喘息」は、ゼーゼーという音や呼吸困難がなく、乾いた咳だけが長く続くタイプの喘息です。
咳が2週間以上続いたり、夜間や明け方に悪化するのが特徴で、風邪と区別がつきにくいこともあります。
こちらは特に、発症初期では本人も「ただの風邪が長引いている」と思いがちで、適切な治療が遅れるケースも少なくありません。
どちらの疾患も、気道が過敏になっているという点では共通しています。
症状の出方やきっかけが異なるだけで、慢性化すると生活の質を大きく損なう可能性がある点では同じです。
そのため、咳が長引く、または運動のたびに決まって咳が出るといった傾向がある場合は、早めの受診と適切な管理が重要です。
【参考情報】『第3章-1 気管支喘息 小児喘息PDF』 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/kenkou/ryumachi/dl/jouhou01-06.pdf
【参考情報】『第3章-2 気管支喘息 成人喘息PDF』 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/kenkou/ryumachi/dl/jouhou01-07.pdf
3. 自宅でできる観察とチェック
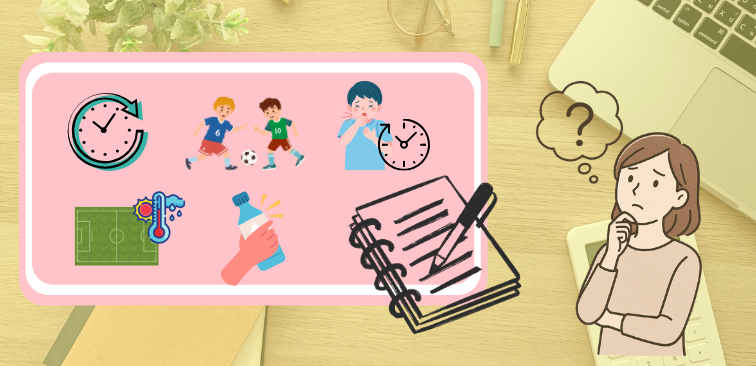
病院を受診する前に、家庭でできる観察や記録があることをご存じですか?
子どもの咳や呼吸の様子を日々チェックすることで、見逃されがちな症状にいち早く気づくことができます。
特に、咳が出るタイミングや運動の内容を記録しておくと、受診時にとても役立つ情報になります。
ここでは、家庭でできるチェック方法と、どんな点に注目すればよいかをご紹介します。
【参考文献】”Assisting Students with Exercise-induced Asthma” by Montana DPHHS
https://dphhs.mt.gov/assets/publichealth/Asthma/Online%20Trainings/AssistingStudentswEIAsthma.pdf
3-1. 日誌で「いつ・どこで・どんな運動で咳が出るか」を記録
咳のタイミングを観察するだけでなく、日々の記録として残していくことは、医師への相談や症状の早期発見に非常に役立ちます。
特に以下のような点を整理して書き留めておくのがおすすめです。
◎記録しておきたい項目の例:
【日付・時間帯】:咳が出たのは午前?午後?夜?
【運動の種類】:体育・部活・遊びなど(例:リレー、縄跳び、サッカー練習)
【咳の出始め】:運動中?運動後何分で?
【咳の続いた時間】:何分程度続いたか
【環境要因】:屋外 or 屋内、気温、湿度、マスクの有無、大気の汚れ、花粉など
【その他】:水分補給の有無、本人の自覚症状(苦しさ、胸のつかえ感など)
このような記録を続けていくと、「毎週水曜のサッカー練習後に決まって咳が出ている」「寒い日は症状が強い」といったパターンが見えてきます。
これは受診時に非常に有効な情報となり、正しい診断と治療につながります。
また、保護者だけでなく、年齢によっては子ども自身にも記録の手伝いをしてもらうと、自己管理意識を高めるきっかけにもなります。
【参考情報】『小児喘息の知識』 アレルギーポータル
https://allergyportal.jp/knowledge/childhood-asthma/
3-2. 呼吸音と息苦しさの観察
咳以外にも、子どもの呼吸の様子を観察することで、病気の兆候に気づくことができます。
特に「音」と「呼吸のしづらさ」は、見逃してはいけないポイントです。
◎こんな呼吸音が聞こえたら要注意
以下のような音が、呼吸時に聞こえていないか注意してみましょう
・ヒューヒュー(笛のような音)
・ゼーゼー(濁ったうなりのような音)
・スースーと浅い息づかい
これらは気道が狭くなっているサインで、喘息や運動誘発喘息の典型的な症状です。
胸や背中に耳を当てると聞こえることもあります。
※ただし、咳喘息の場合はこうした音が出ないこともあるため、「呼吸音がない=問題ない」とは限りません。
◎息苦しさをどう見分ける?
子どもは小さければ小さいほど「苦しい」と言葉でうまく伝えられません。
以下のようなサインをチェックしましょう。
・胸や肩を上下に大きく動かして呼吸している(努力呼吸)
・話す途中で言葉が続かない・すぐに「ハァハァ」と息を継ぐ
・顔色が悪く、口元が青白い(チアノーゼ)
・無意識にうずくまる、運動を途中でやめる、泣く
・いつもより疲れている・元気がない
こうした様子が見られたら、単なる運動疲れではなく、気道に負担がかかっている状態かもしれません。
◎本人に聞いてみるのも大切
小学生以上であれば、「運動のあと、息がしづらい?」「胸が苦しくなることある?」といった質問をしてみてください。
本人の感覚が、咳以外の見えにくい症状を発見する手がかりになります。
4. 日常でできる咳予防対策

運動後の咳を防ぐには、特別な治療だけでなく、家庭でのちょっとした工夫が効果的です。
家庭でできる予防策を整理しました。
① ウォーミングアップとクールダウンを習慣に
運動前に軽く身体を動かすことで、気道が急激な刺激を受けにくくなります。
運動後も急に止まらず、呼吸を落ち着かせる時間をつくることが大切です。
② 環境に応じた工夫を
寒い季節や乾燥した日には、マスクやネックウォーマーで口元を保護。
大気汚染や花粉が多い日は屋内運動に切り替えるのもひとつの方法です。
③ こまめな水分補給を心がける
喉や気道の乾燥は咳の引き金になります。
特に冬は「運動前・中・後」に水分をしっかりとる習慣をつけましょう。
④ 子どもに合った運動選びを
湿度が高く負担の少ない水泳や、ゆるやかなウォーキング・ヨガなどは咳を起こしにくいとされています。
無理せず、体調に合わせて運動内容を調整しましょう。
⑤ 周囲と共有して安心できる環境を
「咳が出たら無理せず休んでよい」「水分補給を忘れずに」といったルールを、学校や部活動でも共有できると安心です。
日々のちょっとした工夫で、咳を予防しながら運動を楽しむことは十分可能です。
ご家庭でも取り入れられる習慣から、少しずつ始めてみてください。
【参考文献】”Exercising and asthma at school” by MedlinePlus
https://medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000037.htm
5. こんなときは医療機関に相談を

子どもによくある咳ですが、「長引いている」「運動のたびに繰り返す」「夜間に悪化する」といった場合は、風邪ではなく、気道の病気が隠れている可能性があります。
とくに咳が2週間以上続いているときや、夜間・明け方に咳が強まって眠れない場合、咳喘息などの慢性的な呼吸器疾患が考えられます。
熱や鼻水などの風邪症状がないのに咳だけが目立つときも、注意が必要です。
こうした症状は、「咳は風邪のあとによくあるもの」と見過ごされがちですが、改善しないまま放置してしまうと、気道の炎症が慢性化し、治療が長引く原因にもなります。
市販薬であまり効果が見られない場合は、自己判断に頼らず、早めに専門医の診察を受けましょう。
また、「体育や部活のたびに咳が出る」「運動中に息苦しそうにしている」「最近、運動を嫌がるようになった」といった場合は、運動誘発喘息の可能性があります。
毎回同じような状況で咳が出る、以前より症状が強くなってきているという変化が見られるときには、悪化を防ぐためにも早めの受診が大切です。
必要に応じて、呼吸機能検査や吸入薬などの対応が行われます。
「病院に行くほどではないかも」「もう少し様子を見てから」と迷うときもあるかもしれませんが、不安があるときは我慢せず、まずは相談してください。
咳の種類や出方によって、受診のタイミングを一緒に考えていくことができます。
【参考文献】”Management of Asthma in Children and Adults” by GovInfo
https://www.govinfo.gov/content/pkg/GOVPUB-VA-PURL-gpo115025/pdf/GOVPUB-VA-PURL-gpo115025.pdf
6. 学校・家庭・医療機関が連携するためにできること
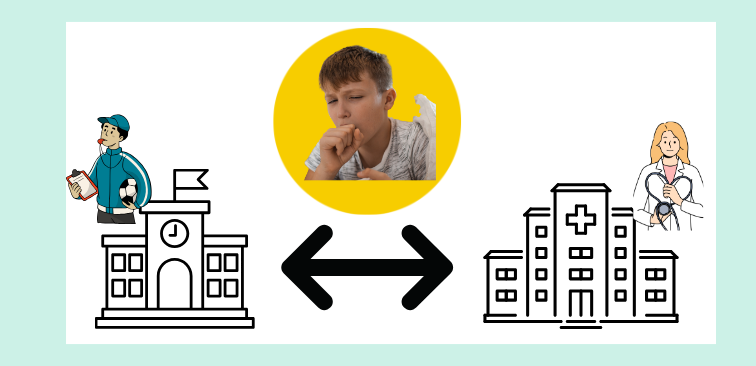
運動後の咳や喘息症状がある子どもにとって、家庭だけでなく学校や医療機関と連携したサポート体制を整えることは、とても大切です。
特に学校では、体育の授業や部活動で日常的に運動する機会があるため、教員やコーチが子どもの体調の特徴を理解しておくことで、無理をさせず、安全に活動させることができます。
そのために有効なのが、「学校生活管理指導表」の活用です。
これは、医師が記載し、保護者・学校と情報共有することで、子ども一人ひとりに合った配慮や対応を可能にする書式です。
喘息などの慢性疾患を持つ子どもが、体調や症状に応じて体育の参加内容を調整したり、必要な吸入薬の使用ができるようにするための支援ツールです。
また、年齢が上がるにつれて、子ども自身が「今日はちょっと苦しいかも」「水を飲んで少し休もう」といった自己管理の力を育てることも大切です。
周囲の大人がそれを認め、サポートする環境があれば、子どもは安心して自分の体調と向き合えるようになります。
咳や呼吸に不安のある子どもが、必要以上に運動を我慢したり、理解されずにつらい思いをすることがないよう、家庭・学校・医療の三者で情報を共有し、支える体制をつくることが、健康と成長の両立につながります。
【参考情報】『アレルギー対応ガイド(PDF)』 東京都保健医療局
https://www.hokeniryo1.metro.tokyo.lg.jp/allergy/pdf/pri16.pdf
【参考文献】”Asthma and Physical Activity in the School: Making a Difference” by NHLBI/National Asthma Education and Prevention Program
https://www.nhlbi.nih.gov/sites/default/files/publications/12-3651.pdf
7.おわりに
子どもが運動後に咳き込むのは、単なる疲れや風邪とは限りません。
運動誘発喘息や咳喘息など、気道に関わる疾患のサインであることもあります。
症状を「よくあること」と見過ごさず、「いつ・どんなときに・どれくらい咳が出るのか」を家庭で観察し、必要に応じて医療機関に相談することが大切です。
また、子どもが安心して体を動かし、学校生活や部活動に前向きに取り組むためには、家庭・学校・医療の連携が欠かせません。
ちょっとした気づきや記録、周囲の理解が、子どもを支える大きな力になります。
咳が気になるときは、早めに受診して原因を確認し、無理なく運動を続けられる方法を一緒に考えていきましょう。
当院でも、気になる症状や不安なことがあればお気軽にご相談ください。



