アスリート喘息と呼ばれる運動誘発性喘息とは

「運動が好きなのに、息切れが止まらない」「試合の途中で胸が苦しくなる」……そのような思いを抱えている方はいませんか?
運動誘発性喘息は、からだを動かした直後や数時間後に喘息の症状が現れるもので、アスリートの方やスポーツを楽しむ方にとって大きな壁となることがあります。
しかし、運動誘発性喘息は決して「運動をあきらめなければならない病気」ではありません。
適切な管理と予防により運動を楽しむことができます。
この記事では、運動誘発性喘息の原因や症状、検査方法、治療法、日常生活で取り入れやすい予防策をご説明いたします。
1. 運動誘発性喘息について

運動誘発性喘息は、運動中や運動後に喘息の症状が現れる状態です。
通常の喘息と同様に、気道が狭くなることで息苦しさや咳、喘鳴(ぜーぜーする音)などの症状が生じます。
運動誘発性喘息の症状が現れるタイミングには、大きく分けて2種類あります。
・即時型反応
運動を始めてすぐに、あるいは運動中に症状が現れます。多くの方がこのタイプに該当します。
・遅延型反応
運動を終えてから6〜12時間後に症状が現れます。この場合、運動が原因だと気づきにくいことがあります。
ただし、運動誘発性喘息があるからといって、運動を完全に避ける必要はありません。
むしろ、適度な運動は体力をつけたり、全身の健康を維持したりするのに重要です。
誤解しやすいのは運動時の喘息発作のほとんどは、喘息のコントロールが不良な状態の結果として起こっている場合が多いということです。
運動自体が喘息に悪影響をする純粋な運動誘発性喘息は小児の一部でしかみられないといわれております。
運動時の咳嗽、呼吸困難、喘鳴は喘息治療を適切に行うことでほとんどがコントロールできます。
むやみに運動を制限するのではなく喘息治療をきちんとすることが大事です。
医師と相談しながら、ご自分に合った運動の種類や強度を見つけ、継続的に取り組むことで、運動誘発性喘息の症状をコントロールしながら健康的な生活を送ることができます。
【参考文献】”Exercise-induced asthma” by Mayo Clinic
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/exercise-induced-asthma/symptoms-causes/syc-20372300
2. 運動誘発性喘息の原因とは
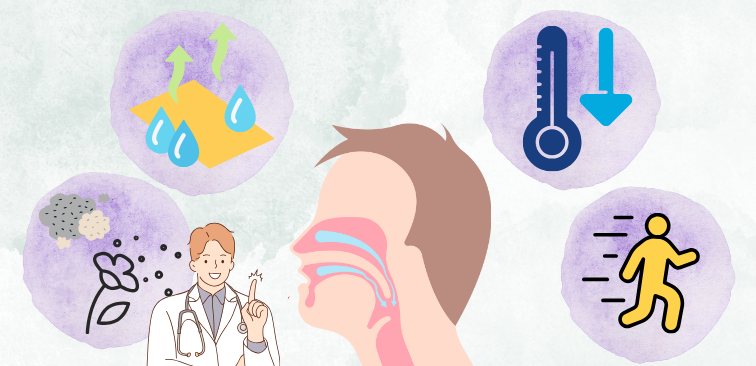
運動誘発性喘息の主な原因は、運動中の呼吸の変化にあります。
具体的には以下のような要因が関係しています。
1. 気道の乾燥
運動中は呼吸が激しくなり、短時間に多くの空気を吸い込みます。
この際、気道内の水分が奪われ、乾燥が起こります。
乾燥した気道は刺激に敏感になり、喘息症状を引き起こしやすくなります。
2. 気道の冷却
激しい運動中は口での呼吸が増えます。
そのため、鼻で温められていない冷たい空気を直接肺に取り込むことになります。
これにより気道が冷やされ、気道粘膜の血管が収縮と拡張を繰り返すことで炎症が起こりやすくなります。
3. 環境要因
屋外での運動の場合、グラウンドに舞うホコリや花粉、大気汚染物質などのアレルギー物質を吸い込むことで、気道が刺激され症状が引き起こされることがあります。
4. 運動の種類と強度
長時間にわたる持続的な運動や、寒い環境での運動は特に症状が出やすいとされています。
5. 個人の体質
もともと気道過敏性が高い方や、アレルギー体質の方は運動誘発性喘息を起こしやすい傾向です。
【参考文献】”Exercise-Induced Asthma” by Cleveland Clinic
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/4174-exercise-induced-asthma
3. おすすめのスポーツは?

すべての運動が同じように喘息の症状を起こしやすいわけではありません。
発作が出やすい運動と出にくい運動があります。
3-1. 運動誘発性喘息の症状が出やすい運動
運動誘発性喘息の症状が出やすい運動には、主に以下のようなものがあります。
1. 長時間走るスポーツ
マラソン、サッカー、バスケットボールなど、長時間にわたって激しい運動を続けるスポーツは、症状が出やすい傾向にあります。
これは、長時間の運動により気道が乾燥し、冷却されやすいためです。
2. ウインタースポーツ
スキー、スケート、アイスホッケーなどの冬季スポーツも注意が必要です。
気温が低い環境で行うスポーツは、冷たく乾燥した空気を大量に吸い込むことになり、気道への刺激が強くなります。
3. 屋外での激しい運動
テニスやホッケーなど、屋外で行う激しい運動も症状が出やすいです。
これは、運動による影響に加えて、花粉やほこりなどの環境要因も関係しています。
とくに寒い日のランニングやスキー、スケートはとくに注意が必要です。
運動を行う際は、必ず事前に医師と相談し、適切な予防策を講じた上で実施するか、場合によっては控えることを検討しましょう。
3-2. 運動誘発性喘息の症状が出にくい運動
一方で、運動誘発性喘息の方でも比較的安全に楽しめる運動もあります。
1. 水泳
水泳は運動誘発性喘息の方に最もおすすめのスポーツのひとつです。
プールの水温が調整され湿度も高いので、気道が潤って刺激を受けにくくなります。
また、水中ではからだが水平になるため、呼吸がしやすくなるという利点もあります。
2. ウォーキング
ウォーキングはご自分のペースで無理なく行える運動です。
激しい運動と比べて呼吸への負担が少なく、屋内外を問わず実施できます。
3. ヨガやピラティス
ヨガやピラティスは呼吸を意識しながらゆっくりとからだを動かす運動です。
呼吸法を学ぶことで、日常生活でも呼吸をコントロールする力が身につきます。
4. 軽度の筋力トレーニング
適度な強度で行う筋力トレーニングは、全身の筋力を向上させ、日常生活での呼吸の効率を高めることができます。
5. ゴルフ
ゴルフは比較的ゆっくりとしたペースで行え、途中で休憩を取ることができるスポーツです。
屋外で行いますが、激しい運動ではないため、多くの方が楽しむことができます。
これらの運動は比較的安全ですが、個人差があるため必ず医師に相談したうえで、ご自分に合った運動を選択することが大切です。
また、どのような運動でも準備運動を十分に行い、徐々に強度を上げていくことが大切です。
【参考文献】”Exercise-Induced Bronchoconstriction (Asthma)” by Asthma and Allergy Foundation of America
https://aafa.org/asthma/asthma-triggers-causes/exercise-induced-asthma/
4. 運動誘発性喘息の検査方法

ここからは、運動誘発性喘息の診断や状態の把握のための主な検査方法についてご説明します。
4-1. 画像検査
画像検査は、肺や気道の状態を視覚的に確認するために行われます。主に以下のような検査が使われます。
1. 胸部X線検査(レントゲン検査)
胸部のX線写真を撮影し、肺や気管支の状態を確認します。
喘息そのものを直接診断することは難しいですが、ほかの呼吸器疾患の有無を確認するのに役立ちます。
2. CT検査(コンピュータ断層撮影)
X線検査よりも詳細な画像が得られ、気道の狭窄や粘液の貯留などを確認することができます。
喘息の重症度評価や、ほかの疾患との鑑別に用いられます。
これらの画像検査は、運動誘発性喘息の直接的な診断というよりは、ほかの呼吸器疾患の除外や、喘息による気道の変化を確認するために行われます。
4-2. 血液検査
血液検査では、喘息に関連するさまざまなからだの状態を調べることができます。
運動誘発性喘息そのものを診断するというよりは、喘息の背景にあるアレルギー傾向や炎症の程度を評価するのに役立ちます。
1. 好酸球数
喘息では好酸球という白血球の一種が増加することがあります。好酸球数の増加は、アレルギー反応や気道の炎症を表します。
2. 総IgE値
IgEはアレルギー反応に関与する抗体です。総IgE値の上昇は、アレルギー性の喘息の可能性を表します。
3. 特異的IgE抗体
特定のアレルゲン(花粉、ハウスダストなど)に対するIgE抗体を測定します。これにより、どのようなアレルゲンが喘息の引き金になっているかを特定できます。
4. 炎症マーカー
CRPやフェリチンなどの炎症マーカーを測定することで、体内の炎症状態を評価します。
4-3. 肺機能検査
肺機能検査は、運動誘発性喘息の診断において最も重要な検査のひとつです。主に以下の検査が行われます。
1. スパイロメトリー
息を思い切り吐き出したときの空気の量や速さを測定します。
FEV1(1秒量)という指標が重要で、低下していると気道狭窄が起こっていると考えられます。
2. ピークフローメーター
最大呼気流速を測定する簡易な検査です。家庭でご自分で計測できるため、日々の喘息管理に役立てることができます。
3. 運動負荷試験
トレッドミル(ランニングマシン)やエルゴメーター(運動負荷をかけて体力測定やトレーニング、機能向上を促す器具)を使って一定の運動をした後、肺機能の変化を測定します。運動誘発性喘息の診断にとくに有用です。
4. メサコリン負荷試験
気道過敏性を評価する検査です。メサコリンという薬剤を吸入し、気道の反応性を調べます。
これらの検査を組み合わせることで、運動誘発性喘息の診断や重症度の評価を行います。
ただし、検査結果だけでなく、症状や病歴なども含めての総合的な診断が必要です。
運動誘発性喘息の疑いがある方が、これらの検査を受けることで、より正確な診断ができ、適切な治療方針を決定することができます。
検査の内容や必要性については、担当の医師とよく相談しましょう。
【参考文献】”Asthma and Exercise” by American Academy of Allergy, Asthma & Immunology
https://www.aaaai.org/tools-for-the-public/conditions-library/asthma/asthma-and-exercise
5. 運動誘発性喘息にはどんな薬を使うのか
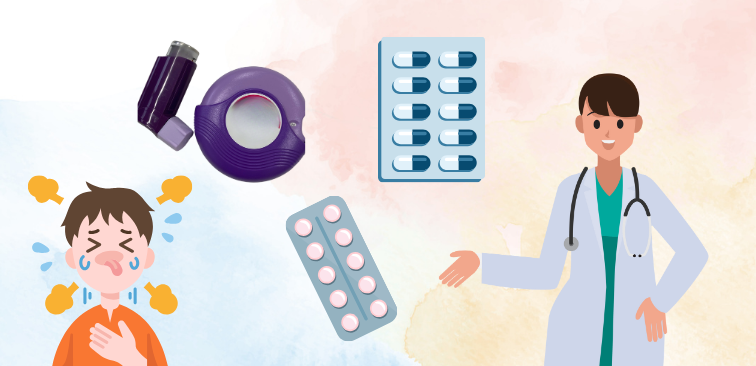
運動誘発性喘息の治療には、主に以下のような薬が使用されます。これらは発作の予防や症状の緩和に効果があり、適切に服用することで運動を安全に楽しむことができます。
これらの薬は、症状の程度や個人の状態に応じて、単独または組み合わせて使用されます。どの薬をどのように使用するかは、医師による慎重な判断が必要です。
1. クロモグリク酸ナトリウム
クロモグリク酸ナトリウムは、肥満細胞からのヒスタミンという化学伝達物質の放出を抑制する薬です。運動の15〜20分前に吸入することで、運動誘発性喘息の予防効果があります。
副作用が少なく、長期使用が可能なため、お子さまから大人の方まで幅広く使用されています。
2. 短時間作用性吸入β2刺激薬
サルブタモールやプロカテロールなどの短時間作用性吸入β2刺激薬は、気管支を拡張させる即効性のある薬です。
運動の15〜30分前に吸入することで、運動中の喘息症状を予防できます。また、症状が現れた際の緊急治療薬としても使用されます。
3. 長時間作用性吸入β2刺激薬
サルメテロールやホルモテロールなどの長時間作用性吸入β2刺激薬は、12時間程度の持続的な気管支拡張効果があります。
定期的に使用することで、1日を通して症状をコントロールできます。
4. 吸入ステロイド薬
ブデソニドやフルチカゾンなどの吸入ステロイド薬は、気道の炎症を抑える効果があります。
長期的に使用することで、気道の過敏性を低下させ、運動誘発性喘息の症状を軽減します。
単独で使用されることもありますが、長時間作用性吸入β2刺激薬と併用されることも多いです。
5. ロイコトリエン受容体拮抗薬
モンテルカストやプランルカストなどのロイコトリエン受容体拮抗薬は、気道炎症に関与するロイコトリエンの作用を抑制します。
経口薬として使用され、長期的な喘息コントロールに役立ちます。運動誘発性喘息の予防にも効果があるとされています。
6. 抗IgE抗体薬
オマリズマブなどの抗IgE抗体薬は、重症のアレルギー性喘息の方に使用されることがあります。
IgEの作用を抑制することで、アレルギー反応を軽減し、喘息症状の改善につながります。
運動誘発性喘息の薬物治療で重要なのは、予防的な使用です。
多くの場合、運動前に薬を使用することで症状を予防できます。
ただし、薬の使用方法や頻度については、必ず医師の指示に従ってください。
また、これらの薬には副作用の可能性もあります。
例えば、β2刺激薬の過度の使用は、動悸や手の震えなどを引き起こします。
ステロイド薬の長期使用では、骨密度の低下や成長への影響などが懸念されることがあります。
そのため、定期的に医師の診察を受け、薬の効果や副作用について相談することが大切です。
自己判断で薬の使用を中止したり、用量を変更したりすることは避けましょう。
適切な薬物治療と生活の管理を組み合わせることで、運動誘発性喘息の症状をコントロールしながら、活動的な生活を送ることが可能です。
【参照文献】環境再生保全機構『さまざまなぜん息 運動誘発ぜん息』
https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/basic/adult/knowledge/exercise.html
6. 運動誘発性喘息の予防

運動誘発性喘息の症状を予防するためには、薬物治療だけでなく、日常生活での工夫も大切です。
ここからは、運動時の具体的な予防策についてご説明しましょう。
6-1. 準備運動をする
適切な準備運動は、運動誘発性喘息の予防に欠かせません。
準備運動により、からだを徐々に運動状態に慣らしていくことができます。
これにより、急激な呼吸の変化を避け、気道への刺激を軽減することができます。
効果的な準備運動の方法
ウォーミングアップは10〜15分程度行いましょう。
最初は軽いジョギングやストレッチなど、低強度の運動から始めます。
徐々に運動強度を上げていきます。
本格的な運動の直前には、短時間の高強度運動(30秒程度)を行い、その後2〜4分休憩するという方法も効果的です。
これは「レフラクトリー期」と呼ばれる、運動誘発性喘息が起こりにくい状態を作り出すのに役立ちます。
6-2. 適宜休憩、水分をとる
継続的な激しい運動は気道への負担を増加させます。適度な休憩を取ることで、呼吸を整え、気道への負担を軽減することができます。
効果的な休憩の取り方
運動の強度や体力に応じて、10〜15分ごとに短い休憩を取りましょう。
休憩中は深呼吸を行い、呼吸を整えます。
症状が現れそうな場合は、すぐに運動を中断し、十分な休憩を取りましょう。
また、適切な水分補給は、気道の乾燥を防ぎ、粘液の粘度を下げる効果があります。
これにより、気道の刺激を軽減し、喘息症状の予防につながります。
効果的な水分補給の方法
運動前、運動中、運動後にこまめに水分を摂取しましょう。
室温の水やスポーツドリンクが適しています。冷たすぎる飲み物は避けましょう。
運動強度や気温に応じて、15〜20分ごとに100〜200ml程度の水分を摂取するのが目安です。
適切な休憩と水分補給を心がけることで、運動中の喘息症状のリスクを軽減し、より安全に運動を楽しむことができます。
6-3. 湿度と気温が低い日は運動を避ける
湿度や気温が低い環境では、運動誘発性喘息が起きやすくなるため、とくに注意が必要です。
やむを得ず屋外で運動する場合は、運動の強度を下げ、時間を短くし、こまめに休憩を取りましょう。
暖かい服装を心がけ、マスクを活用することも効果的です。
マスクは空気を加湿・加温し、花粉やほこりの吸入を防ぐ効果があります。
一方で呼吸がしづらくなることもあるため、ご自分の状態に合わせて使用しましょう。
【参考文献】”Exercise-induced asthma” by Mayo Clinic
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/exercise-induced-asthma/diagnosis-treatment/drc-20372306
7. おわりに
運動誘発性喘息は、適切な管理と予防策で症状をコントロールしながら運動を楽しめます。
医師と相談しつつ治療を続け、症状が出にくいからだづくりをすることが重要です。
喘息が安定すれば運動の幅も広がります。
運動誘発性喘息は運動を諦める理由にはなりません。
むしろ適切な管理と予防で、より健康的な生活のきっかけになるかもしれません。
前向きな気持ちで喘息と向き合い、ご自分に合った運動習慣を見つけていきましょう。



