子どもの喘息と湿布薬の使用について

運動や転倒で子どもが手や足を痛めたときに「湿布を貼って様子を見よう」と思ったことはありませんか。
何気なく使ってしまうことが多い湿布薬ですが、実は、湿布薬に含まれる成分によっては喘息の発作を誘発するリスクがあることをご存知でしょうか。
今回は、子どもの喘息の基本と、湿布薬を使用する際に気をつけたいポイントをわかりやすく解説します。
1. 子どもの喘息とはどんな病気か
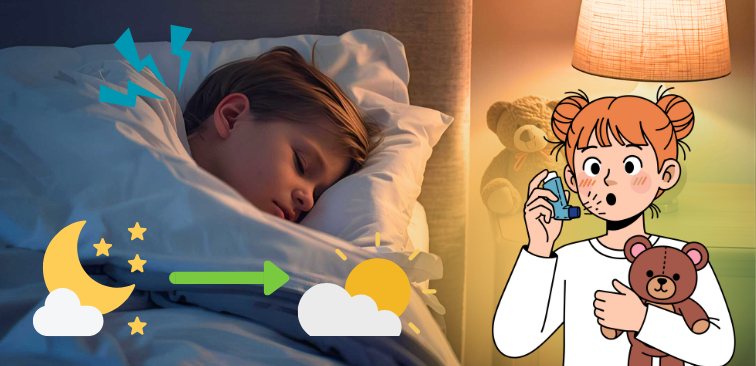
子どもの喘息は、気道(空気の通り道)に慢性的な炎症が起こり、咳やゼーゼー・ヒューヒューといった呼吸音(喘鳴・ぜんめい)、息苦しさなどの症状が繰り返し現れる病気です。
特に夜間から早朝にかけて症状が出やすく、風邪と区別がつきにくいこともあります。
子どもの気道は大人よりも細く柔らかいため、少しの刺激でも咳が出やすい傾向があります。
ハウスダストや花粉、ペットの毛などのアレルゲン(アレルギー原因物質)に加え、冷たい空気や強い匂いを吸ったとき、運動後などにも発作が誘発されることがあります。
小児喘息は成長に伴い症状が軽くなることもありますが、約3割は成人後も症状が続くといわれています。
そのため、子どものうちに適切な治療と管理を行うことが重要です。
◆「運動後に咳が止まらない…喘息の可能性と予防のポイント」>>
【参考情報】『ぜん息とは』環境再生保全機構
https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/
【参考情報】”About Asthma” by Centers for Disease Control and Prevention
https://www.cdc.gov/asthma/about/index.html
2. 湿布薬にはどんな成分が入っているの?

捻挫や筋肉痛のときに貼る「湿布薬」には、痛みや炎症を和らげるためのさまざまな成分が含まれています。
市販されている湿布薬はその成分や作用の違いから第一世代と第二世代に分類されることをご存知でしょうか。
お子さんが使用する際に知っておきたい湿布薬の主な成分と特徴を説明します。
2-1.第一世代の湿布薬の成分
第一世代の湿布薬は、いわゆる「昔ながらの湿布」です。
サリチル酸メチルやサリチル酸グリコールといった消炎鎮痛成分に、メントール(ハッカ油)やカンフル(クスノキから抽出される成分で防虫剤などにも使われる)、トウガラシエキスなどの冷感・温感成分を配合したものが該当します。
貼った部分の血行を促進したり、皮膚への適度な刺激によって神経の興奮を緩和したりすることで、痛みを感じにくくする仕組みです。
効果は穏やかですが、副作用も少なく、小児や妊婦、授乳中の方でも使いやすいとされています。
なお、サリチル酸メチルを主成分とする湿布薬は刺激臭がやや強い傾向がありますが、サリチル酸グリコール配合の湿布では独特の匂いが抑えられている製品もあります。
お子さんが嫌がらずに使用できるよう、低刺激性・低臭の湿布を選ぶ工夫もよいでしょう。
2-2.第二世代の湿布薬の成分
第二世代の湿布薬は、NSAIDs(エヌセイズ)と呼ばれる非ステロイド性抗炎症薬を主成分としたタイプです。
これは飲み薬の痛み止め(解熱鎮痛剤)と同じ成分が皮膚から吸収されるよう工夫された湿布で、痛みや炎症の元に直接作用し高い鎮痛消炎効果を発揮します。
具体的には、インドメタシン、ロキソプロフェン(ロキソニン)、ジクロフェナクナトリウム(ボルタレン)、フェルビナク、ケトプロフェン等が含まれる製品があります。
第一世代に比べて有効成分が患部から浸透しやすく、痛み止めとしての効果は強力ですが、その分成分による副作用リスクも高まる点に注意が必要です。
湿布薬の添付文書には、使用上の注意や成分表示が記載されています。
お子さんに湿布を貼る際は、まずパッケージや説明書で成分名を確認しましょう。
分かりにくい場合は薬剤師に尋ねれば、第一・第二世代の違いやお子さんに適した湿布薬についてアドバイスを受けられます。
【参考情報】『湿布薬の種類と成分(第一世代・第二世代)』桐生厚生総合病院
https://www.kosei-hospital.kiryu.gunma.jp/site/wp-content/uploads/2018/06/kusuribako_12.pdf
3. なぜ湿布で喘息発作が起こるのか

一見関係のなさそうな「喘息」と「湿布」ですが、実は湿布薬に含まれる成分によって喘息の症状が悪化したり、発作を誘発したりすることがあります。
特に注意が必要なのが、先ほど説明した第二世代湿布に含まれるNSAIDs成分です。
また、湿布自体の強い香りや皮膚への刺激も、喘息を持つお子さんに影響を与える場合があります。
なぜ湿布で発作が起こりうるのか、その原因を詳しく見ていきましょう。
3-1.NSAIDsによる「アスピリン喘息」のリスク
喘息患者さんの中には、NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)に過敏な体質を持つ方がいます。
これを一般に「アスピリン喘息」と呼びます。
アスピリン喘息の患者さんは、アスピリンそのものだけでなくすべてのNSAIDs系の痛み止めに注意が必要です。
例えば解熱鎮痛剤(飲み薬)を服用した直後に、ひどい鼻づまりや咳、ゼーゼーという喘鳴、呼吸困難などが急激に現れます。
重症の場合、意識がもうろうとしたり命に関わることもある怖い発作です。
では、湿布薬の場合はどうでしょうか?
湿布は経皮吸収のため飲み薬より作用は穏やかですが、体質によっては湿布に含まれるNSAIDsでもアスピリン喘息の発作が起こり得ることが知られています。
実際、「湿布を貼ってから30分~数時間以内に喘息発作が始まった」というケースや、原因不明の喘息悪化の要因を探った結果「湿布を使っていた」と判明した例も報告されています。
そのため、喘息持ちのお子さんが第二世代湿布を使用する際は特に注意が必要です。
湿布薬の添付文書にも「喘息をお持ちの方は使用しない」「過去に痛み止めで喘息発作を起こした人は使わない」といった使用禁忌が明記されています。
お子さんに湿布を使う前に、成分がNSAIDsに当たらないか必ず確認してください。
なお、サリチル酸メチルやサリチル酸グリコールなど第一世代湿布の成分では、現時点で喘息発作を誘発したとの報告はないとされています。
そのため、アスピリン喘息の人への注意書きも特に設けられていません。
しかし「報告がない=絶対安全」というわけではなく、正式な調査が行われていないため可能性を完全に否定できないとも言われています。
やはり喘息のあるお子さんが湿布を使う場合は、第一世代であっても用心するに越したことはありません。
【参考情報】『アスピリンぜん息(解熱鎮痛薬ぜん息)』環境再生保全機構
https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/basic/adult/knowledge/aspirin.html
【参考情報】『MS冷湿布やGSプラスターは、アスピリン喘息患者に使用できるか?』福岡県薬剤師会
https://www.fpa.or.jp/johocenter/yakuji-main/_1635.html?blockId=40998&dbMode=article
【参考情報】”Key Clinical Activities for Quality Asthma Care” by Centers for Disease Control and Prevention
https://www.cdc.gov/mmwr/pdf/rr/rr5206.pdf
3-2.湿布の香料や刺激が誘発するケース
湿布薬には成分自体の匂いのほか、ハッカ(メントール)のスーッとした香りやサリチル酸系の独特な匂いがある製品も多いです。
喘息の子どもにとって、強い香りや刺激は気道を直接刺激し、発作の引き金となることがあります。
事実、洗剤や柔軟剤に含まれる合成香料でさえ半数以上の喘息患者さんに咳や喘息発作などの症状悪化を引き起こしたとの国内研究報告もあります。
湿布を剥がした際に揮発した成分を吸い込んでしまうと、敏感な気道が反応して激しい咳込みや息苦しさにつながることも考えられます。
◆「喘息持ちの方必見!洗剤や柔軟剤で症状が悪化?避けるべき成分と対策」>>
また、湿布の貼付部位がかぶれたり赤く腫れたりする皮膚の副作用もあります。
皮膚の炎症によるストレスや痛みが間接的に喘息症状に影響する可能性も否定できません。
特にケトプロフェンを含む湿布薬では、紫外線に当たると皮膚が過敏に反応する光線過敏症のリスクも知られています。
使用中と剥がした後、数日間は直射日光を避ける注意が必要です。
【参考情報】『家族に処方された湿布薬を使って体調が悪化』家庭の医学
https://kateinoigaku.jp/qa/267
4. 喘息の子どもが湿布薬を使う際のチェックポイント

今まで紹介した内容を踏まえ、喘息を持つお子さんに湿布薬を使用する際に気を付けたいポイントを整理します。
大切なお子さんの症状を悪化させないために、以下のチェックリストを確認してください。
成分表示をチェックする:
湿布薬のパッケージや添付文書に記載された有効成分を必ず確認しましょう。
インドメタシンやロキソプロフェンなどNSAIDs系の成分が含まれている場合、自己判断で使用せず医師・薬剤師に相談してください。
「喘息の持病がある」と伝えれば、代わりの薬や安全な製品についてアドバイスをもらえます。
過去の発作歴を把握する:
お子さんがこれまでに解熱鎮痛剤で喘息発作を起こしたことがあるか確認しましょう。
いわゆるアスピリン喘息の可能性がある場合、湿布のみならず飲み薬・坐薬・塗り薬も含めNSAIDs系は厳禁です。
主治医から「NSAIDs過敏症」と診断されている場合は、湿布薬も含めて慎重に扱ってください。
第一世代湿布でも油断しない:
第一世代の湿布成分は比較的安全とされていますが(副作用が起こる頻度は低い)、完全にリスクがないわけではありません。
初めて使う湿布薬であれば、お子さんの様子に注意し、貼付後に咳込みや息苦しさがないか観察しましょう。
異変を感じたらすぐに湿布を剥がしてください。
香りの強い湿布は避ける:
湿布独特の強い匂いが苦手なお子さんも多いですし、その香料が発作の誘因になる可能性もあります。
お子さんが嫌がる場合は無理に使わず、低臭タイプの湿布や無香料の冷却ジェルシート(患部を冷やすだけの製品)など代替品の利用を検討しましょう。
貼る部位と使い方に注意:
湿布を貼る場所にも気を配りましょう。できるだけ胸や首周りなど気道に近い場所への使用は避けるのが無難です。
どうしても上半身に貼る場合は、寝る前ではなく日中に貼って様子を見る、就寝時は外す、といった工夫も一つです。
また、決められた時間以上に貼り続けない、入浴前後は貼らないなど、添付文書に沿った正しい使用方法を守ることも大切です。
症状が悪化したらすぐ受診:
もし湿布を貼った後にゼーゼーする、咳が止まらない、息苦しそうといった症状が見られたら、すみやかに湿布を剥がして安静にさせ、必要ならば救急受診を検討してください。
発作治療薬(吸入薬など)を処方されている場合は、医師の指示通りに使用しましょう。
それでも改善しない場合は迷わず医療機関を受診し、湿布を使ったことを医師に伝えてください。
以上のチェックポイントを参考に、湿布薬を使用する際は慎重を期してください。
お子さんの主治医にも「自宅で湿布を使ってよいか」相談しておくと安心です。
場合によっては、小児でも使用できるアセトアミノフェンなどの飲み薬の痛み止めや物理療法で対処する選択肢も提示してもらえるでしょう。
【参考情報】”Medications That May Trigger Asthma Symptoms” by American Academy of Allergy, Asthma & Immunology
https://www.aaaai.org/tools-for-the-public/conditions-library/asthma/medications-may-trigger-asthma-symptoms
5. 湿布以外で痛みを和らげる方法

スポーツや部活でのお子さんのケガに対して、湿布薬以外にも家庭でできる対処法があります。
喘息をお持ちのお子さんの場合、湿布の使用を避けたい場面も多いでしょう。
ここでは、湿布に頼らずに捻挫や筋肉痛の痛みを和らげる方法を紹介します。
ぜひ参考にしてください。
RICE処置:
スポーツなどで捻挫・打撲をした際の基本は「RICE処置」と呼ばれる応急手当です。
RICEとは、Rest(安静)・Icing(冷却)・Compression(圧迫)・Elevation(挙上)の頭文字を取ったもので、早期に適切な処置をすることで内出血や腫れ、痛みを抑え、治りを早める効果があります。
具体的には、ケガをした部位を動かさないよう安静に保ち、氷嚢や冷湿布で冷やします。
次に伸縮包帯などで軽く圧迫固定して腫れを防ぎ、可能であれば患部を心臓より高い位置に挙げて安静にします。
この一連の処置をできるだけ早く行い、終わったらなるべく早めに医療機関を受診しましょう。
RICE処置は応急手当であり治療そのものではないため、放置せず専門医の判断を仰ぐことが大切です。
冷却ジェルシートや氷で冷やす:
市販の冷却ジェルシートやアイスパック(保冷剤)をタオルで包んだものなどは、湿布薬の代わりに患部を冷やして痛みを和らげるのに役立ちます。
とくにケガ直後の急性期は炎症を抑えるために冷やすことが有効です。
肌に直接氷を当てると凍傷の恐れがあるため、布で包むか専用のシートを使い、15~20分冷やしたら一度外すという具合に行いましょう。
安静にして様子を見る:
軽い筋肉痛や関節痛であれば、無理をせず安静にすること自体が何よりの治療になります。
運動で痛めた場合は、しばらくその部位を休ませ、負荷をかけないようにしましょう。
痛みが強い時は無理に動かさず、まずは安静・冷却が基本です。
鎮痛剤(内服薬)を検討する:
市販の痛み止めを使う方法もあります。
ただし、NSAIDs系の飲み薬(イブプロフェン、ロキソプロフェンなど)は湿布と同様に喘息を悪化させる恐れがあるため注意が必要です。
お子さんに使用できて喘息に比較的影響が少ない解熱鎮痛薬としてはアセトアミノフェン(例:小児用バファリンなど)が一般的です。
こちらも一度主治医に相談し、適切な種類と用量の指示を仰ぐと安心です。
ストレッチや温熱で筋肉をほぐす:
急性期を過ぎて痛みが和らいできたら、軽いストレッチやマッサージで血行を促進してあげると回復が早まることがあります。
筋肉痛の場合、軽いストレッチを行うことで疲労物質が流れやすくなり、必要な酸素や栄養が筋肉に行き渡って痛みの軽減につながるとされています。
もちろん痛みが強い間は無理に動かさず、炎症が落ち着いた段階で行いましょう。
また、入浴で温めると筋肉のこわばりが取れやすくなります。
ただし、打撲や捻挫の直後は温めると腫れが悪化するため、炎症が治まってからにしてください。
これらの代替ケアを行っても痛みが引かない、腫れがどんどん酷くなる、関節の変形が見られるなど重症が疑われる場合は、早めに整形外科を受診しましょう。
お子さん自身も成長過程で、痛みを無理に我慢すると後遺症につながる恐れもあります。
適切な検査・治療を受け、安心してスポーツに復帰できるようにしてください。
【参考情報】『RICE処置とは何か』オムロン
https://www.healthcare.omron.co.jp/pain-with/sports-acute-pain/rice/
【参考情報】『筋肉痛を改善するには』久光製薬
https://www.e-hisamitsu.jp/health/special/muscle-training/?srsltid=AfmBOoqqHtstjl7JseJMxtRBkIk1dI6C6BBCCMj76Pbq18KhSP5FMYEN
【参考情報】”Early treatment of injury” by MedlinePlus (U.S. National Library of Medicine)
https://medlineplus.gov/ency/imagepages/19396.htm
6. おわりに
喘息をもつお子さんに湿布薬を使用する際の注意点について解説しました。
湿布に含まれるNSAIDs成分や強い香料が発作を誘発する可能性があるため、成分の確認と慎重な使用が大切です。
どうしても湿布を使う場合は第一世代を選び、異変があればただちに中止してください。
また、冷却や安静など湿布以外の対処法も上手に取り入れましょう。
お子さんの喘息を悪化させずにケガの痛みをケアできるよう、日頃から主治医や薬剤師と相談しながら安全に対処していきたいですね。



