呼吸器内科と外科の違いは?症状で選ぶ受診先ガイド

「咳が続いて息苦しい」「胸が痛むけど、内科と外科どちらに行けばいいの?」
呼吸器の症状があっても、どちらを受診すべきか迷う方は少なくありません。
この記事では、呼吸器内科と呼吸器外科の違いをわかりやすく解説し、あなたの症状に合った受診先を選ぶための具体的な判断基準をご紹介します。
1. 呼吸器内科と呼吸器外科、それぞれの役割と得意分野
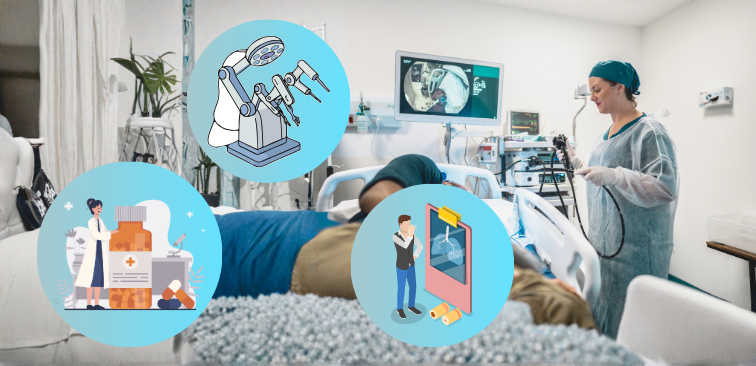
呼吸器に関わる診療科には「呼吸器内科」と「呼吸器外科」の2つがあります。
どちらも肺や気管支などの呼吸器を専門に扱いますが、治療のアプローチが大きく異なります。
まずは、それぞれの役割と得意分野を理解しましょう。
1-1. 呼吸器内科の役割と治療内容
呼吸器内科は、薬による治療や内視鏡検査を中心に行う診療科です。
咳や痰、息切れ、呼吸困難といった症状に対して、まず診断を行い投薬治療やリハビリテーションで改善を目指します。
喘息・慢性閉塞性肺疾患(COPD)・肺炎・間質性肺炎などの疾患は、基本的に手術を必要とせず、薬物療法や生活指導を中心とした内科的管理で治療します。
◆「呼吸器内科とはどんな診療科?」について>>
◆「喘息とはどんな病気?」はこちら>>
【参考情報】”About COPD” by Centers for Disease Control and Prevention
https://www.cdc.gov/copd/about/index.html
1-2. 呼吸器外科の役割と治療内容
呼吸器外科は、手術による治療を専門としています。
肺がんや気胸など手術が必要な呼吸器の病気を扱い、呼吸器内科で診断された病気が進行した際にも対応が可能です。
近年では胸腔鏡を用いた手術が主流で、傷が小さく回復も早いのが特徴といえるでしょう。
ロボット支援手術なども導入され、より精密で安全な手術が実現しています。
1-3. 両者の連携について
呼吸器内科と呼吸器外科は、互いに連携して患者さんの治療にあたります。
例えば、呼吸器内科で肺がんと診断された患者さんが手術適応と判断された場合、呼吸器外科への紹介が検討されるでしょう。
逆に、手術後の経過観察や薬物療法は呼吸器内科が担当するケースも少なくありません。
このように、両科は患者さんの状態に応じて役割分担しながら最適な治療を提供しています。
2. 症状別チェックリスト:この症状ならどちらに受診すべきか?

ここでは具体的な症状ごとに、呼吸器内科と呼吸器外科のどちらを受診すべきかの判断基準をご紹介します。
ただし、これはあくまで目安であり実際には医師の診察を受けて適切な診療科を判断してもらうことが大切です。
2-1. 長引く咳・痰の症状
2週間以上続く咳や痰・息切れなどの症状は、呼吸器の病気のサインかもしれません。
以下のチェックリストで当てはまる症状があるか確認してみましょう。
【こんな症状はありませんか?】
✓ 2週間以上咳が続いている
✓ 痰が絡む・痰の色が黄色や緑色になった
✓ 痰に血が混じる(血痰)
✓ 発熱を伴う咳がある
✓ 夜間や明け方に咳がひどくなる
✓ 階段を上ると息が切れる
✓ 以前より運動時に息苦しさを感じる
✓ ゼーゼー、ヒューヒューという呼吸音がする
→ これらの症状がある方は呼吸器内科を受診しましょう
これらは気管支炎・喘息・肺炎・COPDなど、内科的な治療が必要な病気のサインである可能性が高いです。
特に血痰が出る場合は、肺がんや肺結核などの可能性も考えられるため必ず医療機関を受診してください。
◆「長引く咳で疑われる疾患について」はこちら>>
◆「血痰が出る原因は?」>>
【参考情報】『慢性閉塞性肺疾患/COPD』日本呼吸器学会
https://www.jrs.or.jp/citizen/disease/b/b-01.html
【参考情報】”Signs and Symptoms of Tuberculosis” by Centers for Disease Control and Prevention
https://www.cdc.gov/tb/signs-symptoms/index.html
2-2. 胸痛・突然の呼吸困難
胸痛や突然の呼吸困難は、心臓や呼吸器の重大な病気のサインである可能性があります。
以下の症状に当てはまるものがあるか確認してください。
【こんな症状はありませんか?】
✓ 深呼吸をすると胸が痛む
✓ 咳をすると胸が痛む
✓ 片側の胸だけが痛む
✓ 突然の激しい胸痛がある
✓ 胸痛と同時に呼吸が苦しくなった
✓ 安静時にも息苦しさを感じる
✓ 横になると呼吸が苦しくなる
✓ 唇や爪が青紫色になっている(チアノーゼ)
→ まずは呼吸器内科を受診し、必要に応じて専門科に紹介してもらいましょう
特に、突然の激しい胸痛と呼吸困難が同時に起こった場合は、気胸の可能性があります。
速やかに医療機関を受診してください。
◆「咳による胸の痛みの原因と病気」>>
◆「気胸とは?」について>>
【参考情報】”Spontaneous Pneumothorax” by National Institutes of Health
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441885/
3. 診療科別に扱う主な疾患・治療法

呼吸器内科と呼吸器外科では、扱う疾患や治療法が異なります。
ここでは各診療科で対応する代表的な疾患と、その治療アプローチについて解説します。
3-1 呼吸器内科で扱う疾患
呼吸器内科では、気管支喘息・COPD(慢性閉塞性肺疾患)・肺炎・間質性肺炎・肺結核・睡眠時無呼吸症候群などの疾患を主に扱います。
ここでは、特に代表的な疾患についてご紹介します。
喘息: アレルギーや刺激により気道が狭くなり、発作的に咳や呼吸困難が起こる。吸入ステロイド薬や気管支拡張薬で症状をコントロールする。
COPD(慢性閉塞性肺疾患): 主に喫煙が原因で、肺の組織が破壊され息切れが起こる。禁煙が最も重要な治療で、気管支拡張薬や吸入ステロイド薬の使用が一般的。
肺炎: 細菌やウイルスなどが肺に感染して炎症を起こす。抗生物質による治療が中心。
◆「COPDとは?」はこちら>>
◆「睡眠時無呼吸症候群」について>>
3-2. 呼吸器内科で行われる主な検査
呼吸器内科では、胸部X線検査・CT検査、呼吸機能検査(スパイロメトリー)、気管支鏡検査、血液検査、痰の検査などを行います。
胸部X線検査・CT検査では肺の状態を画像で確認し、呼吸機能検査では肺活量や息を吐く速さを測定して肺の機能を評価します。
気管支鏡検査では、細い内視鏡を用いて気管支の内部を直接観察したり、組織を採取したりすることが可能です。
これらの検査結果をもとに、適切な診断と治療方針が決定されるでしょう。
【参考情報】『肺機能検査とはどのような検査法ですか?』日本呼吸器学会
https://www.jrs.or.jp/citizen/faq/q27.html
3-3. 呼吸器外科で扱う主な疾患
呼吸器外科では、肺がん・転移性肺腫瘍・気胸・膿胸・胸壁腫瘍などの疾患を主に扱います。
肺がん: 呼吸器外科で最も多く扱う疾患で、早期であれば手術による完治が期待できる。
気胸: 肺に穴が開いて空気が漏れる病気。繰り返す場合や重症の場合は手術が必要。
膿胸(のうきょう): 胸腔に膿がたまる病気。抗生物質治療と並行して、ドレナージ(胸にたまった膿や血液・体液などを外に排出する処置)や手術が必要になることがある。
【参考情報】”Non-Small Cell Lung Cancer Treatment (PDQ®)” by National Cancer Institute
https://www.cancer.gov/types/lung/hp/non-small-cell-lung-treatment-pdq
3-4. 呼吸器外科で行われる主な手術
呼吸器外科では、患者さんの状態や病気の進行度に応じて、さまざまな手術法が選択されます。
肺葉(はいよう)切除術は、肺がんなどの場合に病変のある肺葉を切除する手術です。
肺部分切除術は、小さな病変の場合に病変部分のみを切除します。
胸腔鏡下(きょうくうきょうか)手術は、胸に小さな穴を数か所開けてカメラと手術器具を挿入して行う手術で、傷が小さく回復が早いという利点があります。
近年ではロボット支援手術なども導入されています。
4. 内科と外科で異なる受診後の流れ

呼吸器内科と呼吸器外科では、受診後の治療の流れが異なります。
ここでは、それぞれの診療科を受診した後の一般的な流れをご紹介します。
4-1. 呼吸器内科受診後の流れ
呼吸器内科を受診すると、問診・検査・診断・治療開始という流れになります。
まず医師は症状の詳細(いつから、どのような時に、どの程度)や既往歴、喫煙歴などを詳しく聞き取り、聴診器で呼吸音を確認します。
その後、胸部X線検査や血液検査などで診断を進め、必要に応じてCT検査・呼吸機能検査・気管支鏡検査などが追加されることもあります。
診断が確定したら、薬物療法や吸入療法などの治療が開始されます。
喘息やCOPDでは吸入ステロイド薬や気管支拡張薬で症状をコントロールし、肺炎では抗生物質による治療が中心となります。
定期的に通院して症状の変化や治療効果を確認し、病状が安定してきたら通院間隔を延ばすことも可能でしょう。
手術が必要と判断された場合は、呼吸器外科に紹介となります。
◆「呼吸器内科で行われる検査とは?」について>>
◆「喘息で使われる吸入薬について」詳しく>>
◆「気管支拡張薬 ホクナリンテープ」について>>
4-2. 呼吸器外科受診後の流れ
呼吸器外科は、多くの場合、呼吸器内科からの紹介で受診します。
まずCT検査・PET検査・気管支鏡検査などの精密検査を行い、がんの進行度や患者さんの全身状態・呼吸機能などを総合的に評価します。
そして手術が可能かどうか・どのような術式が適切かを決定します。
手術が決まったら血液検査・心電図・呼吸機能検査などの術前検査を行い、手術に耐えられる体力があるかの確認が必要です。
手術は全身麻酔下で行われ、入院期間は手術の種類によりますが1〜2週間程度が一般的でしょう。
近年は胸腔鏡下手術やロボット支援手術など手術が主流となり、回復も早くなっています。
退院後も定期的に通院し、CT検査や血液検査で再発の有無をチェックしていきます。
始めは1〜3ヶ月ごと、病状が安定してきたら6ヶ月〜1年ごとに受診となります。
【参考情報】『肺がん 療養』国立がん研究センター がん情報サービス
https://ganjoho.jp/public/cancer/lung/follow_up.html
5. リスクが高いケース・早期受診を要する症状とは

呼吸器の症状の中には、すぐに医療機関を受診すべき緊急性の高いものがあります。
ここでは、特に注意が必要な症状やリスクが高いケースについて解説します。
5-1. すぐに受診すべき緊急性の高い症状
以下のような症状がある場合は、すぐに医療機関を受診してください。
場合によっては救急車を呼ぶことも検討してください。
【緊急性の高い症状チェックリスト】
✓ 安静時にも息苦しさがあり、会話ができないほどの呼吸困難
✓ 唇や爪が青紫色になっている(チアノーゼ)
✓ 痰に鮮血が混じる、または口から血を吐く(血痰・喀血)
✓ 呼吸困難とともに意識がもうろうとする
✓ 突然の激しい胸痛がある
✓ 高熱(38度以上)と激しい咳が続く
これらの症状は命に関わる可能性があるため、ためらわずに医療機関を受診してください。
特に、突然の胸痛と呼吸困難が同時に起こった場合は気胸や肺梗塞の可能性があり、高熱と激しい咳は重症肺炎の可能性があります。
高齢者や基礎疾患のある方は特に注意が必要です。
5-2. ハイリスク群の方が注意すべきこと
以下のような方は呼吸器の病気が重症化しやすいため、特に注意が必要です。
少しでも気になる症状があれば、早めに医療機関を受診しましょう。
【ハイリスク群チェックリスト】
✓ 喫煙している、または過去に喫煙歴がある
✓ 65歳以上の高齢者
✓ 糖尿病、心臓病、腎臓病などの基礎疾患がある
✓ リウマチなどで免疫抑制薬やステロイドを長期使用している
✓ アスベストやシリカなどへの職業的曝露歴がある
✓ 家族に肺がんや呼吸器疾患の方がいる
該当する方は定期的な健康診断を受け、異常があれば早めに受診してください。
喫煙者・喫煙歴のある方は肺がん、COPD、慢性気管支炎などのリスクが高くなります。
高齢者は肺炎が重症化しやすく、回復にも時間がかかります。
免疫抑制薬を使用している方は感染症にかかりやすく重症化しやすいため、風邪症状でも油断は禁物です。
5-3. 早期受診のメリット注意すべきサイン
呼吸器の病気は早期に発見して治療を始めることで、治療の選択肢が増え治癒率が向上します。
また、症状が軽いうちに治療を開始することで、生活の質を保つことができ医療費の負担も軽減されます。
【特に注意すべきサイン】
✓ 2週間以上続く咳
✓ 痰に血が混じる
✓ 原因不明の体重減少
✓ 息切れが以前よりも悪化している
✓ 声がかすれる
✓ 繰り返す肺炎や気管支炎
肺がんは早期には症状が出にくいため、これらのサインがある場合は必ず受診しましょう。
特に、喫煙歴のある方や家族に肺がんの方がいる場合は注意が必要です。
気になる症状があれば、早めに医療機関を受診することが大切です。
【参考情報】『肺がん検診について』国立がん研究センター がん情報サービス
https://ganjoho.jp/public/pre_scr/screening/lung.html
6. おわりに
呼吸器内科と呼吸器外科は、連携して患者さんの治療にあたっています。
長引く咳や息切れ・胸痛などの症状がある場合は、まず呼吸器内科を受診しましょう。
必要に応じて呼吸器外科に紹介され、適切な治療を受けることができます。
症状を放置せず、早めに医療機関を受診することが大切です。



