赤ちゃんから小児期の咳。注意したいポイントは?

子どものつらそうな咳や、咳によって眠れない姿を見るととても心配になりますよね。
特に赤ちゃんの場合は自分で症状を伝えることができない分、判断に迷うこともあると思います。
赤ちゃんの咳で考えられる病気や注意点、小児期に多い喘息の基礎知識や治療の工夫などについて紹介します。
1.赤ちゃんの咳から考えられる病気

咳は主に、気管、気管支、細気管支のいずれかに異常がある時に起こります。
咳が出るメカニズムは大人も赤ちゃんも基本的には同じですが、赤ちゃんは気管の壁がやわらかく狭いためわずかな刺激でも咳が出やすい傾向にあります。
咳はほこり・痰などの異物や病原体を空気の通り道である気道から排除するために起こります。
赤ちゃんの咳で考えられる原因は大きく分けて3つあります。
1-1.感染症によるもの

咳がでる小児の感染症として、風邪、RSウイルス感染症、クループ症候群などがあります。
特に生後3カ月未満の赤ちゃんは抵抗力が弱いためウイルスに感染すると重症化しやすいので注意が必要です。
〈風邪〉
多くはウイルス感染により、咳、痰、のどの痛み、発熱、倦怠感などの症状が見られます。
赤ちゃんの場合、症状を訴えることができませんが、咳や発熱などの症状に加えて「いつもに比べて哺乳量が少ない」「顔色が悪い」「機嫌が悪くぐったりしている」などの異変を感じたら病院を受診するようにしましょう。
また、風邪から肺炎や気管支炎に移行してしまうこともあるため注意が必要です。
〈RSウイルス感染症〉
接触感染や飛沫感染によりRSウイルスに感染することで、発熱、咳、鼻水などの症状が現れます。
子どもに多い感染症で、生後1歳までに半数以上、2歳までにほぼ100%がかかると言われています。
特に生後6か月以内に感染した場合は、細気管支炎や肺炎など重症化することが多く注意が必要です。
【参考文献】『RSウイルス感染症Q&A』厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/rs_qa.html
〈クループ症候群〉
クループ症候群は、ウイルスなどが喉の奥の咽頭という部分に感染して炎症が起こり、空気の通り道が狭くなることで咳や息苦しさが生じる病気です。
「オウッオウッ」というオットセイの鳴き声のような咳や、「ケンケン」という犬の鳴き声のような咳が特徴的です。
いつもの咳と違うと感じたら、動画を撮っておくと診断の手がかりとなります。
咳や息苦しさの他に、発熱やのどの痛みも伴うことがあります。
【参考文献】”Croup” by Mayo Clinic
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/croup/symptoms-causes/syc-20350348
1-2.アレルギーや喘息によるもの

ホコリやダニなどのハウスダスト、花粉やペットの毛などによるアレルギー反応によって咳が出ることもあります。
乳幼児から高齢者まで国民の2人に1人が何らかのアレルギー疾患を持っていると言われています。
身近で起こりうる原因ですので、室内を清潔に保ち、事前にアレルゲン(アレルギーの原因となる物質)を除去することが大切です。
また、食物アレルギーやアトピー性皮膚炎がある場合、気管支喘息の可能性もあります。
咳が2週間以上続いていたり、「ヒューヒュー」「ゼイゼイ」といった呼吸音の喘鳴がある場合は喘息が疑われますので、早めに受診しましょう。
【参考情報】『免疫アレルギー疾患研究10か年戦略』日本呼吸器学会
https://www.jrs.or.jp/information/file/6e19cdbe1842ce4e6e5d8edfbd60411a4a4db187.pdf
◆「子どもの長引く咳」についてもっと詳しく>>
1-3.温度変化によるもの

感染症などがなくても、夜間や明け方など気温や湿度に変化があると気道の粘膜が敏感に反応して咳き込みやすくなります。
特に冬場の冷たい空気や乾燥した空気によって咳が出やすくなるので、赤ちゃんの部屋は暖かく、加湿器などを使って湿度も一定に保ちましょう。
2.赤ちゃんは痰のつまりに注意
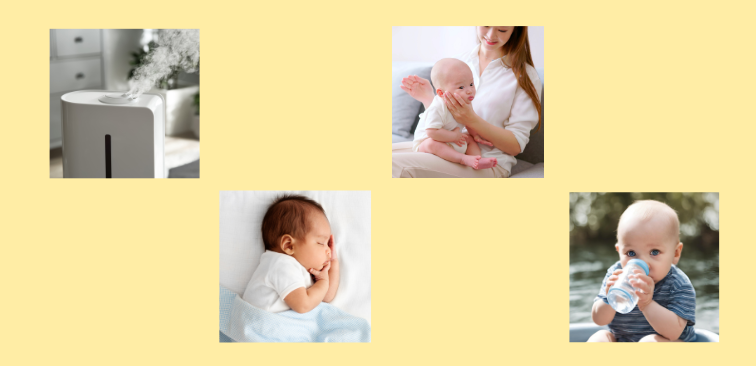
激しい咳や2週間以上続く咳は、風邪以外の疾患が原因である可能性があります。いくつか考えられる疾患をみていきましょう。
赤ちゃんは気道が狭く、大人のように上手く排痰することもできないので、痰が絡まって苦しそうになったり、痰が詰まって嘔吐してしまうこともあります。
「ゼロゼロ」と苦しそうに呼吸をしている時は、次のような方法で楽になることがあります。
・部屋を加湿する
・常温の水分を摂り、痰をゆるくする
・痰がでやすいように背中を軽くたたく
・首が座っている赤ちゃんであれば、上体を起こす、横向きで寝かせる
痰は通常、サラサラとした無色透明ですが、細菌に感染していると黄色や緑色の痰になることがあります。
痰の色がおかしい、全身を使って苦しそうに呼吸をしている、哺乳量が少ないなどの異常が見られる場合は早めに病院を受診してください。
3.小児期の咳も注意が必要

小児とは、7歳以上15歳未満の学童期の子どもを指します。
小児期は学校生活により感染症にかかる機会が増えるほか、親から離れることで様々なリスクが生じる時期です。
小児喘息はアレルギー物質が原因となることが多く、給食などに含まれるアレルゲンを摂取してしまうこともあります。
また、冷えた体育館の空気や砂埃、運動によっても喘息が誘発されることがあるため、喘息の持病があるお子さんやアレルギー体質のお子さんは注意が必要です。
感染症が喘息発作のきっかけとなることもありますので、基本的な感染予防行動も大切です。
4.小児喘息。どんな治療?

小児喘息の患者さんは気道が慢性的に炎症を起こしているため、症状がない時でも気道が過敏な状態になっています。
そこに様々な刺激が加わることで気道平滑筋(呼吸をスムーズにするための筋肉)の収縮、気道粘膜の浮腫、気道分泌の亢進が引き起こされ、気道内腔が狭くなります。
発作の原因となる刺激にはアレルゲンや、運動、感染症、天候の変化、精神的ストレスなどがあります。
気道が狭くなることによって咳や「ゼイゼイ」「ヒューヒュー」のような喘鳴、呼吸困難などの症状が見られます。
治療してすぐに治るものではなく、長期的な治療が必要な病気です。
しかし、小児喘息は成人になってから発症する喘息に比べて完治する可能性が高いため、「子どものうちに治しきる」という意識で治療に臨みましょう。
小児喘息の治療には、発作が起きたときに呼吸を楽にする発作治療薬と、気管支の状態を良くして発作を予防する長期管理薬、発作の原因を取り除くための日常生活管理があります。
【参考文献】”Childhood asthma” by Mayo Clinic
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/childhood-asthma/symptoms-causes/syc-20351507
4-1.発作治療薬
喘息発作が起きてしまった場合、まず発作強度(小発作・中発作・大発作・呼吸不全)を判定します。
基本的な薬剤治療として、β₂刺激薬の投与を行います。
β₂刺激薬は気管支を拡張して呼吸を楽にする薬で、即効性があります。
具体的な商品名としては次のようなものがあります。
・吸入薬:メプチンエアー、サルタノールなど
・経口薬:メプチン、ベネトリン、ホクナリン、スピロペントなど
β₂刺激薬は、心身を活動モードにする交感神経に作用するため、副作用として心悸亢進(ドキドキする)などが起こることがあります。
4-2.長期管理薬
長期管理薬としては主に、気管支の炎症を抑えるために吸入ステロイド薬(アドエア、フルタイドなど)を投与します。
吸入後は必ずうがいをし、口に残った薬を洗い流しましょう。
吸入薬は自分で上手く吸う力が必要なため、乳幼児や小学校低学年の子どもには難しい場合もあります。
吸入が難しい場合はスペーサーやネブライザーという吸入補助具を使います。
例えばマスクタイプのスペーサーでは、マスクを装着し普通に呼吸をするだけで必要な薬剤を吸入させることができます。
【参考文献】『セルフケアのための主な小児ぜん息治療薬』環境再生保全機構
https://www.erca.go.jp/yobou/pamphlet/form/00/pdf/kyuunyuposter.pdf
4-3.日常生活管理
ダニなどのアレルゲンが喘息発作の誘因となるため、室内をこまめに掃除しましょう。
また、運動は発作の誘因になりますが全く運動しないというのは良くありません。
適切な薬剤治療を継続できていれば運動をしても発作が起こりにくいため、かかりつけ医で相談の上取り組みましょう。
ウォーミングアップを行うことや、発作が起こりにくい水泳などを取り入れることで体力づくりにもなります。
5.おわりに
小児期の学校生活では喘息のリスクが多く、吸入などの自己管理も難しい部分もあります。
保護者のサポートや、補助具の活用などで喘息と上手く付き合うことができれば、通常と同じような生活が可能になります。
また、赤ちゃんの咳の場合、症状を自分で伝えられないため、保護者の観察が重要になります。
「いつもより哺乳量が少ない」「顔色や機嫌が悪くぐったりしている」という症状が見られたら、すぐに病院を受診してください。



