「非結核性抗酸菌症」の基本情報
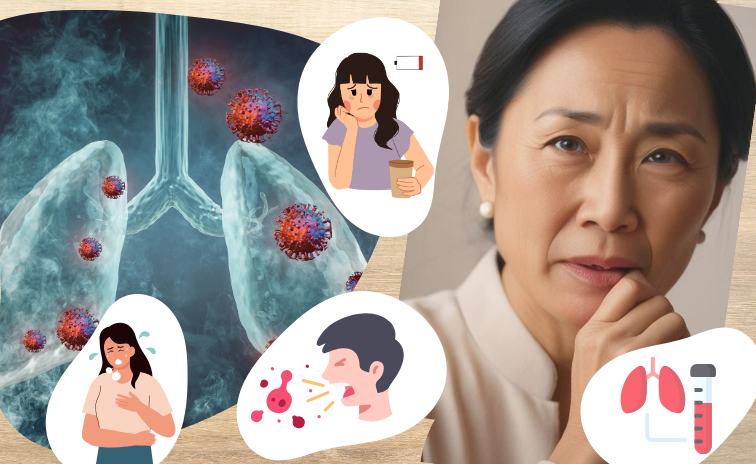
非結核性抗酸菌症(ひけっかくせいこうさんきんしょう)は、結核菌ではない抗酸菌によって引き起こされる感染症です。
結核菌やらい菌以外の菌が、「非結核性抗酸菌」と呼ばれています。
身近に存在している細菌で、その数は約200種類以上あるとされていますが、実際に人へ感染を起こすのは約30種類程度です。
感染を起こし発症すると、咳や痰などが主な症状としてあらわれます。
今回の記事では、非結核性抗酸菌症の特徴や症状、検査、治療について、基本情報を分かりやすく解説します。
あまり聞きなれない感染症ですが、誰でも感染する可能性がある病気です。
特徴や症状を理解しておくと、早期発見に役立つでしょう。
1.非結核性抗酸菌症の特徴

非結核性抗酸菌症は、肺に抗酸菌が感染して起こる病気です。数年から数十年かけ慢性的に進行するのが特徴です。
結核とは異なり、進行が遅いため、自覚症状が出るまで時間がかかる場合があります。
そのため、健康診断や人間ドックでたまたま見つかるケースも少なくありません。
抗酸菌は非常に多種多様で土壌や水、空気中に広く存在しており、私たちの生活環境にごく普通にいる細菌です。
非結核性抗酸菌のなかで、最も多いのは「マイコバクテリウム・アビウム」と「マイコバクテリウム・イントラセルラー」と呼ばれる菌です。
この2つの菌を合わせてMAC菌と呼んでおり、感染すると肺MAC症になります。
これらは肺を中心に感染を起こすことが多いですが、生活環境で存在しているため、完全に防ぐことは難しいとされています。
この菌は感染力が強いわけではなく、人から人への直接感染はほとんどありません。また、感染したからといって必ず発症するわけでもありません。
しかし、以下のような方は感染すると発症リスクが高い方です。
・免疫力が低下している方
・肺に既存の病気がある方
・体力が低下している方
免疫不全疾患(エイズなど)や自己免疫疾患(関節リウマチなど)の方は免疫機能の低下があるため、感染すると発症しやすい状態です。
また、ステロイド治療中の方や抗がん剤投与中の方も、免疫機能が低下しやすく、病状によっては体力も低下しているため注意が必要です。
結核の後遺症やCOPD(慢性閉塞性肺疾患)、気管支拡張症など、肺や気管支など呼吸機能の低下がある方も発症リスクが高いといえます。
また、最近では「中高年のやせ型の女性」に非結核性抗酸菌症が増加しています。
ガーデニングや家庭菜園など、庭いじりが好きな方は特に注意しましょう。
【参考情報】『結核症の基礎知識 肺非結核性抗酸菌症 学会雑誌第96巻第3号』日本結核・非結核性抗酸菌症学会
https://www.kekkaku.gr.jp/books-basic/pdf/7.pdf
【参考情報】”Learn about NTM Lung Disease” by American Lung Association
https://www.lung.org/lung-health-diseases/lung-disease-lookup/nontuberculous-mycobacteria/learn-about-nontuberculosis-mycobacteria
2.非結核性抗酸菌症の症状

非結核性抗酸菌症の症状は多岐にわたり、初期の段階では風邪や気管支炎の症状と似ているため、見過ごされることも少なくありません。
非結核性抗酸菌症は診断されている方だけでも19万人にも及び、潜在的にはさらに多くの患者さんが存在すると考えられています。
中年以降の女性に多く、軽症では感冒の区別できるような特異的な症状はないために多くはレントゲン検査にて偶発的に発見されます。
軽症の場合は間欠的な症状で進行は緩徐(かんじょ)のことが多いです。
しかし進行していく症例も少なからずあり病気の勢いを判断することは重要なことです。
以下は非結核性抗酸菌症の主な症状です。
・慢性的な咳
・痰や血痰
・微熱や倦怠感
・体重減少
・息切れや呼吸困難
症状の特徴を解説します。
【慢性的な咳】
非結核性抗酸菌症の最も一般的な症状です。咳は乾いた咳や痰を伴う湿った咳がみられます。
特に数週間以上の長期に渡って続く場合は非結核性抗酸菌症だけでなく、ほかの病気の可能性もあります。
一度受診しておくと安心です。
【痰や血痰】
症状が進行すると、痰が増えてきます。色は透明から黄色、時には緑色になることもあります。
血が混じる血痰(けったん)が見られることもあります。
痰の色や性状の変化も意識しておきましょう。
【微熱や倦怠感】
微熱が続いたり、慢性的なだるさを感じたりします。発熱は高熱よりも37℃台の微熱が続くことが特徴です。
【体重減少】
食欲が低下し、結果、体重が徐々に減少していきます。この症状は病気が進行しているサインのひとつです。
体重が減少すると体力の低下を招き、回復が遅れる原因になります。
【息切れや呼吸困難】
肺が炎症を起こし呼吸機能が低下することで、階段を上がるなどの日常的な動作で息切れを感じるようになります。
さらに病状が進行すると、呼吸困難を起こし酸素吸入が必要になるケースがあります。
これらの症状はひとつだけでなく、複数が同時にあらわれたり、症状が出たり引いたりを繰り返すことも特徴です。
症状の重さも個人差があり、無症状のケースから重篤な症状まで幅広くあらわれます。
無症状の場合は発見までに時間がかかり、治療開始が遅れるケースもあります。
【参考情報】”Nontuberculous Mycobacteria Infections” by Cleveland Clinic
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/21200-nontuberculous-mycobacteria-infections
3.非結核性抗酸菌症の診断・検査

結核性抗酸菌症の診断には、症状の確認だけでなく、さまざまな検査を組み合わせて判断します。
ここでは、診断の流れや必要な検査について詳しく解説します。
3-1.診断方法
非結核性抗酸菌症の診断は、主に以下の2つの基準を満たす必要があります。
・臨床的基準
・細菌学的基準
それぞれの基準について解説します。
【臨床的基準】
胸部CT検査で以下のような所見を確認します。
・結節性陰影(けっせつせいいんえい)…肺の中に丸みをおびた白い影が映ること
・小結節性(しょうけっせつせい)陰影…肺の中に直径数ミリ以下の小さな丸い影が見られること
・分枝状(ぶんしじょう)陰影の散布…肺の中に木の枝のように分岐するような影が映ること
・均等性陰影…比較的均一な濃度の白っぽい影のこと。「肺の曇り」とも呼ばれる
・空洞性陰影…肺の中に空洞(穴)のような黒い影が見られること
・気管支または細気管支拡張陰影…肺の中に木の枝のように分岐する太くて黒い影が見られること。気管支が拡がっている状態を表わす。
いずれかひとつ、または複数所見がないか確認します。また、他の呼吸器疾患を除外する必要があります。
なかには結核と画像所見が似ているものもあるため、結核との鑑別は重要です。
【微生物学的基準】
病原菌を特定するために、痰を培養して菌を確認する検査(喀痰(かくたん)培養)を行います。
菌種の区別は必要なく、培養検査で以下のいずれかひとつを満たす必要があります。
・異なった喀痰検体での培養で2回以上の陽性が示されること
・気管支洗浄液および肺胞洗浄液での培養で1回以上の陽性が示されること
・経気管支(けいきかんし)肺生検や肺生検組織で採取した検体で抗酸菌症に合致する所見を認め,組織または喀痰検体での培養で1回陽性が示されること
臨床学的基準と微生物学的基準の観点から診断を行います。
無症状のケースもあるため、症状の有無は診断には影響しません。
【参考情報】『肺非結核性抗酸菌症診断に関する指針─2024年改訂』日本結核・非結核性抗酸菌症学会
https://www.kekkaku.gr.jp/pub/pdf/Guidelines_for_the_Diagnosis_of_Non-tuberculous_Mycobacterial_Antimycosis_2024_rev.pdf
【参考情報】”Diagnosing Nontuberculous Mycobacterial Infections” by NYU Langone Health
https://nyulangone.org/conditions/nontuberculous-mycobacterial-infections/diagnosis
3-2.必要な検査
非結核性抗酸菌症の診断には、以下のような検査が用いられます。
・喀痰検査
・画像検査
・血液検査
・気管支鏡検査
それぞれの検査について解説します。
【喀痰検査】
痰を採取し、顕微鏡で抗酸菌を確認したり、培養を行って菌の種類を特定したりします。
非結核性抗酸菌が複数回検出されることが重要です。
喀痰検査の検体を取る前に、口の中の雑菌が痰に混入しないよう事前にうがいをしてもらいます。
うがい後、患者さん自身で専用の容器に痰を吐き出してもらい検査を行います。
【画像検査】
非結核性抗酸菌症の診断基準で、胸部CT検査で陰影を確認することが必要とされています。
胸部CT検査は、胸部レントゲンよりも詳細な画像を得ることができ、肺の異常をより正確に把握できます。
特に、小さな結節や気管支拡張の所見が診断の手がかりです。
胸部CT検査は、CT検査室で行います。撮影の部位によって、向きを変えたり一時的に息を止めたりする必要があるため、検査技師の指示に従ってください。
【血液検査】
血液検査は、体内の炎症の有無や程度を確認するために行います。
また、MAC菌に感染すると血液中のMAC抗体値が上昇するため、補助診断として有用です。
血液検査は、非結核性抗酸菌症自体を直接診断するわけではありませんが、他の病気との鑑別に役立ちます。
【気管支鏡検査】
気管支鏡検査は、痰が出せず喀痰検査ができない場合や診断が難しい場合に行われます。
そのため、必ず行う検査ではありません。
気管支鏡検査は、気管支鏡を用いて肺の内部を直接観察し、洗浄液や組織を採取します。
口や鼻から気管支鏡を入れ、病変部の観察や洗浄液の注入と吸引を行います。
気管支鏡は柔らかい管でできており局所麻酔を行いますが、非常に侵襲(体への負担)が大きい検査のため、検査の実施には慎重な検討が必要です。
採取した組織や検体は、顕微鏡で観察し、非結核性抗酸菌による感染の特徴を確認します。
非結核性抗酸菌症は、症状や画像所見が他の呼吸器疾患と似ているため、診断が難しい感染症です。
特に、結核やCOPD、肺がんなどとの鑑別が必要で、経験豊富な呼吸器内科医の診察が重要となります。
【参考情報】”Clinical Overview of Nontuberculous Mycobacteria (NTM)” by Centers for Disease Control and Prevention
https://www.cdc.gov/nontuberculous-mycobacteria/hcp/clinical-overview/index.html
4.非結核性抗酸菌症の治療

治療については年齢、病勢によって異なりますが軽症の場合は経過観察することも多く、治療効果と治療の副作用などを総合的に判断して慎重に治療適応を検討することが重要となります。
治療は主に抗菌薬による長期的な薬物療法を基本に治療が進められます。治療期間は通常12か月以上に及び、継続的な通院が必要です。
使用される薬剤は、通常マクロライド系抗菌薬と抗結核薬2剤を併せた3剤を使用します。
治療中の副作用管理は非常に重要であり、定期的な血液検査や肝機能のモニタリングを行います。
副作用の影響が大きい場合、治療薬の組み合わせや投与量を調整することで、副作用の軽減を図ることが可能です。
そのため、治療中は患者さん自身の体調変化や症状について、些細なことでもいいので変化や疑問があれば、医師に伝えましましょう。
また、抗菌薬の治療以外に、症状緩和や体力維持のための生活習慣の改善も行います。
症状緩和のためには対症療法を行います。咳には鎮咳(ちんがい)薬、痰には去痰薬、発熱には解熱薬など、つらい症状を緩和するための治療です。
以下は、日常生活での注意点です。
・禁煙
・栄養バランスの取れた食事
・適度な運動
・疲れやストレスをためない
・十分な睡眠
そのほか、庭いじりや家庭菜園、農業などをしている方は、マスクをするなど土埃を吸い込まないような対策をしましょう。
非結核性抗酸菌症は、病気の進行をある程度抑えることはできても、完全に治癒させることはできません。
菌が完全に消えることはほとんどなく、治療が終了しても再発のリスクがあります。再発がないか、定期的な検診を受けることが大切です。
【参考情報】『病気と健康の話 肺非結核性抗酸菌症』小郡三井医師会
http://www.ogorimii-med.net/column/%E8%82%BA%E9%9D%9E%E7%B5%90%E6%A0%B8%E6%80%A7%E6%8A%97%E9%85%B8%E8%8F%8C%E7%97%87
【参考情報】”Treatment of Nontuberculous Mycobacterial Pulmonary Disease: An Official ATS/ERS/ESCMID/IDSA Clinical Practice Guideline” by IDSA
https://www.idsociety.org/practice-guideline/nontuberculous-mycobacterial-ntm-diseases/
5.おわりに
非結核性抗酸菌症は、生活環境の中に存在している菌の感染症であり、一般的な結核とは異なる抗酸菌によって引き起こされます。
咳や痰が主な症状で血痰が出る場合もありますが、無症状で経過するケースも少なくありません。
この病気は完治が難しく、長い治療期間が必要です。場合によっては、周囲のサポートも必要でしょう。
完全に感染を予防することは不可能ですが、日々の生活習慣や体調管理が感染予防のポイントです。
感染経路は日常の中にあるため水まわりや土壌の吸い込みなどを平常から気を付けておくとよいでしょう。
リスクが高い方は特に意識しておきましょう。
非結核性抗酸菌症は緊急性の高い病気ではないですが、放置すると重篤な呼吸器疾患を引き起こしたり、急激に悪化したりする可能性があります。
咳や痰が続いていたり健康診断で指摘されたりした場合には、早めに呼吸器内科を受診しましょう。



