中学生のお子さんが貧血かも?症状・原因と対策、受診の目安

お子さんに「ふらつき」や「疲れやすさ」などの体調不良が見られると、「もしかして貧血では?」と保護者として心配になりますよね。
思春期は身体が大きく成長する時期で、鉄分など必要な栄養も急増します。
そのため中学生は貧血になりやすい年代でもあり、特に女子では約1割が貧血状態だという報告もあります。
本記事では、中学生のお子さんを持つ保護者の方向けに、貧血の症状や原因、家庭でできる対策、そして受診の目安についてわかりやすく解説します。
お子さんの健康管理にぜひお役立てください。
1.中学生が貧血を起こす原因とは?

まず、中学生で起こりやすい貧血の原因を押さえておきましょう。
貧血の大半は鉄分の不足による鉄欠乏性貧血です。
思春期のお子さんが鉄分不足に陥りやすい主な理由には、次のようなものがあります。
1-1.成長期に伴う鉄分の必要量増加
思春期には急速に身体が成長し、血液量も増加するため、それに伴い鉄の必要量も増えます。
体格が大きくなる中学生では、食事からの鉄摂取が追いつかないと貧血を起こしやすくなります。
1-2.女子中学生に多い月経による鉄の喪失
女子は小学校高学年から中学生頃に初経を迎えますが、月経による定期的な出血は鉄分の損失につながります。
特に月経過多(経血の量が多い場合)では、失われる鉄分も多くなり貧血リスクが高まります。
1-3.無理なダイエットや朝食抜きに注意
食べ盛りの時期ですが、思春期の子ども、とりわけ女子は体型を気にして無理なダイエットをしたり、好き嫌いで食事が偏るケースもあります。
朝食抜きや極端な摂食は鉄分や他の栄養素の不足を招き、それが貧血を助長する一因となります。
実際、思春期の女子ではダイエット志向の高まりも貧血有病率を上げる要因とされています。
1-4.スポーツ貧血と運動の関係
男子・女子問わず、運動部などでハードな練習をしている場合も注意が必要です。
汗や尿とともに微量の鉄が失われたり、足裏への強い衝撃で赤血球が壊れる「スポーツ貧血」と呼ばれる現象が起こることがあります。
これは陸上の長距離走やサッカーなど激しい運動をする子にみられ、古くは長時間行軍する兵士にも起きたことから「行軍貧血」とも呼ばれました。
運動自体は健康に良いものですが、過度な練習で疲労が蓄積し栄養補給が追いつかないと貧血リスクが高まる点は押さえておきましょう。
【参考情報】『スポーツ貧血の仕組み』日本医師会 学校保健ポータルサイト
https://www.gakkohoken.jp/special/archives/214
部活動で息切れが続く場合は、貧血だけでなく運動誘発性喘息(別名アスリート喘息)の可能性もあります。症状が長く続く場合には、呼吸器内科を受診してみるのがおすすめです。
以上のように、中学生年代で貧血になる背景には急激な成長による鉄需要の高まりや月経・食生活・運動習慣など様々な要因があります。
特に女子中学生は思春期に入ると鉄分不足に陥りやすいため、日頃の食事内容や体調の変化に保護者の目配りが必要です。
一方、男子でも成長期に加え部活動などで活発に体を動かす子は貧血が起こり得ます。
お子さんの性別を問わず、「食事は足りているか」「疲れがたまっていないか」といった点に注意してあげましょう。
【参考文献】”Prevention of iron deficiency anaemia in adolescents” by World Health Organization (WHO)
https://iris.who.int/handle/10665/205656
【参考文献】”Recommendations to Prevent and Control Iron Deficiency in the United States” by Centers for Disease Control and Prevention
https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00051880.htm
2.貧血の主な症状とサイン

お子さんに貧血の疑いがある場合、具体的にどんな症状やサインが見られるのでしょうか。貧血になると体の酸素が不足するため、以下のような症状が現れます。
・疲れやすく元気がない(全身の倦怠感)
・立ちくらみやめまい(急に立ち上がったときにフラッとする)
・顔色が青白い(特にまぶたの裏の結膜が白っぽい)
・動悸・息切れ(軽い運動でもドキドキしたり息苦しくなる)
・頭痛や耳鳴り
・集中力の低下やイライラしやすくなる(ぼんやりしたり機嫌が不安定になる)
・爪が反り返る(スプーンのように中央が凹む匙状爪という状態)※重度の場合
こうした症状が複数みられる場合、貧血の可能性があります。
特にまぶたの裏が白い、「爪の変形(匙状爪)」などは典型的な鉄欠乏のサインです。
貧血になると全身に酸素を届けようと心拍数が上がるため脈が速くなり、顔色が蒼白になることも知られています。
【参考情報】”Anaemia in Children and Teens: Parent FAQs” by HealthyChildren.org
https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/chronic/Pages/Anemia-and-Your-Child.aspx
2-1.似た症状を持つ別の疾患にも注意
極度の緊張や不安が原因で過換気症候群(過呼吸)を起こした場合にも、めまいや息切れ、動悸といった症状が現れることがあります。
貧血とは異なるメカニズムですが、思春期のお子さんにも起こりうるため注意が必要です。
息切れ・呼吸困難感は貧血以外にも起こります。
呼吸器疾患など他の原因について知りたい方は、呼吸器内科などの専門の病院で検査をすることをおすすめします。
なお、貧血症状はゆっくり進行すると自覚しにくいこともあります。
お子さん自身があまり訴えなくても、「最近疲れやすそう」「顔色が悪い」と感じたら注意してあげてください。
学校生活では見逃されがちなケースもありますので、保護者の方が日頃の様子からサインを見つけてあげることが大切です。
【参考文献】”Iron-Deficiency Anemia in Children” by Children’s Hospital of Philadelphia
https://www.chop.edu/conditions-diseases/iron-deficiency-anemia-in-children
3.中学生の貧血対策:家庭でできる鉄分の摂り方と生活改善

思春期の貧血対策には、まず日々の食事や生活習慣を見直すことが基本です。
ここでは保護者がお子さんのために実践しやすいポイントを紹介します。
3-1.規則正しい食事が貧血予防の第一歩
食事は朝昼夕の3食を規則正しく摂り、欠食や極端な偏食・ダイエットを避けましょう。
特に朝食抜きは成長期の貧血リスクを高めます。
インスタント食品やジャンクフードばかりでは鉄分が不足しがちなので注意が必要です。
3-2.鉄分を多く含む食材と調理の工夫
貧血予防・改善には何と言っても鉄分補給が重要です。
鉄分が豊富な食材としては、レバー(鶏・豚・牛)や赤身の肉、カツオ・マグロなど赤身の魚、イワシやサバ、アサリやシジミなどの貝類、ほうれん草や小松菜などの青菜、ひじきなどの海藻類、大豆製品や豆類などが挙げられます。
調理の際に鉄鍋や鉄のフライパンを使うと、調理中に鉄分が食品に溶け出して微量ながら摂取量を増やせるとも言われます。
また、赤血球の材料となる良質なたんぱく質(魚・肉・卵・大豆製品など)もしっかり摂らせましょう。
食品中の鉄には、肉や魚介に含まれるヘム鉄(吸収率が高い)と、野菜や穀物などに含まれる非ヘム鉄(吸収率は低い)の2種類があります。
動物性食品の鉄(ヘム鉄)は体に吸収されやすいため、貧血対策には肉や魚を適量取り入れることが有効です。
一方、ほうれん草など植物性食品の鉄(非ヘム鉄)は吸収されにくいですが、ビタミンCや動物性たんぱく質と一緒に摂ると吸収率が高まることが知られています。
例えば、食事で野菜や海藻から鉄を摂る場合は、果物や野菜のビタミンC豊富なものを組み合わせたり、肉や魚と一緒に調理する工夫をしましょう。
日々の献立に鉄分の多い食品をできるだけ取り入れることが、貧血に負けない体づくりにつながります。
3-3.ビタミンB12・葉酸など造血を助ける栄養素
鉄だけでなく、ビタミンB12や葉酸など赤血球の生成に必要なビタミン類もしっかり摂取しましょう。
これらは普通の食事をしていれば不足しにくい栄養素ですが、偏食をしないよう注意が必要です。
レバー類や魚介、卵黄、緑黄色野菜、大豆製品などをバランス良く食べることで補給できます。
またタンパク質も赤血球の主成分ですから、毎食主菜(肉・魚・豆腐・卵など)を欠かさないようにしましょう。
3-4.鉄の吸収を妨げる飲み物に注意
緑茶や紅茶、コーヒーに含まれるタンニンは鉄の吸収を妨げます。
せっかく鉄分を含む食事をしても、食事中や直後に渋いお茶やコーヒーばかり飲んでいると吸収率が下がってしまいます。
食事中の飲み物は水や麦茶(カフェインレス)などにするか、少なくとも食後30分~1時間はお茶・コーヒーを控えると良いでしょう。
3-5.運動と休息のバランスが大切
部活動などで激しい運動をしている場合、練習の強度や頻度を見直すことも必要です。
運動は大切ですが、過度なトレーニングは貧血を悪化させる可能性があります(溶血性の貧血や鉄消耗)。
お子さんが「疲れが取れない」「立ちくらみがひどい」と訴えるときは、練習量を一時的に減らしたり休養日を増やすことも検討してください。
運動後は特に鉄分を含む食事と十分な水分補給を心がけましょう。
栄養不足は免疫力の低下を招き、風邪などの感染症にもかかりやすくなることがあります。
日頃の体調管理をしっかりとすることが、自分自身の体調を整えることにつながります。
上記のような対策を続けることで、思春期のお子さんの貧血予防・改善に効果期待できます。
ただし、食事療法だけでは重度の貧血を速やかに改善することは難しい場合も多いという点は押さえておきましょう。
鉄欠乏性貧血と診断された場合、医療機関では「鉄剤(鉄分の内服薬)」が処方されることが一般的です。
医師の指示に従い薬を服用しつつ、根本的な改善と再発防止のためには上記のような食事・生活習慣の改善を根気強く続けることが大切です。
また、日々の食生活の改善に不安がある場合は、栄養カウンセリングで管理栄養士に相談することもできます。
お子さんに合わせた食事の工夫や鉄分補給のポイントなど、プロの視点からアドバイスいたします。
当院でも行っていますので、興味のある方はお問い合わせください。
【参考文献】”Clinical Practice Guidelines: Iron deficiency” by Royal Children’s Hospital (Australia)
https://www.rch.org.au/clinicalguide/guideline_index/iron_deficiency/
【参考文献】”Iron ‑ Health Professional Fact Sheet” by NIH Office of Dietary Supplements
https://ods.od.nih.gov/factsheets/Iron-HealthProfessional/
4.病院を受診する目安とタイミング
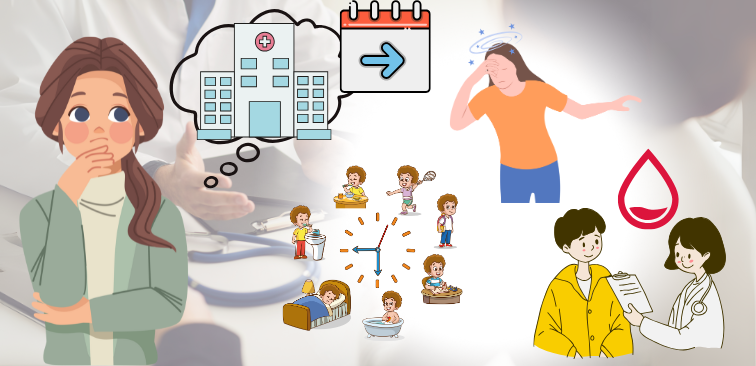
貧血が疑われる場合、適切なタイミングで医療機関を受診することも重要です。
では、保護者としてどのような状況になったら病院に連れて行くべきでしょうか。
4-1.日常生活への影響が見えるときは要注意
お子さんが「朝起きられないほどだるい」「体育の後にめまいで倒れそうになる」「部活で記録が急に伸びなくなった」「勉強中に集中できず眠気が強い」など、生活や学業・スポーツに影響が出ている場合は受診を検討しましょう。
貧血になると集中力や持久力の低下を招き、学業成績や運動パフォーマンスにも影響し得ます。
明らかに体調不良が続くようなら一度検査を受けることをおすすめします。
4-2. 失神や強いめまいを経験したとき
立ちくらみが頻繁に起きる、階段で貧血を起こして座り込んでしまった、意識が飛ぶような失神をした、といった重い症状が一度でもあれば早めに医療機関へ連れて行ってください。
とくに体育祭の練習中や通学中などに倒れて怪我をする危険もありますし、重篤な貧血や他の疾患が隠れている可能性もあります。
4-3.健診や検査で貧血を指摘されたら確認を
学校の健康診断でヘモグロビン値の低下を指摘された場合や、部活のために受けた血液検査で貧血気味と言われた場合も、念のため専門医の診断を受けると安心です。
学校健診では貧血のチェックが省略されることも多いですが、健診がない場合でも保護者の判断で検査を受けに行って構いません。
貧血は血液検査で簡単にわかり、検査自体も採血だけですぐ終わります。
4-4. 重い月経やその他の気になる症状があるとき
中学生の女子で、生理の出血量が非常に多かったり、生理期間が長引いている場合も貧血を疑いましょう。
月経過多による貧血は放置すると将来的な健康にも影響します。
また、食欲不振や体重減少、腹痛など貧血以外の症状が併発している場合は、消化器系の病気など他の原因が隠れていることもあるため医師に相談してください。
以上のようなケースでは、小児科や内科(必要なら婦人科)を受診して医師の判断を仰ぐことをおすすめします。
「たかが貧血」と軽くみないで、必ず医師の診断を受けて原因を調べるようにしてください。
貧血そのものは鉄剤の内服などで改善しますが、その背景に潜む要因(例:過度の月経、消化管からの出血、栄養不足の原因など)を突き止めて対処することが再発予防につながります。
お子さんの貧血が改善し元気になることで、日々の学校生活や部活動も今まで以上に充実してくるでしょう。
保護者の皆さんも、ぜひ本記事の情報を参考にしながら、お子さんの健康管理に役立ててくださいね。
【参考文献】”What Are the Causes of Anemia in Adolescence?” by iCliniq
https://www.icliniq.com/articles/blood-health/anemia-in-adolescence
【参考文献】”Iron‑Deficiency Anemia” by National Heart, Lung, and Blood Institute
https://www.nhlbi.nih.gov/health/anemia/iron-deficiency-anemia
5.まとめ
思春期の中学生は、急激な成長や月経、運動、食生活の影響で貧血になりやすい時期です。
日頃のふらつきや疲れやすさといった小さなサインを見逃さず、鉄分を意識した食事や生活習慣の見直しで予防・改善が可能です。
生活への支障が出る場合や、学校健診で指摘された際は、早めの医療機関受診をおすすめします。
お子さんの元気を守るために、この記事を日々の健康管理の参考にお役立てください。



