長く続く咳や血痰の原因は「肺MAC症」かも?

この記事では、近年注目されている肺の病気「肺MAC症」についてご説明いたします。
肺MAC症は、Mycobacterium avium complex(MAC菌)という非結核性抗酸菌による慢性感染症です。
MAC菌は土壌や水回りなど自然環境に広く存在し、人から人へ感染することはありません。
肺MAC症について正しい知識を持ち、早期診断と適切な治療を受けることで症状をコントロールしながら生活することが可能です。
長引く咳や血痰などの症状がある場合は、肺MAC症も可能性も考え、早めに呼吸器内科を受診しましょう。
1. 肺MAC症とは

肺MAC症は、Mycobacterium avium complex(マイコバクテリウム・アビウム・コンプレックス)という菌による慢性の肺感染症です。
非結核性抗酸菌症の一種で、日本では肺非結核性抗酸菌症の約9割を占める重要な疾患です。
MAC菌は土壌や水回りなど、私たちの身近な環境に広く存在しています。
そのため、どなたでも日常生活のなかでMAC菌に接触する可能性があります。
肺MAC症の特徴として、治療に長期間を要し、再発のリスクが高いことが挙げられます。
完全に治癒することは難しく、多くの場合、慢性的な病気として管理していく必要があります。
このため、早期発見と適切な治療が非常に重要です。
症状が軽い段階で発見できれば、より効果的な治療が可能になる場合があります。
肺MAC症は、年々患者さんの数が増加傾向にあり、とくに中高年の女性に多く見られます。
その理由として、高齢化社会の進行や診断技術の向上、環境因子の変化などが考えられています。
また、肺MAC症はほかの呼吸器疾患と併存することも多く、例えば気管支拡張症や慢性閉塞性肺疾患(COPD)を持つ方に発症しやすい傾向があります。
このような疾患がある方は、とくに注意が必要です。
肺MAC症は潜在的患者さんが非常に多いとされています。
無症状でも罹病している方も多いため、特に後発年齢である40代以降女性に関しては定期的な画像検診が必要になります。
診断されたら全員治療介入ではありませんが専門医の定期的な評価が望ましいです。
【参考文献】”MAC Lung Disease” by American Lung Association
https://www.lung.org/lung-health-diseases/lung-disease-lookup/mac-lung-disease
2. 肺MAC症の原因

肺MAC症の主な原因は、MAC菌を吸い込むことです。
MAC菌は、先ほど述べたように環境中に広く存在しています。
具体的には、以下のような場所に多く存在します。
・土壌
・水道水
・ほこり
・鳥の糞
・浴室やシャワーヘッド
・エアコンのフィルター
これらから空気中に浮遊したMAC菌を吸い込むことで、感染の可能性が出てきます。
ただし、重要なポイントとして、MAC菌は病気を引き起こす能力が比較的低い菌であるということです。
つまり、MAC菌を吸い込んだからといって、必ずしも全ての方が肺MAC症を発症するわけではありません。
健康な方の場合、免疫システムがMAC菌の増殖を抑制することができます。
しかし、以下のような要因がある方は、感染のリスクが高くなる傾向があります。
・高齢の方
・慢性的な肺疾患(慢性閉塞性肺疾患や気管支拡張症など)をお持ちの方
・免疫機能が低下している方(HIV感染症の方や免疫抑制剤を使用している方など)
・喫煙者の方
・やせ型の方(とくに中高年の女性)
・胃食道逆流症(GERD)の方
・遺伝的要因がある方
また、中年以降の女性に多いことも特徴のひとつです。
その理由として、女性ホルモンの影響ややせ型の体型、胸郭の形状などが関係していると考えられていますが、詳細な仕組みはまだ完全には解明されていません。
一方で、長期間にわたる菌の吸入が、発症のきっかけとなりやすいとされています。
そのため、日常生活における予防も重要になります。
例えば、浴室の換気を十分に行う、エアコンのフィルターを定期的に清掃する、ペットの糞尿の処理を適切に行うなどの対策が有効です。
◆「アレルギー症状の引き金となるカビ、掃除で注意すべきポイント」とは>>
【参考文献】”MAC Lung Disease” by Cleveland Clinic
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/22256-mac-lung-disease
3. 肺MAC症の症状

肺MAC症の症状は、一般的な呼吸器疾患と似ています。
主な症状には以下のようなものがあります。
・長引く咳(3週間以上続く乾いた咳)
・痰(たん)が多い
・血痰(血液の混じった痰)
・息切れや呼吸困難
・胸の痛みや圧迫感
・全身のだるさや疲労感
・体重減少
・微熱(37度前後の熱が続く)
・寝汗(夜中に汗をかく)
これらの症状は、肺MAC症に特有のものではありません。
そのため、これらの症状があるからといって、必ずしも肺MAC症であるとは限りません。
肺MAC症の大きな特徴として、長い年月をかけてゆっくりと進行することが挙げられます。
多くの場合、10年以上かけて徐々に症状が進行していきます。
ゆっくりとした進行のため、病気に気づかない方も多いのが現状です。
初期段階では症状がほとんどない、あるいは軽微な場合もあります。
そのため、健康診断や人間ドックの胸部レントゲン検査で偶然発見されることもあります。
また、咳や痰といった症状が長期間続いているにもかかわらず、風邪や気管支炎と勘違いして放置してしまうケースも少なくありません。
症状の進行度合いは個人差が大きく、ゆっくりと進行する場合もあれば、比較的急速に悪化する場合もあります。
一般的に、以下のような経過をたどることが多いです。
1. 初期段階
軽い咳や少量の痰が出る程度で、日常生活にはほとんど支障がありません。この段階で発見されることは少なく、多くの場合は次の段階まで進行してから診断されます。
2. 中期段階
咳や痰の症状が徐々に強くなり、息切れを感じるようになります。
体重減少や微熱、疲労感なども現れることがあります。この段階で医療機関を受診する方が多いです。
3. 進行期
症状がさらに悪化し、日常生活に支障をきたすようになります。
呼吸困難が顕著になり、血痰が出ることも増えます。
この段階では、肺の機能低下が進んでいることが多いです。
そのため、以下のような症状が1ヶ月以上続く場合は、肺MAC症の可能性も考えて、呼吸器内科への受診を検討しましょう。
・咳が止まらない
・痰が多い
・血痰が出る
・息切れがする
・体重が減少する
・原因不明の微熱が続く
早期発見・早期治療が悪化させないための重要なポイントです。
ご自身の体調の変化に敏感になり、気になる症状があれば躊躇せずに医療機関を受診しましょう。
◆「血痰が出る原因は?心配な病気と呼吸器内科を受診する目安」>>
【参考文献】”Mycobacterium avium Complex” by National Institutes of Health
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK431110/
4. 検査

肺MAC症の診断には、さまざまな検査が必要となります。
なぜなら、肺MAC症の症状はほかの呼吸器疾患と似ているためです。
例えば、長引く咳や痰は、慢性気管支炎や気管支拡張症でも見られる症状です。
そのため、複数の検査を組み合わせて総合的に判断する必要があります。
主な検査方法には以下のようなものがあります。
・画像検査
胸部レントゲンや胸部CT検査を行います。
これらの検査で、肺の中の異常な影を確認します。
肺MAC症特有の陰影パターンを見つけることが診断の手がかりとなります。
肺MAC症の典型的な画像所見として、以下のようなものがあります。
・小結節影(小さな粒状の影)
・気管支拡張像
・浸潤影(すりガラス状の影)
・空洞影
これらの所見が、とくに右中葉や左舌区(左肺の一部)に見られることが多いのが特徴です。
・喀痰検査
患者さんに痰を出してもらい、その中にMAC菌がいないかを調べます。
この検査では、顕微鏡で直接菌を観察する方法(塗抹検査)と、培養して菌を増やす方法(培養検査)があります。
塗抹検査は結果が早く出ますが、感度が低いため、陰性でも菌がいないとは言い切れません。
培養検査はより正確ですが、結果が出るまでに6〜8週間かかることがあります。
・血液検査
血液中の抗MAC抗体を調べる検査があります。
血液検査は診断の補助として用いられます。
また、炎症反応(CRPやESRなど)や栄養状態、肝機能や腎機能なども確認します。
・気管支鏡検査
喀痰検査で菌が見つからない場合や、より詳細な検査が必要な場合に行われます。
気管支の中に細い管を入れて、直接検体を採取します。
局所麻酔を行いますが、多少の不快感を伴う検査です。
・肺機能検査
肺の機能(呼吸機能)を調べる検査です。
肺活量や1秒量などを測定し、肺の状態を評価します。
これらの検査を総合的に判断して、肺MAC症の診断を行います。
なお、MAC菌は環境中にも存在するため、1回の検査で菌が検出されただけでは診断確定とはなりません。
アメリカ胸部疾患学会(ATS)と日本結核病学会の診断基準では、以下の条件を満たす場合に肺MAC症と診断されます。
・画像所見:胸部X線写真または胸部CTで結節性陰影や小結節性陰影、または空洞性陰影を認める
・細菌学的所見:複数回の喀痰検査でMAC菌が検出される、または気管支洗浄液でMAC菌が検出される
・ほかの疾患の除外:ほかの肺疾患(肺結核など)が除外される
これらの条件を満たすことで、肺MAC症の診断が確定します。
ただし、症状や画像所見が典型的でない場合もあるため、最終的な診断は経験豊富な呼吸器専門医が総合的に判断します。
肺MAC症は潜在的患者さんが非常に多いとされています。
無症状でも罹病している方も多いため、特に後発年齢である40代以降女性に関しては定期的な画像検診が必要になります。
診断されたら全員治療介入ではありませんが専門医の定期的な評価が望ましいです。
次の章では、肺MAC症の治療方法についてご説明しましょう。
◆「呼吸器内科で行われる検査とは?専門的な検査を紹介します」>>
【参照文献】日本内科学会雑誌『成人肺非結核性抗酸菌症化学療法に関する見解』
https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/100/4/100_1058/_pdf
【参考文献】”MAC lung disease marked by cough and fatigue” by UCLA Health
https://www.uclahealth.org/news/article/mac-lung-disease-marked-cough-and-fatigue
5. 治療方法
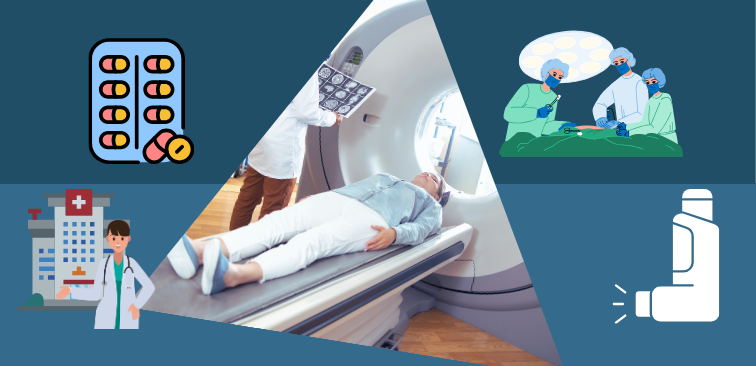
肺MAC症の治療方法は、患者さんの症状や病状によって異なります。主な治療方法として、以下の4つがあります。
5-1. 経過観察
症状がない、あるいは軽微な場合は、すぐに治療を開始せず、経過観察を行うことがあります。
これは、肺MAC症がゆっくりと進行する病気であり、場合によっては自然に軽快することもあるためです。
また、治療に使用する抗菌薬には副作用のリスクもあるため、症状が軽い段階では治療によるメリットよりもデメリットの方が大きくなる可能性があります。
経過観察中は、定期的に胸部レントゲンやCT検査を行い、病状の進行がないかを確認します。
咳や痰などの症状が悪化していないか観察し、3〜6ヶ月ごとの受診が一般的です。
経過観察中であっても、以下のような変化がある場合は、治療の開始を検討することがあります。
・症状(咳、痰、血痰など)が悪化した場合
・画像検査で病変の拡大が認められた場合
・喀痰検査で菌の量が増加した場合
5-2. 抗菌薬を複数・長期間服用する
症状がある場合や、病状の進行が認められる場合は、抗菌薬による治療を開始します。
肺MAC症の標準的な治療は、複数の抗菌薬を組み合わせて長期間服用する方法です。
一般的に使用される薬剤の組み合わせは以下の通りです。
・クラリスロマイシンまたはアジスロマイシン
・エタンブトール
・リファンピシン
これらの薬を毎日、または週3回服用する治療法が推奨されています。
治療期間は通常2年以上に及び、菌が培養検査で検出されなくなってからさらに1年間は治療を継続する必要があります。
治療では、薬の服用を指示通りに続けることが非常に重要です。
なぜなら、服薬を中断したり、不規則になったりすると、薬が効きにくくなる(薬剤耐性)可能性があるからです。
薬剤耐性が起こると、それまで効いていた薬が効かなくなり、治療がより困難になってしまいます。
そのため、たとえ症状が改善しても、医師の指示なく自己判断で薬の服用を中止しないようにしましょう。
また、長期間の服薬が必要なため副作用の管理も重要です。
主な副作用として以下のようなものがあります。
・胃腸障害(吐き気や下痢など)
・肝機能障害(倦怠感や黄疸など)
・視力障害(エタンブトールによる視神経への影響)
・皮膚症状(発疹やかゆみなど)
これらの副作用を早期に発見し対応するために、定期的な血液検査や眼科検査が必要です。
5-3. 吸入薬の使用
抗菌薬の内服で十分な効果が得られない場合や、副作用によって内服薬を使用できない場合には、吸入薬による治療が選択されることがあります。
主に使用される吸入薬は「アミカシン」という抗菌薬です。
アミカシンを霧状にして吸入することで、直接肺へ届けることができます。吸入療法には以下のようなメリットがあります。
・肺に直接高濃度の薬剤を届けられる
・全身への副作用が比較的少ない
・内服薬と併用することで治療効果を高められる可能性がある
ただし、吸入を正しく行わないと十分な効果が得られないため、医師や看護師から正しい吸入方法について指導を受ける必要があります。
また、副作用として声枯れや気道刺激感などが現れることがあります。
さらに、ご自宅で吸入治療を継続する必要があるため、患者さんご自身やご家族の協力も必要です。
吸入器具の清掃や管理も欠かせないため、器具の管理についても医療スタッフから説明を受けましょう。
5-4. 手術の検討
肺MAC症では、一部の患者さんにおいて手術による治療が検討されることがあります。
ただし、手術はあくまで補助的な治療法であり多くの場合は抗菌薬治療との併用となります。
手術が考慮されるケースとしては以下の場合があります。
・病変が肺の一部にある場合
・抗菌薬治療で十分な効果が得られない場合
・繰り返す喀血(血痰)がある場合
・気胸(肺に穴が開く状態)などの合併症がある場合
手術では病変部位を切除することで菌量を減らし、その後の抗菌薬治療の効果を高めることを目的とします。
また、大量喀血や気胸といった緊急性の高い合併症への対処としても行われます。
ただし、手術には全身麻酔や術後合併症など一定のリスクがあります。
そのため、患者さんの全身状態や病変範囲、残存肺機能などを慎重に評価した上で適応かどうか判断されます。
手術後も抗菌薬治療は継続されます。
これは目に見えない小さな病変部分が残存している可能性があるためです。
手術をご提案された場合には、メリットとデメリットについて医師と十分に話し合い、ご自身で納得した上で決定することが大切です。
【参考文献】”About MAC” by The University of Texas at Tyler
https://www.uclahealth.org/news/article/mac-lung-disease-marked-cough-and-fatigue
6. おわりに
肺MAC症は慢性疾患ですが、正しい知識と適切な対策で良好な生活を送ることができます。
長引く咳や痰、血痰などの症状がある場合は早めに呼吸器内科を受診しましょう。
早期発見・早期治療が重要です。
診断後は、定期的な受診と検査を継続しましょう。
また、健康的な生活習慣や禁煙など、ご自身でできる努力も大切です。
肺MAC症は長期的な管理が必要な病気ですが、適切な治療と生活管理によって症状をコントロールすることが可能です。
ご不安や心配なことがあれば遠慮なく担当医に相談しましょう。
また、同じ病気を持つ方との情報交換も有益です。
患者会などに参加することで、日常生活での工夫や心理的なサポートを得られることもあります。
お一人で抱え込まず、周囲のサポートを活用しながら前向きに病気と向き合っていきましょう。



