階段で息切れは年齢のせいではない?隠れた呼吸器疾患に注意

最近、階段を上っただけで息が切れる、少し動いただけですぐに疲れてしまう、そんな悩みを「年齢のせい」や「運動不足だから」と片付けていませんか?
実は、その息切れや疲れやすさは呼吸器疾患の初期症状かもしれません。
この記事では、見過ごされがちな呼吸器のサインと主な原因疾患、受診の目安について解説します。
早めに対処すれば、将来の重症化を防ぐことができます。
1. 「年齢のせい」と見過ごしがちな息切れ・疲れやすさ

息切れや疲労感といった症状は、中高年になると誰にでも起こりうるため、「歳だから仕方ない」と思い込んで放置しがちです。
しかし、呼吸器の病気はゆっくり進行するものが多く、初期には自覚症状がほとんどありません。
症状が出ても「年齢的な衰え」「運動不足のせい」と判断して受診を先延ばしにしてしまう人が多く、気づかないうちに病気が悪化しているケースも少なくありません。
例えば、同年代と比べて明らかに階段を上るペースが遅くなったり、軽い家事や散歩でも息切れしてしまう場合、単なる体力不足ではなく呼吸器の疾患が潜んでいる可能性があります。
事実、日本では40歳以上の約8.6%(約530万人)がCOPD(慢性閉塞性肺疾患)を患っていると推計されていますが、その大半が未診断・未治療のままだと報告されています。
こうした疾患は早期発見・治療で進行を抑えられるため、「歳のせい」と決めつけず、症状が続くときは注意が必要です。
また、1週間程度で治るはずの風邪の症状(咳や鼻水など)がなかなか治らず、2週間以上続いている場合は呼吸器疾患の可能性が高いです。
「年齢のせいで長引いている」と思わず早めに専門医に相談しましょう。
【参考情報】『慢性閉塞性肺疾患(COPD)』日本呼吸器学会
https://www.jrs.or.jp/citizen/disease/b/b-01.html
【参考情報】”Breathing Problems | Shortness of Breath” by U.S. National Library of Medicine
https://medlineplus.gov/breathingproblems.html
2. 息切れ・疲れやすさの原因 – 加齢変化との違いとは?

なぜ肺の病気になると息切れや倦怠感が起こるのでしょうか?
呼吸によって私たちの肺は酸素を取り込み、身体に供給しています。
呼吸器に異常があると十分な酸素を取り込めなくなり、全身がエネルギー不足の状態に陥ります。
その結果、階段を上ったり少し体を動かしただけで息が切れたり、疲れやすく感じたりするのです。
加齢や運動不足による息切れは、筋力や心肺機能の低下が原因であり、トレーニングである程度改善できる場合があります。
これに対して、COPDや肺の線維化など病的な原因がある場合、努力では改善せず徐々に悪化していくのが特徴です。
特に喫煙習慣のある方は注意が必要です。
タバコに含まれる有害物質は長年にわたり肺を傷つけ、気道を慢性的に炎症させます。
その結果、咳や息苦しさが生じるだけでなく、肺の働きそのものが低下してしまいます。
喫煙者の15~20%がCOPDを発症するとも言われており、喫煙歴の長い中高年ほど息切れ症状には注意が必要です。
さらに、大気汚染や粉じんなどの環境要因も呼吸器にダメージを与え、徐々に呼吸機能を低下させることがあります。
例えば化学物質を扱う職場などで長年働いていた方などは、非喫煙者でも肺が弱っている可能性があります。
こうした生活習慣や環境因子による息切れは、残念ながら歳のせいではなく肺からのSOSと考えてください。
普段から喫煙している方で「最近咳が増えた」「動くと息切れする」という場合は、以下の記事も参考にしてみてください。
【参考情報】『COPD(慢性閉塞性肺疾患)』厚生労働省
https://kennet.mhlw.go.jp/slp/event/disease/copd/index
【参考情報】”Health Effects of Cigarettes: Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)” by Centers for Disease Control and Prevention
https://www.cdc.gov/tobacco/about/cigarettes-and-copd.html
3. 息切れ・倦怠感を引き起こす主な呼吸器の病気
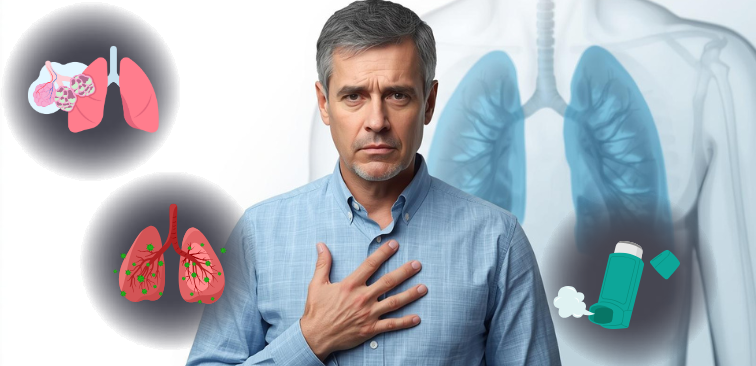
「息切れが続く」「すぐ疲れる」といった症状の背景には、呼吸器内科で扱うさまざまな病気が隠れている可能性があります。
ここでは代表的な2つの病気について、その特徴と初期症状を紹介します。
3-1. COPD(慢性閉塞性肺疾患)
COPD(シーオーピーディー)は、長年の喫煙や大気汚染などにより気管支や肺がダメージを受け、空気の通り道が狭くなる病気です。
以前は「肺気腫」や「慢性気管支炎」と呼ばれていた疾患を総称する名称で、まさに「肺の生活習慣病」ともいわれます。
主な原因はタバコで、患者さんの90%以上が喫煙歴を持っています。
COPDの初期症状として多いのが、階段や坂道で息切れを感じることです。
また、朝方に長引く咳や大量の痰が出るのも典型的な症状と言われます。
ところが症状はゆっくり進行するため、本人は「年齢のせいかな」と思ってしまいがちです。
実際、COPDは中高年の喫煙者に多い病気ですが、初期には「年齢」や「運動不足」のせいと誤解され、放置されるケースも少なくありません。
しかし放置すると、症状がだんだんと悪化して少し動いただけでも息苦しくなり、重症化すると在宅酸素療法(自宅での酸素吸入)が必要になることもあります。
日本では40歳以上のCOPD患者数は約530万人にのぼると推定され、その多くがまだ診断を受けていない状況です。
COPDは進行すると呼吸不全を招き、心不全や肺癌など他の病気のリスクも高まります。
しかし禁煙や吸入薬で進行を遅らせ、症状を緩和することが可能です。
早期に治療を始めれば、同年代の健康な人と変わらない生活を送ることも十分期待できます。
「ただの喫煙習慣による咳や息切れ」と侮らず、思い当たる方は早めに検査を受けることが大切です。
【参考情報】『COPDと心不全 併存に対する診断と治療 診断編』Boehringer-ingelheim
https://pro.boehringer-ingelheim.com/jp/product/spiolto/diagnosis-treatment-of-copd-and-hf-diagnosis
【参考情報】『ぜん息などの情報館)』環境再生保全機構
https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/copd/about/03.html
【参考情報】”About COPD” by Centers for Disease Control and Prevention
https://www.cdc.gov/copd/about/index.html
3-2. 間質性肺炎
間質性肺炎とは、肺組織のひとつである「間質」に炎症が生じ、肺が固くなってしまうことで呼吸がしづらくなる病気の総称です。
間質性肺炎の中で原因がはっきりしないものは特発性間質性肺炎と呼ばれ、中でも特発性肺線維症は肺の組織が徐々に線維化(硬くなること)していく病気で、慢性化すると5年間の生存率が低い重篤な病気です。
一方で原因がはっきりしている間質性肺炎は、原因によって自己免疫性間質性肺炎(膠原病に伴う肺炎など)や、職業環境性間質性肺炎(じん肺など)、医原性間質性肺炎(薬剤性肺炎など)に分類されます。
間質性肺炎は、乾いた咳(痰を伴わない咳)が続くのも特徴です。
初期の間質性肺炎は無症状のことが多く、健康診断の胸部レントゲンやCT検査で偶然見つかるケースもあります。
「最近息切れしやすいけれど、年だから体力が落ちただけ」と思っていたら、実は肺の線維化が進んでいた…ということも少なくありません。
特発性間質性肺炎は50歳以上の男性に多くみられ、患者さんのほとんどが喫煙者であることから、喫煙がリスク要因と考えられています。
喫煙歴があり階段での息苦しさを感じ始めた中高年の方は、この病気も念頭に置く必要があります。
間質性肺炎は様々な病気の総称のため、詳しい病名によって治療法は異なりますが、一部の感染症や薬剤を原因とした間質性肺炎を除く、ほとんどの間質性肺炎は現在の医療で治癒できません。
ただし、ステロイド薬や、免疫抑制薬、抗線維化薬などの治療で進行を遅らせることが可能です。
早期の受診によって日常生活への影響を最小限に抑えられます。
「ただの息切れ」と放置せず、早めに専門医を受診することが重要です。
【参考情報】『間質性肺炎』日本呼吸器学会
https://www.jrs.or.jp/citizen/disease/d/
【参考情報】”What Are Interstitial Lung Diseases?” by National Heart, Lung, and Blood Institute (NIH)
https://www.nhlbi.nih.gov/health/interstitial-lung-diseases
3-3.その他に考えられる呼吸器疾患
息切れやだるさを引き起こす呼吸器疾患としては他にも喘息があります。
喘息発作時にはゼーゼーという喘鳴(ぜんめい)や強い息苦しさを伴うのが一般的です。
喘息は、一見すると風邪などの症状と勘違いしてしまいますが、放置すると気管支の炎症が悪化し、症状が悪化する「気道のリモデリング」という状態になり、治療が難しくなってしまいます。
息切れやだるさの他にも、咳や痰が出るなどの症状があるときは、早めに受診しましょう。
【参考情報】”About Asthma” by Centers for Disease Control and Prevention
https://www.cdc.gov/asthma/about/index.html
4. 息切れは心臓病だけじゃない!呼吸器内科で検査すべき理由

息切れというと、「心臓に問題があるのでは?」と心配する方も多いでしょう。
確かに、心不全など心臓の病気でも息切れ症状は起こります。
しかし、呼吸困難は肺を原因とすることも多いです。
心臓と肺は体に酸素を送り届ける両輪のような存在で、どちらかの機能が低下すると息切れとして現れるのです。
では、心臓由来の息切れと肺由来の息切れに違いはあるのでしょうか?
一般的に、心臓の病気では動悸・胸の痛み・足のむくみなどを伴うことが多い一方、肺の病気では咳・痰・喘鳴など呼吸器症状を伴うケースが多いとされます。
ただし症状だけで原因を判断するのは難しく、専門的な検査が必要です。
例えば、息切れの原因がはっきりしない場合、呼吸器内科では胸部レントゲンや肺機能検査(スパイロメトリー)などを行い、肺の状態を詳しく調べます。
必要に応じて血液検査や心電図などで心臓の評価も行い、心疾患との鑑別をします。
「息切れ=循環器内科(心臓)」と思い込んでしまいがちですが、咳や喉の痛みなどの症状を伴う場合は呼吸器内科の受診が適切です。
呼吸器内科はその名の通り「呼吸」に関わる臓器や症状を専門に診療する科であり、咳や痰、息切れといった症状の原因究明に長けています。
実際、「最初は循環器を受診したが異常がなく、呼吸器の検査をしたら肺の病気が見つかった」というケースもあります。
息切れの原因が心臓か肺か判断がつかない場合も、呼吸器内科であれば肺の検査に加え必要に応じ心臓のチェックもしてもらえますので安心です。
【参考情報】『呼吸器Q&A Q11. 発作性もしくは突然呼吸が苦しくなります。』日本呼吸器学会
https://www.jrs.or.jp/citizen/faq/q11.html
【参考情報】『Shortness of breath』MAYO CLINIC
https://www.mayoclinic.org/symptoms/shortness-of-breath/basics/causes/sym-20050890
【参考情報】”About Heart Disease” by Centers for Disease Control and Prevention
https://www.cdc.gov/heart-disease/about/index.html
5. 息切れや倦怠感を感じたら…受診の目安と早期治療の重要性
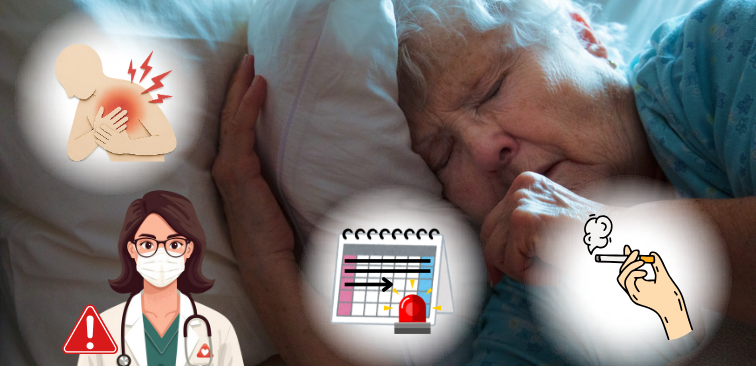
「まだ受診するほどではない」と先延ばしにしないでください。
息切れや倦怠感が続く場合、2週間以上改善しないなら一度医療機関で相談することをおすすめします。
特に、以下のような状況に当てはまる場合は呼吸器内科への受診を検討しましょう。
・突然息苦しさを感じたり、息切れが生じたりする。
・長引く咳や痰を伴っており、熱がないのに咳が2~3週間以上続いている。
・喫煙習慣がある・過去に長年喫煙していた。もしくは粉じんや有害物質にさらされる環境で働いていた。※こうした方は定期的な肺の検査も大切です。
早期に受診すれば、呼吸の異常を検査で確認できます。
例えば肺活量や1秒量を測るスパイロメトリー検査でCOPDの有無を調べたり、胸部画像で肺の影(線維化や腫瘍)を確認したりできます。
病気が見つかった場合も、早期の治療開始ができれば進行を食い止めたり症状を軽く保つことが可能です。
COPDも間質性肺炎も、治療せず放置すると取り返しのつかないダメージが蓄積してしまいますが、適切な管理を続ければ「息切れしにくい体」に維持することができます。
また、「息切れやだるさがあるけれど検査で何も出ない」と自己判断で安心してしまうのも禁物です。
症状が軽いうちに専門医が診れば、わずかな肺機能低下も見逃さず発見できる可能性があります。
息切れは放っておいて良いことはありませんので、気になるサインは早めに医師に相談しましょう。
【参考情報】『「肺年齢」対応のスパイロメトリー』厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/07/dl/s0713-2f.pdf
【参考情報】”Dyspnea – Causes, Symptoms, and Treatment Options” by U.S. National Library of Medicine
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499965/
6. おわりに
階段での息切れや慢性的な疲れやすさは、単なる年齢の問題ではなく呼吸器疾患の初期サインである可能性があります。
COPDと間質性肺炎ともに患者数が増えていると考えられており、より一層の注意が必要です。
早期に呼吸器内科で検査を受け、適切な治療を開始すれば、重症化を防いで日常生活の質を保つことが可能です。
「息切れ=心臓」と決めつけず、ぜひ呼吸器の専門医に相談してみてください。
息切れしない健やかな生活を取り戻すためにも、症状が軽いうちに受診しましょう。



