肺胞蛋白症とは?特徴や症状・診断・治療について解説
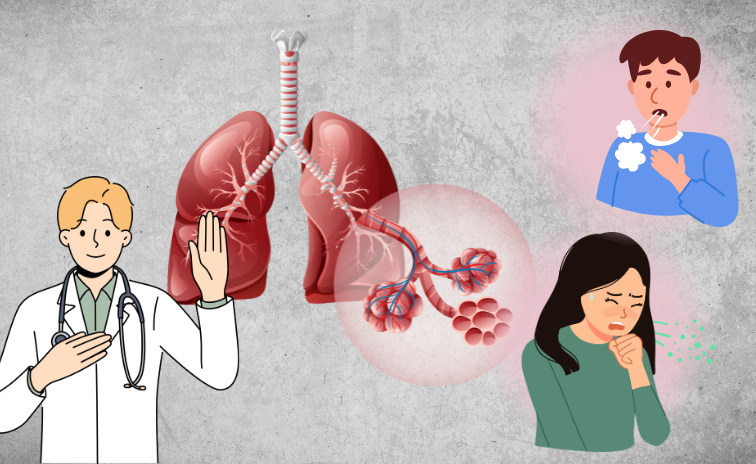
肺胞蛋白症(はいほうたんぱくしょう)は、「肺胞」(肺の奥にある小さな袋状の組織)に蛋白質様の物質(サーファクタント)が蓄積することで起こるまれな疾患です。
肺胞に物質が溜まると酸素と二酸化炭素の交換が妨げられ、息切れなどの呼吸症状を引き起こします。
本記事では、肺胞蛋白症の特徴や症状、診断方法、治療法について分かりやすく解説します。
1. 肺胞蛋白症の特徴

まず、肺胞蛋白症とはどのような病気なのか、その原因やタイプ(種類)など特徴について解説します。
1-1 自己免疫性肺胞蛋白症
肺胞蛋白症の約90%を占める最も多いタイプです。
体の免疫システムの誤作動により、肺胞マクロファージの働きに必要な物質「GM-CSF」に対する自己抗体が体内で作られてしまい、この抗体が肺の中でGM-CSFの働きを妨げます。
その結果、マクロファージが十分に機能せずサーファクタントが蓄積してしまうことで発症します。
現在このタイプが指定難病(番号229)として認定されています。
なぜ自己抗体ができるのかはまだ解明されていません。
1-2 続発性肺胞蛋白症
他の疾患や環境要因によって生じるタイプです。
例として白血病や骨髄異形成症候群などの血液疾患、膠原病、また長期間の粉じん曝露(職業上の粉塵吸入など)がきっかけで発症します。
このタイプでは抗GM-CSF抗体は検出されません。原因となる基礎疾患の治療や、粉じんなど環境因子の除去が重要です。
1-3 先天性・遺伝性肺胞蛋白症
極めてまれなタイプで、生まれつきの遺伝子異常によって起こります。
多くは新生児期や乳児期など小児で発症しますが、まれに成人での遺伝性発症例も報告されています。
家族内発症するケースもあり、根本的な治療法が確立していないことが多いです。
これらいずれのタイプでも共通するのは、肺胞にタンパク質様物質が溜まってガス交換が妨げられる点です。
また発症年齢は幅広く、小児から高齢者まで起こりえますが、報告の多い年齢層は30~50代です。
男女比はおよそ2:1で男性に多い傾向があります。
患者数は非常に少なく、国内では数百人程度(約10万人に1人以下)と推定されています。
男性患者が女性の約2倍とやや多い傾向も指摘されています。
【参考情報】『肺胞蛋白症(自己免疫性又は先天性)(指定難病229)』難病情報センター
http://nanbyou.or.jp/entry/4774
【参考情報】 “Pulmonary alveolar proteinosis: from classification to therapy” by European Respiratory Society
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7341616/?utm_source=chatgpt.com
2. 肺胞蛋白症の症状

肺胞蛋白症では初期には症状がほとんど現れず、多くの場合、進行とともに徐々に症状が出てきます。
実際、日本の調査では約30%の患者さんは自覚症状がなく、健康診断の胸部レントゲン検査で偶然見つかっています。
病変が広がっていても自覚症状が乏しいことがあり、「症状がないから大丈夫」とは言えない病気です。
2-1.進行に伴って現れる主な症状
病状が進行すると、主に次のような呼吸器症状が現れます。
息切れ(呼吸困難): 最も典型的な症状で、運動時や階段昇降時などに息苦しさを感じます。
全国調査では約40%の患者さんに労作時の呼吸困難がみられました。
置すると日常生活に支障をきたすほど悪化することがあります。
乾いた咳: 痰をほとんど伴わない乾いた咳が続くことがあります。
数週間以上続く慢性的な咳で発症するケースもあり、約10%の患者さんは咳のみが主症状でした。
白色の痰: 肺胞に溜まった物質が乳白色であるため、白い痰が出ることがあります。
ただし痰が出るケース自体まれで、調査では約2%に留まりました。痰に血が混じることは通常ありません。
全身の倦怠感: 進行すると酸素不足により体が疲れやすくなり、少し動いただけでも強いだるさを感じることがあります。
微熱・体重減少: あまり多くありませんが、微熱程度の発熱や原因不明の体重減少がみられる場合もあります。
このように肺胞蛋白症では、息切れや咳といった呼吸器症状が中心ですが、初期には症状が出ない場合も多い点に注意が必要です。
息苦しさを感じにくいまま低酸素状態が進んでしまうケースも報告されており、自覚症状だけで判断せず定期的な検査を受けることが大切です。
【参考情報】
“Pulmonary Alveolar Proteinosis – Symptoms, Causes, Treatment” by National Organization for Rare Disorders
https://rarediseases.org/rare-diseases/pulmonary-alveolar-proteinosis/?utm_source=chatgpt.com
3. 肺胞蛋白症の診断・検査

肺胞蛋白症の診断には、胸部画像検査や気管支鏡検査など複数の検査を組み合わせます。
他の肺疾患との鑑別も重要で、総合的な判断が必要です。
3-1 診察と問診
まず医師が症状の経過や既往歴、職業(粉じん曝露の有無)など詳しくお話を伺います。
同時に、聴診器で肺の音を確認し、呼吸状態を観察します。
肺胞蛋白症では診察で特徴的な音が聞こえない場合もありますが、全身状態の評価は重要です。
3-2 画像検査
肺の状態を確認するために胸部エックス線検査(レントゲン)や胸部CT検査を行います。
肺胞蛋白症では両方の肺にすりガラス状の陰影(白くぼんやりした影)が広がることが多くみられます。
特にCTでは、肺内にモヤがかかったような敷石状(しきいしじょう)陰影(舗装道路の敷石のようなまだら模様)が現れることが多く、この特徴的パターンは診断の重要な手がかりとなります。
3-3 血液検査
血液中の酸素濃度や炎症の有無を調べるほか、肺の病気で上昇しやすい肺サーファクタント関連蛋白(KL-6、SP-D、SP-Aなど)の値を測定します。
肺胞蛋白症ではこれらの値が高くなることがあり、特に自己免疫性タイプでは抗GM-CSF抗体という特殊な抗体が血液中や気管支洗浄液中から検出されることがあります。
3-4 気管支鏡検査(BAL)
細い気管支鏡で肺に生理食塩水を注入・吸引して洗浄する検査(気管支肺胞洗浄)です。
肺胞蛋白症では回収された洗浄液が白く濁った乳白色(米のとぎ汁様)になり、診断の決め手となります。
3-5 肺生検
BALでも確定しない場合などには、肺の組織を採取して調べる肺生検を行うこともあります。
顕微鏡で肺胞内に蛋白様物質の沈着が認められれば診断が確定します。
ただし侵襲が大きいため典型例では実施されません。
3-6 タイプの判別
肺胞蛋白症と診断された後は原因タイプの特定を行います。
検査で抗GM-CSF抗体が高濃度で検出されれば自己免疫性、抗体陰性で血液疾患の合併や粉じん曝露歴があれば続発性、どちらにも当てはまらない場合は遺伝子検査で先天性/遺伝性を疑います。
本症はまれで一般の医療機関では診断が難しいことがあります。
疑われる場合は呼吸器専門医のいる病院で詳しい検査を受けることが望ましいでしょう。
また指定難病に定められており、重症度が基準(管理区分III以上)を満たせば医療費助成の対象になります。
専門医の指導のもと定期検査を受けながら適切に管理していくことが重要です。
【参考情報】 『肺胞蛋白症診療ガイドライン2022』日本呼吸器学会
https://www.jrs.or.jp/publication/file/pap2022_241009.pdf?utm_source=chatgpt.com
【参考文献】
“Pulmonary alveolar proteinosis syndrome” by U.S. National Library of Medicine / National Institutes of Health
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5902187/?utm_source=chatgpt.com
◆「呼吸器内科で行われる検査とは?専門的な検査を紹介します」>>
4. 肺胞蛋白症の治療

肺胞蛋白症の治療法は、症状の程度や病型によって異なります。
ここでは主な治療アプローチを紹介します。
4-1 経過観察
症状が軽く安定している場合は治療を急がず、定期的な検査をしながら経過を見守ることがあります。
実際、約20〜30%の患者さんは治療しなくても自然に症状が改善した例が報告されています。
4-2 全肺洗浄療法
現在の標準治療は全肺洗浄療法(ぜんはいせんじょう)です。
全身麻酔下で片肺ずつ生理食塩水を大量に出し入れし、肺胞内の蓄積物を洗い流します。
この方法で多くの症例で症状の改善が期待できます。
ただし根本治療ではないため再び物質が溜まり、再度洗浄が必要になる場合もあります。
また全身麻酔が必要で体への負担が大きく、高度な設備を要するため実施可能な医療機関が限られます。
4-3 GM-CSF吸入療法
近年登場したGM-CSF吸入療法は、自己免疫性肺胞蛋白症で不足しているGM-CSFを補う治療法です。
日本ではサルグラモスチム(商品名サルグマリン)が有効性を認められ、2024年に保険承認されました。
数か月にわたり定期的に吸入投与することで肺胞マクロファージの働きを回復させ、多くの患者さんで症状の安定が得られています。
全肺洗浄に代わる新たな治療法として期待されています。
4-4 薬物療法・支持療法
症状緩和のための対症療法も行われます。
痰が多い場合は去痰薬や吸入薬、咳がつらい場合は鎮咳薬を使用します。
低酸素血症がみられる場合には在宅で酸素を吸入する在宅酸素療法を導入します。
こうした支持療法で生活の質を維持しつつ病状を観察します。
4-5 先天性・遺伝性の場合
先天性/遺伝性肺胞蛋白症は原因遺伝子を修復する治療法がなく、基本的に対症療法で経過を見ます。
重症例では肺移植や造血幹細胞移植(骨髄移植)が検討されることもあります。
特に出生直後から重度の呼吸不全の場合は専門的な治療が必要です。
病態や重症度に応じて様々な治療が選択されます。
新薬の登場により治療の選択肢が広がりつつあり、患者さんの負担軽減や予後改善が期待されています。
治療後も再発しうるため定期的な経過観察が欠かせません。
また肺胞蛋白症では肺の免疫機能低下により真菌症や非結核性抗酸菌症などの感染症にかかりやすくなります。
そのため治療だけでなく、感染予防や禁煙・粉じん回避など生活上の注意も重要です。
【参考情報】『肺胞蛋白症の治療』難病情報センター
http://nanbyou.or.jp/entry/4774
【参考文献】 “Autoimmune Pulmonary Alveolar Proteinosis” by American Lung Association
https://www.lung.org/lung-health-diseases/lung-disease-lookup/pulmonary-alveolar-proteinosis/autoimmune?utm_source=chatgpt.com
5. 肺胞蛋白症と間違えやすい病気

肺胞蛋白症は、症状や画像所見が他の肺疾患と似ている場合があり、診断にあたっては鑑別(見分けること)が重要です。
以下に、間質性肺炎・肺がん・肺感染症と肺胞蛋白症との違いを説明します。
5-1 間質性肺炎との違い
両者とも咳・息切れの症状があり、胸部CTでは両肺にすりガラス状の陰影が広がるため、一見よく似ています。
しかし、肺胞蛋白症ではときに白い粘稠な痰が出ますが、間質性肺炎では痰を伴わない乾いた咳が主体です。
また間質性肺炎では肺組織が炎症で線維化し蜂巣肺(蜂の巣状の病変)が生じますが、肺胞蛋白症では線維化は起こらず肺胞内に物質が溜まるだけです。
画像所見も、肺胞蛋白症は特徴的な敷石状陰影を示すのに対し、間質性肺炎では線維化による網目状陰影や蜂巣肺がみられます。
診断面では、肺胞蛋白症はBALで乳白色の洗浄液が得られたり抗GM-CSF抗体陽性で確定しますが、間質性肺炎は肺生検が必要になる場合があります。
【参考情報】難病情報センター「特発性間質性肺炎(指定難病85)」
https://www.nanbyou.or.jp/entry/156
5-2 肺がんとの違い
肺胞蛋白症も肺がんも咳や息苦しさなどの症状を起こしうる点や、画像検査で異常陰影が見つかる点は共通しています。
どちらも初期は自覚症状に乏しく健康診断などで偶然発見される場合があります。
大きな違いは画像所見で、肺がんでは肺の特定の部分に見られる塊状の腫瘤や結節が映ります。
また肺がんでは原因不明の長引く咳や血痰が現れることがありますが、肺胞蛋白症で血痰は極めてまれです。
診断にあたっては、肺胞蛋白症では洗浄液に悪性細胞がなくタンパク質様物質が確認され、一方肺がんでは生検でがん細胞が検出されるため、病理検査で両者を区別できます。
【参考情報】がん情報サービス「肺がん」国立がん研究センター
http://ganjoho.jp
5-3 感染症(非結核性抗酸菌症など)との違い
肺胞蛋白症と肺感染症(例:非結核性抗酸菌症)は、慢性的な咳や息切れ、体重減少が起こり、胸部CTでも両肺にすりガラス陰影がみられる点で共通します。
違いとして、感染症では発熱や痰の増加、CRP値の上昇がよくみられ、肺に空洞(穴)ができることもありますが、肺胞蛋白症ではこうした所見はほとんどみられません。
画像異常が認められた場合はまず痰の培養検査などで菌の有無を確認し、抗菌薬治療で影が改善すれば感染症と診断します。
治療に反応しない場合は肺胞蛋白症など他の病気を疑います。
また、肺胞蛋白症の患者さんは免疫低下により真菌症や非結核性抗酸菌症を合併しやすいため、診断時にこれらの感染の有無も注意して調べます。
6. まとめ
肺胞蛋白症は非常に稀な疾患ですが、原因や症状、治療法が少しずつ明らかになってきており、適切な診断と治療によって症状のコントロールも可能です。
息切れや長引く咳など気になる症状があれば、慌てずに呼吸器の専門医に相談してみてください。
早期発見と専門的なケアにより、肺胞蛋白症の患者さんも日常生活を送りながら上手に病気と付き合っていくことができます。
定期的な通院・検査を続け、医療チームと協力しながら体調管理に努めましょう。



