呼吸器内科のレントゲン検査とは

レントゲン検査は、呼吸器内科で広く行われる診断方法のひとつです。
レントゲン検査では、X線を用いて肺や心臓などの内部状態を画像化し、病気の有無や進行状況を確認します。
この記事では、レントゲン検査の仕組みや注意事項、検査でわかる病気、判断が難しい場合に行う追加検査についてご説明いたします。
1. レントゲン検査の仕組みと注意事項
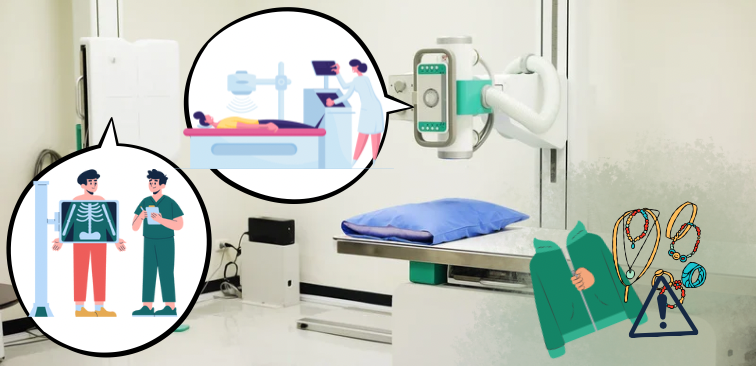
ここからは、レントゲン検査の仕組みと注意事項についてご紹介しましょう。
1-1. レントゲン検査とは
レントゲン検査は、X線(放射線の一種)をからだに照射し、その透過性の違いを利用して体内の画像を撮影する方法です。
骨や水分を多く含む部位は白く写り、空気が多い肺などは黒く写る特徴があります。
この特性により肺炎や腫瘍など異常がある部位を特定できます。
レントゲン検査の技術はドイツの物理学者ヴィルヘルム・レントゲンによって1895年に発見されました。
そのため、一般的に「レントゲン検査」と呼ばれています。
レントゲン検査の大きな利点は、非侵襲的であることです。
つまり、からだを傷つけることなく内部の状態を観察できます。
また、検査時間が短く即座に結果を得られることも特徴です。
これにより、医師は迅速に診断を行い、適切な治療方針を立てることができます。
なお、レントゲン検査は、胸部だけでなく、骨や腹部など、からだのさまざまな部位の撮影に使用されます。
1-2. 撮影方法
胸部レントゲン検査では主に立位(りつい)で撮影します。
以下が基本的な流れです。
1. X線装置に背を向けて立ち、胸をパネルに密着させます。
2. 少し前かがみになり、大きく息を吸って止めた状態で撮影します。
3. 撮影時間は5〜10分程度で終了します。
必要に応じて座位や寝た状態(臥位・がい)で撮影することもあります。
例えば、立位での撮影が困難な患者さんや、特定の疾患の診断のために異なる体位での撮影が必要な場合などです。
撮影の際は、放射線技師から詳しい指示があるため、その指示に従って姿勢を整えましょう。
正確な画像を得るためには、からだの位置や呼吸のタイミングが重要です。
また、通常は正面からの撮影を行いますが、場合によっては側面からの撮影も行うことがあります。
これにより、正面からは見えにくい病変を発見したり、病変の位置をより正確に把握したりすることが可能です。
1-3. 注意すること
検査時には服装や身につけるものに注意が必要です。薄いシャツであれば着たまま撮影可能ですが、以下の場合には洋服を脱ぐことが必要になることがあります。
・ボタンやファスナー付きの服
・刺繍やプリント柄がある服
・金属製の下着やアクセサリー
これらの物は、X線を遮ったり、画像に影響を与えたりする可能性があるため、撮影前に外すことが必要です。
また、湿布やペースメーカーなども画像に影響を与える可能性があるため、事前に医師へ相談しましょう。
撮影時には、できるだけからだを動かさないようにすることが大切です。
もし息を止めるのが難しい場合は、事前に放射線技師の方に伝えておくとよいでしょう。
また、レントゲン検査では微量の放射線を浴びますが、1回の検査で浴びる放射線量は非常に少なく、健康への影響はほとんどありません。
一方で、頻繁に検査を受ける場合は、医師と相談のうえで検査の頻度を決めることが望ましいです。
1-4. 医師に相談が必要な場合
妊娠中または妊娠の可能性がある方は、胎児への影響を避けるため必ず医師に相談してください。
胎児は放射線の影響を受けやすいため、特別な配慮が必要です。
医師は、検査の必要性と潜在的なリスクを慎重に検討し、適切な判断を下します。
また、糖尿病などの持病があり薬を服用している方も事前に医師へ伝えましょう。
特定の薬剤は、レントゲン検査の結果に影響を与える可能性があります。
例えば、造影剤を使用する特殊なレントゲン検査の場合、腎臓機能に影響を与える薬を服用している方は注意が必要です。
さらに、過去にレントゲン検査で副作用や不快な症状を経験したことがある方も、必ず医師に相談してください。
まれに、造影剤によるアレルギー反応などが起こることがあります。
【参考文献】”Radiographic Screening and B Readers” by Centers for Disease Control and Prevention
https://www.cdc.gov/niosh/chestradiography/php/about/index.html?utm_source=chatgpt.com
2. レントゲン検査で発見できる呼吸器の病気

胸部レントゲン検査では、さまざまな呼吸器疾患を発見することができます。
ここからは、主な疾患と特徴をご説明いたしましょう。
肺炎
肺炎は、細菌やウイルスなどの病原体によって引き起こされる肺の炎症です。
レントゲン画像では、炎症による白い影(浸潤影)が確認されます。
この影は、通常、片側または両側の肺に斑状(はんじょう・斑点状の異常陰影が見られる状態)が広範囲に現れます。
肺炎の種類や重症度によって、影の形や大きさが異なることがあります。
例えば、細菌性肺炎(肺炎球菌性肺炎・マイコプラズマ肺炎など)では比較的はっきりとした境界の影が見られることが多いのに対し、ウイルス性肺炎(新型コロナウイルス感染症(COVID-19)・RSウイルス性肺炎・アデノウイルス性肺炎など)ではより広範囲にわたって淡い影が見られることがあります。
肺がん
肺がんは、レントゲン検査で白い塊状の影として現れることがあります。
ただし、初期の小さながんは見つけにくいことがあるため、定期的な検査やほかの検査方法(CTスキャンなど)と組み合わせて診断することが重要です。
肺がんの影は、その大きさ、形状、位置によってさまざまな様相を呈します。
たとえば、末梢型(肺の末梢(端)に癌ができるタイプ)の肺がんは円形の影として現れやすく、中心型の肺がんは気管支の閉塞や肺炎様の陰影として現れることがあります。
COPD(慢性閉塞性肺疾患)
COPDは、長期の喫煙などによって引き起こされる進行性の肺疾患です。レントゲン検査では、肺気腫などによる肺組織の変化が見られます。
具体的には、肺が通常よりも大きく膨らんで見えたり、横隔膜が下がって平たくみえたりする特徴があります。
また、COPDが進行すると、肺の血管影が減少したり、気管支壁が厚くなったりする変化も観察されることがあります。
ただし、軽度のCOPDではレントゲン検査で異常が見られないこともあるため、呼吸機能検査などと併せて診断されます。
肺結核
肺結核は、結核菌による感染症で、レントゲン検査では特徴的な陰影が現れます。
初期の結核では、肺の上部に小さな影(結節影)が見られることが多く、進行すると空洞を形成することがあります。
また、古い結核病変が治癒した跡として、石灰化した影が見られることもあります。
結核の診断には、レントゲン検査だけでなく、喀痰(かくたん)検査や培養検査なども併せて行われます。
気胸
気胸は、肺から空気が漏れて胸腔内にたまった状態です。
レントゲン検査では、肺が縮小し、胸腔内に空気層が見られます。
空気層は、通常の肺野(はいや)よりも黒く写ります。
気胸の程度によって、肺の虚脱(つぶれ)の程度が異なります。
軽度の気胸では、わずかな空気層しか見られないこともありますが、重度の場合は肺が大きく縮小し、明らかな空気層が観察されます。
胸水
胸水は、胸腔内に水分が溜まった状態です。
レントゲン検査では、通常は空気で満たされているはずの胸腔に、水分による白い影が見られます。
胸水の量が少ない場合は、立位での側面像で確認されることがあります。
胸水の原因はさまざまで、心不全、肺炎、がんなどが考えられます。
胸水の性状や原因を特定するためには、さらなる検査(胸水穿刺・きょうすいせんし等)が必要になることがあります。
これらの病気以外にも、心臓の大きさや形状も確認できるため、一部の心疾患発見にも役立ちます。
たとえば、心不全による心拡大や、心臓弁膜症による心臓の形態変化なども、胸部レントゲン検査で観察できることがあります。
【参照文献】環境再生保全機構『COPDかも…。どうしたらわかりますか?』
https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/copd/about/04.html
【参考文献】”Pneumonia – Diagnosis” by National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI), NIH
https://www.nhlbi.nih.gov/health/pneumonia/diagnosis
【参考文献】”COPD – Diagnosis” by NHLBI, NIH
https://www.nhlbi.nih.gov/health/copd/diagnosis
【参考文献】”Pleural Disorders – Pleurisy, Pleural Effusion, and Pneumothorax” by NHLBI, NIH
https://www.nhlbi.nih.gov/health/pleural-disorders/types
参考文献】”Collapsed lung (pneumothorax)” by MedlinePlus, U.S. National Library of Medicine
https://medlineplus.gov/ency/article/000087.htm
3. レントゲン検査では判断できない病気もある
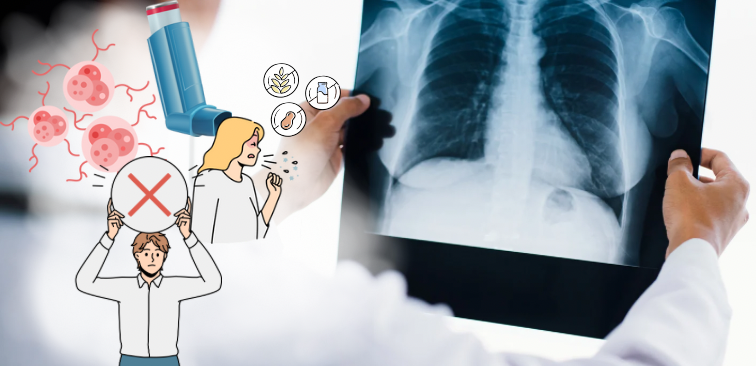
レントゲン検査は多くの疾患の診断に役立ちますが、一方で、レントゲン検査だけでは判断できない場合もあります。
ここからは、それらの疾患の例を挙げてご説明いたします。
微細ながん細胞
非常に小さい腫瘍や初期段階のがんは、レントゲン検査では映らない場合があります。
これは、レントゲン検査の解像度の限界によるものです。
とくに、直径1cm未満の小さながんは、胸部レントゲン検査では見逃される可能性が高くなります。
このような場合、CTスキャンやMRI、PET-CTなどのより詳細な画像診断が必要です。
これらの検査は、レントゲン検査よりも高解像度で、小さな病変も捉えることができます。
喘息やアレルギー咳嗽(がいそう)
喘息やアレルギーによる咳(アレルギー咳嗽)は、気道の炎症や過敏性が原因で起こりますが、これらの変化はレントゲン画像上で異常が確認できないことがあります。
喘息やアレルギー咳嗽では、気道の機能的な変化が主な問題となるため、形態的な変化を捉えるレントゲン検査では異常が見られないことが多いのです。
そのため、診断には問診、聴診、呼吸機能検査などが重要になります。
初期の間質性肺炎
間質性肺炎は肺の間質(肺胞と肺胞の間の組織)に炎症や線維化が起こる病気ですが、初期の微細な変化はレントゲン検査では見逃されることがあります。
このような場合、高解像度CT(HRCT)検査が有用です。
HRCTでは、初期の間質性肺炎でも特徴的な所見を捉えることができます。
肺塞栓症
肺塞栓症は、肺動脈が血栓などによって詰まる重篤な疾患ですが、レントゲン検査では正常に見えることがあります。
とくに発症初期や軽症例では、レントゲン上の変化が乏しいことがよくあります。
肺塞栓症の診断には、造影CTや肺血流シンチグラフィーなどの特殊な検査が必要になることが多いです。
気管支喘息の発作間欠期
気管支喘息の患者さんでも、発作が起きていない時期(間欠期)にはレントゲン検査で異常が見られないことがほとんどです。
喘息は気道の慢性的な炎症による疾患ですが、その変化はレントゲン検査では捉えにくいのです。
喘息の診断や経過観察には、症状の評価、呼吸機能検査、気道過敏性試験などが重要な役割を果たします。
レントゲンは症状の原因精査にとってとても有用です。
呼吸器疾患を診断するうえで必須といっていいですが限界があることも事実です。
それを理解しながら診断を進めることが重要となります。
患者さんのなかには、「レントゲン検査で異常がなかったから大丈夫」と安心してしまう方もいらっしゃいます。
しかし、症状が続く場合は、たとえレントゲン検査で異常がなくても、担当医に相談することが大切です。
【参考文献】”Limitations of Chest X‑Ray in Cancer Detection” by National Cancer Institute (NCI)
https://www.cancer.gov/types/lung/hp/lung-screening-pdq
【参考文献】”HRCT in Interstitial Lung Disease” by Radiopaedia.org
https://radiopaedia.org/articles/diagnostic-hrct-criteria-for-usual-interstitial-pneumonia-uip-pattern-atsersjrsalat-2018?lang=us
【参考文献】”Pulmonary Embolism – Diagnosis” by MedlinePlus, U.S. National Library of Medicine
https://medlineplus.gov/pulmonaryembolism.html
4. レントゲン検査だけで判断できない時におこなう検査
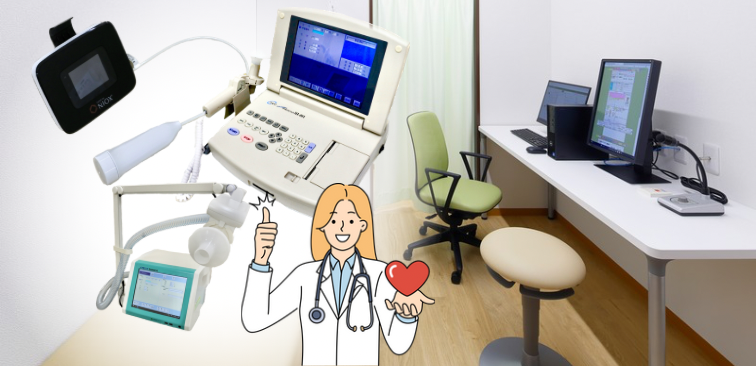
レントゲン検査だけでは診断が難しい場合には、さまざまな追加検査が行われます。
これらの検査は、より詳細な情報を得たり、特定の疾患を確定診断したりするために重要です。
ここからは、主な追加検査についてご説明しましょう。
スパイロメトリー
スパイロメトリーは、肺活量や呼吸機能を測定する検査です。
スパイロメトリーでは、患者さんに大きく息を吸ってもらい、それを一気に吐き出してもらいます。
その際の空気の流れを測定することで、以下のような情報が得られます。
・肺活量(VC):肺に取り込める最大の空気量
・1秒量(FEV1):1秒間に吐き出せる空気量
・努力肺活量(FVC):できるだけ早く、深く吐き出したときの空気量
これらの値を分析することで、閉塞性肺疾患(COPD、喘息など)や拘束性肺疾患(間質性肺炎など)の診断や重症度の評価に役立ちます。
スパイロメトリーは非侵襲的で比較的簡単に行える検査ですが、患者さんの協力が必要です。
検査の際は、技師の指示に従って、できるだけ大きく息を吸い、一気に吐き出すよう心がけましょう。
呼気一酸化窒素濃度測定(FeNO)
FeNO検査は、喘息などのアレルギー性気道炎症の診断に有効な検査です。
FeNO検査では、患者さんに一定の速さで息を吐いてもらい、呼気中の一酸化窒素(NO)濃度を測定します。
気道に炎症がある場合、NOの産生が増加するため、呼気中のNO濃度が上昇します。
とくに、好酸球性の気道炎症(アレルギー性喘息など)で顕著に上昇することが知られています。
FeNO検査の利点は、非侵襲的で即座に結果が得られること、そして喘息の診断だけでなく、治療効果のモニタリングにも使用できることです。
ただし、喫煙者の方ではNO濃度が低下することがあるため、結果の解釈には注意が必要です。
モストグラフ
モストグラフは、呼吸抵抗を測定する新しい検査方法です。
モストグラフでは、患者さんが通常の呼吸をしている間に、口から小さな圧力波を送り込み、その反応を測定します。
モストグラフの特徴は、患者さんの特別な努力を必要とせず、安静呼吸下で測定できることです。
そのため、高齢者の方やお子さま、重症の患者さんでも比較的負担が少なく検査を行うことができます。
モストグラフでは、以下のような情報が得られます。
・呼吸抵抗(R5、R20など):気道の狭窄の程度を反映
・呼吸リアクタンス(X5など):肺の弾性や末梢気道の状態を反映
これらの値を分析することで、喘息やCOPDなどの閉塞性肺疾患の診断や、治療効果の評価に役立ちます。
とくに、従来の検査では捉えにくかった末梢気道の機能評価に有用とされています。
胸部CT検査
胸部CT(コンピュータ断層撮影)検査は、レントゲン検査よりも詳細な画像を得ることができる検査です。
CTでは、からだの断層画像を撮影するため、病変の位置や大きさ、形状をより正確に把握することができます。
CTはとくに以下のような場合に有用です。
・レントゲンで異常が疑われるが、詳細が不明な場合
・小さな肺がんや転移巣の検索
・間質性肺炎の診断と経過観察
・気管支拡張症の評価
・肺塞栓症の診断
ただし、CTは被ばく量がレントゲンよりも多いため、検査の必要性と利益を十分に検討したうえで実施されます。
気管支鏡検査
気管支鏡検査は、細い管状の内視鏡を気管や気管支に挿入して直接観察する検査です。
気管支鏡検査では、以下のようなことが可能です。
・気道内の異常(腫瘍、炎症、出血など)の直接観察
・病変部からの組織採取(生検)
・気管支洗浄液の採取(細胞診や培養検査用)
気管支鏡検査は、レントゲンやCTでは判断が難しい気道内の異常や、原因不明の咳、喀血などの精査に有用です。
ただし、侵襲的な検査のため、患者さんの状態や検査の必要性を慎重に検討した上で実施されます。
検査に不安がある場合や、検査の目的がよくわからない場合は、遠慮なく担当医に質問してください。
医師は患者さんの理解と協力を得ながら、最適な診断と治療を目指します。
【参考文献】”Pulmonary Function Tests” by National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI), NIH
https://www.nhlbi.nih.gov/health/lung-tests
【参考文献】”Pulmonary Embolism – Diagnosis and Treatment” by Mayo Clinic
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/pulmonary-embolism/diagnosis-treatment/drc-20354653
【参考文献】”Lung Cancer Early Detection” by CDC
https://www.cdc.gov/lung-cancer/screening/index.html
5. おわりに
レントゲン検査は呼吸器疾患診断の基本です。
必要に応じて追加検査を行うことで、正確な診断と適切な治療をすることが可能です。
定期的な健康診断と健康的な生活習慣で呼吸器の健康を維持しましょう。



