喘息や咳喘息のときに行くべき病院

喘息は身の回りで聞くことも多い身近な病気ですが、重症化すると命の危険性もある病気です。
また、気管支喘息と咳喘息の違いについて、よく分からないという方も多いのではないでしょうか。
つらい咳症状が続いていたら放置せず、早めに治療を開始することが大切です。
この記事では喘息・咳喘息の基本的な情報や、受診目安、病院の選び方について詳しく解説します。
1.2週間以上続く咳。それは喘息かも

2週間以上咳が続く場合は喘息、咳喘息、COPD(慢性閉塞性肺疾患)、肺炎、肺がん、結核などが考えられます。
◆「2週間以上続く咳で考えられる病気」について詳しく>>
◆「COPD」について詳しく>>
喘息は空気の通り道である気道に炎症が生じることで気道が狭くなり、発作的に咳や呼吸困難などの症状が現れる病気で、「ゼーゼー」「ヒューヒュー」のような喘鳴(ぜんめい)が特徴的です。
喘息の患者さんは、症状がない時でも気道に慢性的な炎症が起きている状態で、少しの刺激でも反応しやすい過敏な状態となっています。
風邪、運動、アレルゲン、タバコ、気温や気圧の変化などさまざまな刺激がきっかけとなって発作が起こります。
喘息といえば子どもがかかりやすいというイメージですが、成人になってから発症する成人発症喘息は、特に完治が難しい病気だと言われています。
また、治療せずに放っておくと悪化し「ぜんそく死」を招くこともある病気です。
ぜんそく死は減少傾向にありますが、2022年には1004人の方が喘息で亡くなっています。
ぜんそく死の原因は重篤な発作による窒息死で、感染症、過労、ストレスなどが発作の引き金となっています。
解剖の結果もともと気道に慢性的な炎症があった場合が多く、喘息の治療や自己管理が不十分だったことも考えられます。
【参考情報】『令和4年(2022) 人口動態統計(確定数)の概況 第7表 死因簡単分類別にみた性別死亡数・死亡率(人口10万対)』厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei22/dl/11_h7.pdf
【参考情報】『喘息死ゼロ作戦の実行に関する指針』 厚生労働省 喘息死ゼロ作戦評価委員会
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/kenkou/ryumachi/dl/jititai05_0001.pdf
しかし、適切な治療を受け、自己管理を継続することで健康な人と同じような日常生活を送ることができます。
定期的に受診し、処方された通り薬物治療を行うことはもちろんですが、生活環境を整えたり症状について記録するといった自己管理も大切です。
【参考情報】『成人喘息の疫学、診断、治療と保健指導、患者教育』厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/kenkou/ryumachi/dl/jouhou01-07-0001.pdf
【参考情報】『気管支ぜんそく』日本呼吸器学会
https://www.jrs.or.jp/citizen/disease/c/c-01.html
2.喘息を疑うときは呼吸器内科へ

呼吸器内科とは、のど、気管支、肺、胸膜など呼吸器の病気に特化した診療科です。
一般的な内科では呼吸器以外の症状についても総合的に診察しています。
発熱、頭痛、腹痛などの症状がある場合、まずは一般内科で総合的に診てもらうのもいいでしょう。
「咳が止まらない」「息が苦しい」などの呼吸器症状が目立つ場合は呼吸器内科の受診をおすすめします。
呼吸器内科では専門医の診察に加え、呼吸機能検査でより詳しい病状を把握することができます。
また、呼吸器内科の中でも「喘息の専門医がいる病院」「睡眠時無呼吸症候群を得意とする病院」「禁煙カウンセリングを行っている病院」など様々な特徴があります。
例えば、喘息の治療では、気管支拡張剤や吸入ステロイド薬の量を症状の程度に応じて調整する必要があり、喘息の専門医のいる病院がおすすめです。
3.喘息と咳喘息の違いって?
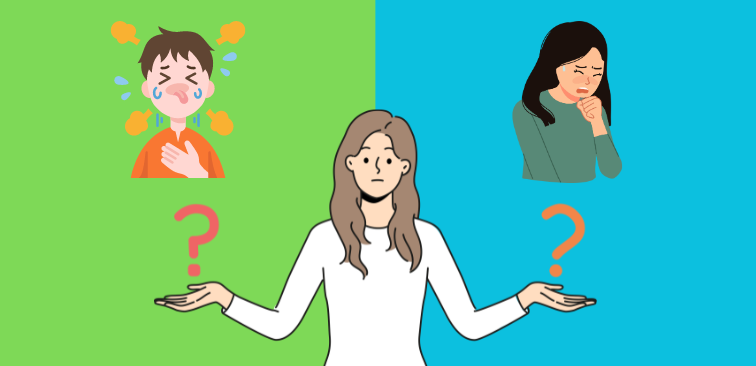
喘息と咳喘息は何が違うのでしょうか?
咳の種類や、咳喘息の特徴、進行、治療について解説します。
3-1. 期間による咳の分類
咳は症状が続いている期間によって「急性咳嗽(がいそう)」「遷延性(せんえんせい)咳嗽」「慢性咳嗽」に分けられます。
①急性咳嗽:3週間未満の咳。風邪などの感染症によるものが多い。
②遷延性咳嗽:3週間以上8週間未満の咳。感染症の後に咳症状だけが残ることが多い。
③慢性咳嗽:8週間以上の咳。感染症の可能性は低く、咳喘息やアトピー性咳嗽、肺結核など。
【参考情報】『慢性咳嗽の病態,鑑別診断と治療 ―咳喘息を中心に― 』日本内科学会雑誌第105巻第10号
https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/105/9/105_1565/_pdf
3-2.咳と咳喘息の違い

咳喘息は咳のみが症状として現れる喘息の前段階の状態です。
咳喘息の特徴には次のようなものがあります。
・咳が長引く
・喘鳴を伴わない
・深夜、早朝に咳が悪化する
・季節の変わり目や天候、運動によって咳が悪化する
・喉の違和感や胸のしめつけ感がある
慢性咳嗽の基準は厳密には8週間ですが、3週間以上続いている場合は喘息や咳喘息の可能性が強く疑われます。
また、喘息は「ゼーゼー、ヒューヒュー」のような喘鳴を伴うことが特徴ですが、喘鳴がなく咳だけの場合を咳喘息と言います。
ただし、喘息でも息苦しさや喘鳴が見られず症状が咳のみということがありますので、自分で判断せず専門の医療機関を受診しましょう。
◆「季節の変わり目は喘息発作の予防を!」>>
◆「朝の咳と夜の咳の違いについて」>>
咳喘息は喘息と違って、基本的には呼吸機能検査で異常が見られないのも特徴です。
【参考情報】『咳喘息』日本内科学会雑誌第109巻第10号
https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/109/10/109_2116/_pdf
喘息も咳喘息も、もともとアレルギーの素因を持っている人が発症しやすいと言われており、アレルゲン(アレルギーの原因となる物質)を吸い込むことや風邪などの感染がきっかけで起こります。
【参考文献】”Cough-Variant Asthma” by Cleveland Clinic
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/25200-cough-variant-asthma
3-3.咳喘息は喘息に移行する?
咳喘息は特に風邪などの後に起こり、その3〜4割は本格的な喘息へと移行します。
喘息の段階まで進行する前に、早めに治療を開始することが大切です。
3-4.治療

喘息と咳喘息では症状に違いがありますが、基本的な治療方針は同じです。
薬物治療としては喘息と同様に吸入ステロイド薬や気管支拡張剤の投与を行います。
吸入ステロイド薬は気管の炎症を抑えるための薬です。
気管支拡張剤は気管支平滑筋(気管支の太さを変えて、息の量を調整する筋肉)を弛緩させ、気管を広げることで呼吸しやすくする薬です。
「気管支拡張剤によって咳が治まる」ことも咳喘息の診断基準になっています。
また、ご自宅で行う自己管理としては喘息日記の記載やピークフローメーターを使った気道閉塞のモニタリングなどがあります。
喘息日記やピークフローメーターは、日内変動の把握や治療方針が適切かを評価するために大切です。
【参考文献】『慢性咳嗽(咳喘息)』呼吸器内科学レビュー
【参考情報】『診療群別臨床検査のガイドライン2003』長谷川好規
https://www.jslm.org/books/guideline/04.pdf
4.おわりに
喘息は、咳や息苦しさなどのつらい症状だけでなく、発作によって命の危険もある病気です。
しかし自己管理や服薬など、喘息と上手く付き合っていくことができれば健康な人と同じような生活を送ることができます。
咳が2週間以上続いている場合は咳喘息や喘息かもしれません。
手遅れにならないためにも、早めに呼吸器内科を受診してください。



