子どもの咳が繰り返す原因とは?家庭でできるケアと受診の目安

夜間にお子さんが咳き込むと、とても心配になる保護者の方は多いのではないでしょうか。
とくに、赤ちゃんや小さなお子さんは自分でつらさを伝えられないため、どの程度苦しいのか判断が難しいですよね。
子どもは大人より気道が細く、些細な刺激でも咳が出やすい傾向があります。
多くの場合、咳は風邪など一時的な原因で起こり、時間とともに治まります。
しかし、長引く咳や夜だけ咳き込む場合には、別の原因が隠れている可能性もありますので注意が必要です。
この記事では、子どもの繰り返す咳の原因から家庭でできる対処法、受診の目安まで解説していきます。
1. 子どもの咳の原因

子どもの咳の多くは、ウイルスなどによる風邪が原因です。
風邪の場合、咳や鼻水などの症状は通常1~2週間程度で改善します。
とくにRSウイルス感染症は乳幼児で肺炎や細気管支炎(さいきかんしえん)を引き起こすことがあり、生後6か月以内の初感染では重症化しやすいことが知られています。
このような感染症以外にも、咳が長引く背景にはさまざまな病気が考えられます。
例えば、気管支が急性の炎症を起こす急性気管支炎や、肺に炎症が及ぶ肺炎では、長引く咳や発熱を伴うことがあります。
百日咳のように激しい咳が続く感染症では、咳込みによって嘔吐することもあります。
また、気管支喘息(小児喘息)の初期症状では、夜間や明け方に咳が出る場合もあるでしょう。
さらに、鼻炎や副鼻腔炎で喉に鼻水が流れ込むときや、夜間の冷たい空気・乾燥した空気によって気道が刺激されるときにも、咳が悪化しやすいです。
【参考情報】『RSウイルス感染症に関するQ&A』厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/rsv_qa.htm
【参考情報】『RSウイルス感染症に関するQ&A』厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/rsv_qa.htm#:~:text=
2.家庭でできる咳へのケア

夜間にお子さんが咳き込んでいると、何か楽になる方法はないのかと思いますよね。
この章では、少しでもお子さんを楽にしてあげるために、家庭で簡単にできる対処法を紹介します。
2-1. 加湿して喉を潤す
咳をおさえるには、部屋の湿度を保つことが大切です。
加湿器を使ったり濡れタオルを掛けたりして、湿度はおおよそ40~60%に保ちましょう。
湿度が十分にあると気道の乾燥を防ぎ、咳を和らげる効果が期待できます。
2-2. 室温を調整する
室温にも気を配りましょう。
冬場はとくに空気が冷えて乾燥しがちです。
部屋は適度に暖かく保ち(目安として22~24℃程度)、冷たい空気で気道が刺激されないようにすることが大切です。
2-3. 楽な姿勢で休ませる
咳が出るときは横になると辛くなることがあります。
寝るときに枕や布団を工夫して上半身を少し高くしてあげると、呼吸が楽になり咳が和らぐ場合があります。
2-4. 水分をこまめに取らせる
喉を潤すことも効果的です。
水やぬるめの飲み物を少しずつ飲ませてあげましょう。
1歳以上であれば、ハチミツをお湯やミルクに少し溶かして与えると咳に良いと言われています。
要注意:1歳未満の乳児には、乳児ボツリヌス症を防ぐため、ハチミツを絶対に与えないでください。
2-5. 痰を出しやすくする工夫
痰が絡んでいるときは、背中を優しくトントンと叩いてあげると痰が出やすくなります。
保護者の方も心配だとは思いますが、不安がお子さまに伝わるとお子さまも更に不安になってしまいます。
お子さんが咳で苦しそうなときでも、保護者の方がそばに付きそい、落ち着かせてあげることで安心感につながりますよ。
◆「咳がつらい時の寝姿勢!うつ伏せ・仰向け・横向きのどれがいい?」>>
【参考情報】『子どもの救急ってどんなとき?~せき・息が苦しい時』群馬県医務課
https://www.pref.gunma.jp/page/4127.html
3. 病院を受診する目安
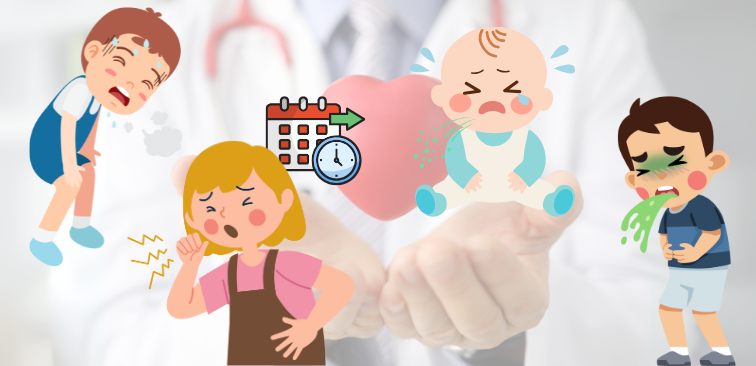
咳をしているお子さまを受診させるべきか迷うことがありますよね。
基本的に、軽い咳で元気もあり、熱もない場合は少し様子を見ても大丈夫でしょう。
しかし、次のような場合には早めに医療機関を受診することを検討してください。
3-1. 呼吸が苦しそうなとき
ゼーゼー・ヒューヒューと喘鳴(ぜんめい)が聞こえたり、肩やお腹を使ってぜいぜい呼吸している、呼吸が速く浅いなど、明らかに呼吸困難の兆候がある場合は要注意です。
唇や顔色が青白く(チアノーゼ)なるようなときは、酸素が足りない危険な状態ですので至急受診してください。
3-2. 咳が長引くとき
普通の風邪であれば咳は1〜2週間で治まりますが、それ以上に何週間も咳が続くときは、小児科や呼吸器内科で相談しましょう。
とくに夜だけ咳が出る日を繰り返す場合や、「ゼーゼー」という音が慢性的に続く場合には、喘息など他の病気の可能性があります。
小児科で「喘息ではない」と言われても、咳がしつこく心配なときは、呼吸器の専門医に相談してもよいでしょう。
◆「子供が呼吸器内科を受診する目安は?よくある病気と症状について」>>
3-3. 赤ちゃんの咳の場合
赤ちゃん(生後3か月頃まで)の咳はとくに注意が必要です。
乳児は気道が狭く、一気に症状が悪化することがあります。
咳が弱くても飲みが悪い、ぐったりして元気がない、泣き方がおかしいなど普段と違う様子が見られたら、早めに受診しましょう。
3-4. その他の注意すべきケース
高熱が3日以上続く場合や、咳とともに嘔吐してしまう場合も、単なる風邪ではない可能性が考えられます。
とくに、夜間に咳き込んで嘔吐し、十分な睡眠がとれないと、体力の低下や脱水にもつながるおそれがあります。
また、繰り返す嘔吐によって食事や水分が摂れなくなると、栄養状態の悪化や脱水症状を引き起こすリスクもあります。
咳が強く、日常生活に支障が出ているような場合は、早めに小児科など医療機関を受診し、原因を特定することが大切です。
【参考情報】『救急外来受診(せき・息が苦しいとき)』茨城県小児救急医療啓発サイト
https://www.pedqq.pref.ibaraki.jp/commentary/救急外来受診-2/
『こどもの救急(ONLINE-QQ)』日本小児科学会監修
https://kodomo-qq.jp/
4. 小児喘息の早期発見と対応

繰り返す咳やゼーゼーという呼吸音がある場合、小児喘息(気管支喘息)の可能性があります。
小児喘息とは、気道が慢性的に炎症を起こし、発作的に咳や呼吸困難(息苦しさ)などを生じる病気です。
症状は夜間から明け方に悪化しやすい特徴があり、運動後や笑った後に咳込むこともあります。
4-1. 小児喘息とはどんな病気?
小児喘息かどうか早期に見極めるには、以下のような点に注意しましょう。
・風邪をひくたびに咳が長引く
・夜中や朝方に咳で何度も目を覚ます
・走った後にゼーゼーする
といった症状が繰り返し見られる場合は喘息を疑います。
また、ご家族に喘息やアレルギー体質の方がいる場合、お子さんも喘息になりやすい傾向があります。
4-2. 小児喘息を疑うサイン
上記のような兆候がある場合には、小児科医や呼吸器の専門医に相談しましょう。
医師による診断では、症状の経過や聴診、必要に応じて検査を行い、小児喘息かどうか判断します。
早い段階で喘息と分かれば、その後の適切な対応につなげることができます。
4-3. 早期治療と管理の重要性
小児喘息と診断された場合は、早期に適切な治療を始めることが重要です。
吸入ステロイド薬などで気道の炎症を抑える長期管理治療を継続することで、発作を予防できます。
治療を続けることで、子どもの成長とともに症状が改善し、発作が起こらなくなるケースも多くあります。
実際、喘息の子どもの多くは思春期までに症状が軽快するとされます。
適切な治療と管理により、将来的な健康リスクを減らし、子どもは普段と変わらない生活を送ることも可能です。
4-4. 発作予防と日常生活の工夫
日常生活では、喘息の誘因となるタバコの煙やハウスダスト、ダニなどをできるだけ避けるようにしましょう。
定期的に掃除や換気を行い、寝具も清潔に保つことが大切です。
外遊びや運動も主治医と相談の上で適度に行い、本人の体調に合わせて無理のない範囲で活動させてあげてください。
発作時には、慌てずに指示された吸入薬を使用し、改善しなければ医療機関での処置を受けるようにしましょう。
【参考情報】『小児ぜん息基礎知識』環境再生保全機構
https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/basic/kodomonozensoku/
【参考情報】『小児のぜん息Q&A』日本アレルギー学会
https://www.jsaweb.jp/modules/citizen_qa/index.php?content_id=2
5. おわりに
お子さんの夜間の咳について、原因や対処法、小児喘息の可能性などを紹介してきました。
夜の咳は心配ですが、多くの場合は適切なケアで乗り切ることができます。
一方で、長引く咳や苦しそうな様子があるときには早めに受診し、必要ならば検査や治療を受けましょう。
小児喘息であっても、現在では良い治療法が確立されており、発作をコントロールしながら成長とともに症状が改善するケースが少なくありません。
お子さんの咳に気になる点があれば、無理をせず専門医に相談してください。
早期に対応することで、お子さんが夜ぐっすり眠れ、元気に日中の生活を送れるようサポートしていきましょう。



