子どもが喘息発作を起こしたら?応急処置と受診判断

お子さんが夜中に突然「ゼーゼー」と苦しそうな呼吸を始めたとき、慌ててしまった経験はありませんか?
喘息を持つ子どもの保護者にとって、発作時の応急処置は常に心配の種です。
しかし、正しい知識があれば冷静に対処することが可能です。
本記事では、家庭でできる応急処置から医療機関への受診判断まで、保護者が知っておくべき重要なポイントを解説いたします。
1. 喘息発作の基本的な理解と症状の見極め

喘息発作への適切な対応を行うためには、まず発作がどのようなメカニズムで起こり、どのような症状が現れるのかを理解することが重要です。
喘息は気道の慢性的な炎症により、様々な刺激に対して気道が過敏に反応し、急激に狭くなることで発作が起こります。
1-1. 発作時に現れる典型的な症状
喘息発作が始まると、お子さんには特徴的な症状が現れます。
最も分かりやすいのは呼吸音の変化で、「ヒューヒュー」「ゼーゼー」という喘鳴(ぜんめい)と呼ばれる音が聞こえるようになります。
この音は気道が狭くなることで空気の流れが乱れて生じるもので、発作の重要なサインとなります。
呼吸困難も主要な症状で、お子さんは息苦しそうな表情を見せ、普段より呼吸が浅く速くなります。
また、乾いた咳が続いたり、痰を伴う咳が出ることもあります。
特に注意深く観察していただきたいのは、胸の動きの変化です。発作時には「陥没呼吸」と呼ばれる現象が見られることがあります。
これは、のどぼとけの下や肋骨の間が、息を吸うときにはっきりとへこむ状態で、呼吸筋が普段以上に頑張って働いていることを示しています。
陥没呼吸は発作の程度を判断する重要な指標となりますので、ぜひ覚えておいてください。
【参考情報】『発作時の対応』環境再生保全機構
https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/basic/kodomonozensoku/hossa.html
【参考情報】”What to Do When an Emergency Occurs | Asthma” by U.S. Centers for Disease Control and Prevention
https://www.cdc.gov/asthma/emergency/index.html
1-2. 発作の程度を正しく評価する方法
発作への適切な対応を行うためには、その程度を正しく評価することが欠かせません。
医学的には発作の程度を軽度・中等度・重度に分類しますが、ご家庭では日常生活への影響度で判断していただくのが実用的です。
軽度の発作ではお子さんは話すことができますが、激しく動くと息切れを感じるようになります。
中等度になると横になることが困難になり、会話も短い単語や文章でしかできなくなります。
重度の発作では動くことさえ困難になり、座っていても呼吸が苦しい状態となります。
・軽度の発作…会話はできるものの、激しく動くと息切れを感じるようになる。
・中程度の発作…横になることが困難になり、会話も短い単語や文章でしかできなくなる。
・重度の発作…動くことさえ困難になり、座っていても呼吸が苦しい状態となる。
お子さんの普段の様子と比較して、食欲や睡眠などの日常生活への影響度を観察し、発作の程度を判断してください。
顔色や表情、話し方の変化も重要な手がかりとなります。
【参考情報】”Asthma in Children – Vital Signs” by U.S. Centers for Disease Control and Prevention
https://www.cdc.gov/vitalsigns/pdf/2018-02-vitalsigns.pdf
2. 家庭における基本的な応急処置の実践方法

喘息発作が起きた際の応急処置において、最も重要なのは保護者自身が落ち着くことです。
お子さんは保護者の感情を敏感に感じ取るため、慌てふためく様子を見せるとそれがさらなる不安や恐怖につながり、症状を悪化させる可能性があります。
深呼吸をして心を落ち着かせ冷静に対処することが、効果的な応急処置の第一歩となります。
2-1. 呼吸を楽にする体位の確保
発作時は、お子さんを呼吸しやすい姿勢にしてあげることが大切です。
横になった状態は気道を圧迫しやすいため、必ず上半身を起こした姿勢を保つようにしてください。
具体的には、ベッドの背もたれを上げて半座位(はんざい)にするか、椅子に座らせるのが効果的です。
さらに呼吸を楽にするためには、テーブルに肘をついて前傾姿勢を取らせる方法も有効です。
この姿勢は呼吸筋の働きを助け、気道を広げやすくする効果があります。
状態が比較的落ち着いているときには、鼻からゆっくり息を吸い、お腹を膨らませ、口からゆっくり吐くといった腹式呼吸を試みることも呼吸を整える助けになります。
ただし、強い呼吸困難がある場合には無理に指導せず、まずは姿勢の確保を優先しましょう。
【参考情報】『【知識編】効率の良い呼吸方法』環境再生保全機構
https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/copd/effective/02.html
2-2. 環境調整による症状軽減
応急処置において、周囲の環境を整えることも症状の軽減に大きく寄与します。
まず重要なのは換気です。
新鮮な空気を室内に取り入れることで酸素濃度を高め、呼吸を楽にすることができます。
ただし、外気に花粉やほこりが多い場合は、適度な換気に留めるよう注意してください。
室内の湿度調整も重要な要素です。
乾燥した空気は気道を刺激するため、加湿器や濡れたタオルで室内の湿度を50~60%程度に保つよう心がけてください。
また、タバコの煙や香水、芳香剤などの刺激物を遠ざけることも大切です。
【参考情報】”Managing Asthma in the School Environment” by U.S. EPA
https://www.epa.gov/iaq-schools/managing-asthma-school-environment
3. 薬物療法による発作時対応

医師から処方されている発作時の薬がある場合、それらを適切に使用することが症状改善の鍵となります。
喘息の発作時に使用される薬は主に気管支拡張薬で、これらは「リリーバー(発作治療薬)」と呼ばれ、狭くなった気道を素早く広げる働きがあります。
3-1. 気管支拡張薬の適切な使用方法
最も一般的な発作時の薬は、短時間作用性β2刺激薬と呼ばれる気管支拡張薬です。
この薬は吸入薬として処方されることが多く、効果が現れるまでの時間が短いのが特徴です。
薬の使用タイミングは、発作の症状が現れたらできるだけ早期に使用することが重要です。
使用方法については、必ず医師から指示された回数と間隔を守ってください。
一般的には、最初の吸入から15~20分後に症状の改善を確認し、効果が不十分であれば医師の指示に従って追加の吸入を行います。
ただし、自己判断で頻繁に使用したり、指示された量を超えて使用したりすることは危険ですので絶対に避けてください。
薬の効果は、呼吸状態や喘鳴、顔色、会話の様子などをみて判断します。
症状が明らかに改善し、お子さんが楽になったと感じられるようであれば、薬が効いていると判断できます。
しかし、効果が不十分である場合や一時的に改善しても再び症状が悪化する場合は、医療機関への受診を検討する必要があります。
3-2. 吸入器の正しい操作技術
吸入薬の効果を最大限に発揮するためには、正しい吸入技術を身につけることが不可欠です。
プレッシャー定量噴霧式吸入器を使用する場合は、容器をよく振ってから、お子さんに背筋を伸ばした姿勢を取らせてください。
基本的な手順は以下の通りです:
いったん息を吐いてから吸入器をくわえ、薬剤を放出するタイミングに合わせてゆっくりと深く息を吸い込みます。吸入後は10秒程度息を止め、その後口をゆすいでください。使用した時間と回数の記録も重要です。
【参考情報】”Know How to Use Your Asthma Inhaler” by U.S. Centers for Disease Control and Prevention
https://www.cdc.gov/asthma/pdfs/Inhaler_Spacer_FactSheet.pdf
【参考情報】”EXHALE Guide for People With Asthma, Their Families, and Caregivers” by U.S. Centers for Disease Control and Prevention
https://www.cdc.gov/national-asthma-control-program/php/exhale/pdfs/EXHALE-Guide-People-with-Asthma-Families-Caregivers-508.pdf
3-3. 薬物療法の限界と次のステップ
指示された薬を適切に使用しても症状が改善しない場合は、家庭での対応には限界があると認識しましょう。
このような状況では、より強力な治療や専門的な評価が必要となる可能性が高く、早めに医療機関を受診すべきです。
重要なのは、決して自己判断で薬の使用量を増やしたり、処方されていない薬を使用したりしないことです。
また、症状が改善しないからといって何もしないのも適切ではありません。
継続的な観察と適切なタイミングでの医療機関受診が、お子さんの安全を確保する上で最も重要です。
なお、発作時に使用される薬剤にはさまざまな種類があり、それぞれに効果や副作用、適切な使い方があります。
たとえば「サルタノールインヘラー」などが代表的な例で、その特徴については以下の記事で詳しく紹介されています。
薬剤の特性を理解することは、正しい使用と安全な管理につながります。
◆「サルタノールインヘラー」の特徴や副作用について解説!>>
【参考情報】”Pediatric Asthma” by NCBI / StatPearls (U.S. National Library of Medicine)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK551631/
4. 状況別の具体的対応戦略

喘息の発作は時と場所を選ばず発生するため、様々な状況に応じた対応策を準備しておくことが重要です。
4-1. 夜間発作への対応とポイント
夜間の喘息発作は特に注意が必要で、多くの喘息患者において症状が悪化しやすい時間帯として知られています。
夜中にお子さんが発作を起こした場合、まず確認していただきたいのは睡眠への影響程度です。
軽い喘鳴があってもぐっすりと眠っている場合は、無理に起こして薬を使用する必要はありません。
夜間の対応では、照明の使い方にも配慮が必要です。
間接照明や手元灯を使用し、優しい光の中で対応することを心がけてください。
また、ベッドを少し起こしたり、クッションで上半身を支えたりして、楽な姿勢を確保してあげることも重要です。
夜間に備えて、寝室には常に発作時の薬を手の届く場所に置いておくことをお勧めします。
4-2. 学校や外出先での発作管理
学校や外出先での発作対応には、事前の準備と関係者との連携が不可欠です。
学校では担任の先生だけでなく、保健室の先生にも喘息の状態と発作時の対応について詳しく伝えておくことが重要です。
お子さんの発作の特徴、使用している薬の種類と使用方法、発作時の連絡先などを明記した書面を提出することをお勧めします。
外出時には必ず発作時の薬を携帯することを習慣づけてください。
外出先で発作が起きた場合は、まず人混みから離れ、静かで風通しの良い場所に移動することを優先します。
そして普段通りの応急処置を実施し、症状が改善しない場合は、近くの医療機関を受診してください。
4-3. 季節・天候変化に対する予防的対応
喘息は季節の変わり目や天候の変化に影響を受けやすい疾患です。
春季には花粉飛散情報をチェックし、マスク着用や帰宅時の花粉除去を心がけてください。
梅雨時期は室内の除湿とカビ対策、夏季はエアコンフィルターの清掃と適切な温度設定、冬季は加湿と防寒対策が重要です。
特に台風や低気圧の接近時には、気圧変化の影響で症状が悪化しやすくなります。
天気予報を注意深く確認し、気圧の急激な変化が予想される日は、予防的に薬の使用を検討することも必要です。
【参考情報】『天気とぜん息の関係を知っておきましょう①』環境再生保全機構
https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/sukoyaka/column/202207_1/
【参考情報】”Controlling Childhood Asthma and Reducing Emergencies” by U.S. Centers for Disease Control and Prevention
https://www.cdc.gov/national-asthma-control-program/php/about/ccare.html
5. 医療機関受診の判断基準と緊急度評価
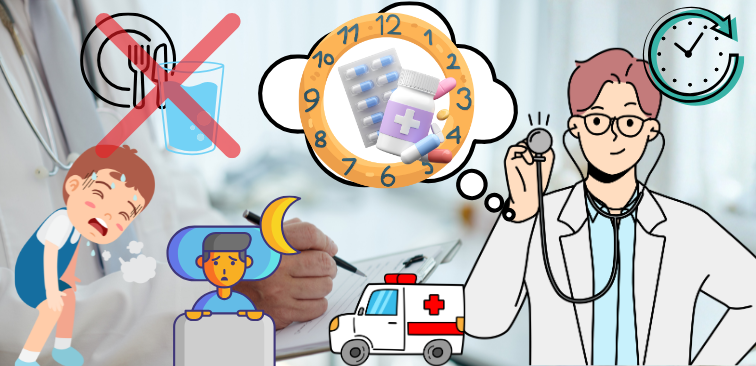
家庭での応急処置と医療機関での専門的治療の境界を見極めることは、お子さんの安全を守るために重要です。
喘息の症状は徐々に悪化する場合もあれば、急激に重篤化することもあります。
受診のタイミングを誤らないことが、早期の適切な治療につながります。
5-1. 家庭観察継続の判断基準
気管支拡張薬を使用した後に症状が明らかに改善し、お子さんが普段通りに会話でき、食事や水分の摂取にも支障がない状態であれば家庭での経過観察が可能です。
特に、顔色が通常と変わらず落ち着いて横になって休むことができていれば、一時的に状態が安定していると判断できます。
ただし症状が再び強まる可能性もあるため、30分から1時間ごとに状態を確認しながら慎重に見守ることが大切です。
【参考情報】『小児のぜん息/Q&A』日本アレルギー学会
https://www.jsaweb.jp/modules/citizen_qa/index.php?content_id=2
5-2. 医療機関受診を要する症状
気管支拡張薬を使用しても十分な効果が得られない場合は、速やかに医療機関を受診してください。
また、明らかに呼吸が苦しそうで横になることができない、会話が途中で途切れる、肋骨の間がへこむような呼吸(陥没呼吸)が見られるといった場合も医師の診察が必要な状態です。
加えて、食事や水分が摂れない、夜間に眠ることができないなど日常生活に明らかな支障が出ている場合には、ためらわずに受診することをおすすめします。
【参考情報】『子どもの救急ってどんなとき?~喘息(ぜんそく)の発作が出た時』群馬県健康福祉部
https://www.pref.gunma.jp/page/4135.html
5-3. 救急搬送が必要な緊急事態
次のような状態が見られる場合は、直ちに救急車を要請してください。
たとえば、動くことができないほどの呼吸困難や、唇や舌、指先が青紫色に変色するチアノーゼが現れている場合、また、呼びかけに反応が乏しくぐったりしているなど意識レベルに変化がある場合は、緊急の対応が必要です。
呼吸の動きに異常がある場合や、普段とは異なる激しい症状が出現したときも迷わず119番通報を行ってください。
医療機関を受診する際には、これまでの症状の経過や使用した薬の種類・回数、日常的に行っている治療内容を正確に伝えることが重要です。
お薬手帳や診療情報がわかる書類も必ず持参するようにしましょう。
【参考情報】”Childhood Asthma — Mayo Clinic” by Mayo Clinic
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/childhood-asthma/symptoms-causes/syc-20351507
6.おわりに
お子さんの喘息発作は突然起こるため、保護者として正しい知識を持っておくことが何より重要です。
まずは落ち着いて楽な姿勢を取らせ、環境を整え、必要に応じて処方薬を使用してください。
症状が改善しない場合や重篤なサインがある時は、迷わず医療機関を受診しましょう。
適切な対応により、お子さんは安心して日常生活を送ることができます。
不安な時は一人で悩まず、かかりつけ医にご相談ください。
【参考情報】”Asthma — U.S. Centers for Disease Control and Prevention” by U.S. Centers for Disease Control and Prevention
https://www.cdc.gov/asthma/index.html



